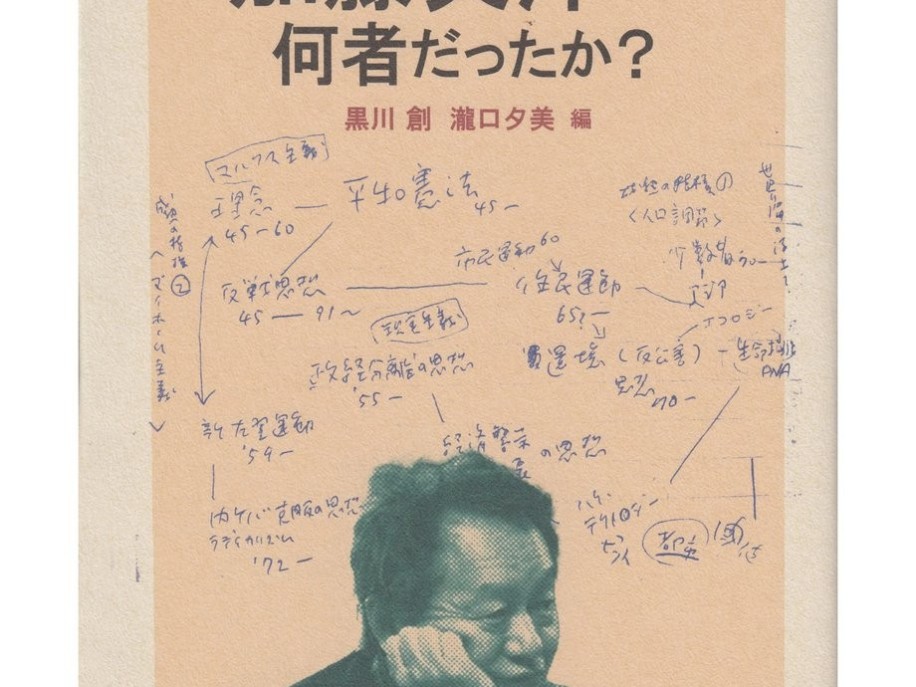書評
『「人間の時代」への眼差し』(講談社)
不意の悲劇、事故にどう対応
著者は最近、「犠牲(サクリファイス)――我が息子・脳死の11日」(「文芸春秋」4月号)という手記を発表した。次男の突然の自死という厳しい現実を前に、「救命センターのガランとした一角を衝立(ついたて)で仕切った待合コーナーのベンチに、みじめに打ちひしがれて」待つ苛酷(かこく)な運命に見舞われた。だが、そこにも新しい出発があると信じるほかはないのだ。本書は長年にわたりガンやその他の病気と医学の歩みについて、あるいは航空機事故などきわめて現実的な悲劇をも対象に取材し作品を書いてきた著者が、折に触れ記したコラムの集成である。科学技術の肥大化に対し「人間の時代」をあえて対置した意図は、例えばガンの先端治療ばかりでなく痛みをやわらげるためにどうするか、という人間的な課題が置き去りにされやすいからである。
こんな体験もさりげなく披瀝(ひれき)されている。サイパンでDC10が離陸した直後、突然、背後でドーンと大音響がする。心臓が早鐘のように鼓動を早めた。自分をコントロールするために事態がどの程度のものか把握しようと努めた。後方を見てもエンジンは見えないが乗客が騒いでいないことから推定すれば火災にはなっていないだろう。客室の与圧は抜けていないから胴体に穴はあかなかったろう。機の姿勢は安定しているから尾翼や操縦系統に異常は生じていないだろう。DC10には三基のエンジンがあるが一基が駄目でも操縦系統がダメージを受けていなければ着陸に支障はない。著者は「科学的な知識による自己のコントロール」で冷静になり、機長の「第一エンジンが爆発したのでグァムに緊急着陸する」というアナウンスを聞く。ちなみに日本人スチュワーデスは「エンジントラブルのため」としか訳さなかった。
ガンにしろ事故にしろ、あるいはストレス過多による心の軋轢(あつれき)にしろ、現代社会には不意の悲劇が待ち構えている。避けることが不可能としても、依然としてバランスのとれた認識が救済への第一歩に違いないのである。
ALL REVIEWSをフォローする