書評
『平安京はいらなかった: 古代の夢を喰らう中世』(吉川弘文館)
住むに不便な未完の都
古代の都は、天皇を頂点とする社会(身分)秩序を目に見える形で建造物の形・規模・配置に表現し、その秩序を日々体感させて再生産するシステムであった。延暦13(794)年に成立した平安京では、羅城門と大内裏を結ぶ幅82㍍の朱雀大路が設けられたが、それは外国使節を迎えることと天皇の即位礼(大嘗会<だいじょうえ>)を主な目的とする天皇の権威を示す装置であり、そもそも住民の居住性への配慮はなかった。
そのため、現実には大路で牛馬の放牧がおこなわれたり、築地塀が通行に便利となるよう崩されたりしたのである。
特に唐との対抗を強く意識した平安京は、国力に比べて規模が大き過ぎるという弱点もあった。平安京はそもそも唐の長安のように城壁で四囲を固めることもなく、南の羅城門の左右にだけ土塀を設けた装飾的なものにすぎなかった。
私たちは平安京といえば整然と条里で区切られた長方形のプランを考えてしまう。しかし、それはあくまでプランであって、現実には着工すらされなかった部分が相当あった。それは特に西側の葛野川(桂川)の流域で顕著だったという。
こうして摂関政治、すなわち藤原氏による天皇の代行という時代に入った10世紀には平安京は未完のまま、本来の機能を失っていった。平安京の羅城門は天元3(980)年に倒壊したまま、再建されることはなかった。そして倒壊した建物の礎石が新時代にふさわしい記念物に再利用されるなど、平安京そのものの解体が進行していく。
流れを決定的にしたのは11世紀、白河法皇の時代である。法皇が鴨川東岸、白河の地に築いた広大な院御所と巨大な寺院群は、新しい権威をこれまでと異なる形式で視覚的に示し、平安京から中世的な京都への転換の第一歩ともなるべきものであった。
中世史を専門とする著者が、平安京の崩壊という視点から京都の成立を展望した点がこれまでにない新鮮な視点を与えてくれる。
[書き手] 春名 徹(はるな あきら・ノンフィクション作家)
初出メディア
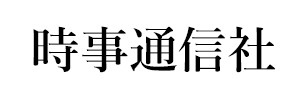
時事通信社 2016年12月
ALL REVIEWSをフォローする



































