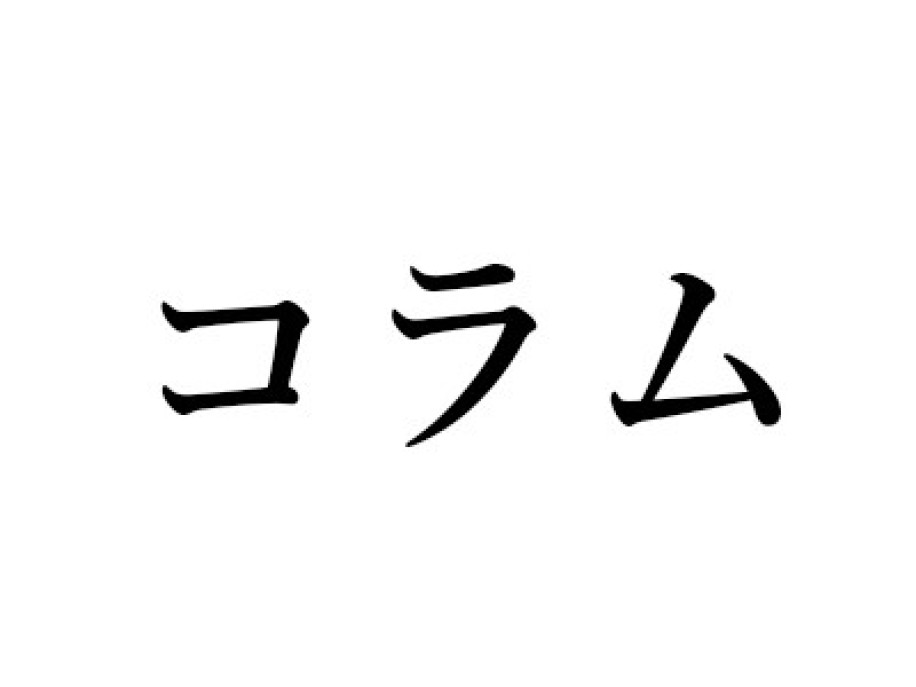後書き
『ステータス・ゲームの心理学: なぜ人は他者より優位に立ちたいのか』(原書房)
自分の地位をめぐる不安に人間は常につきまとわれ、それが行動を規定している。心理学・人類学・社会学・経済学・歴史学の研究をもとに人生の隠された構造を読み解き、サヴァイヴするための啓蒙の書『ステータス・ゲームの心理学』より、訳者あとがきを公開します。
ですが本書を読むと、このような道徳観念の正体が実は普遍的なものでもなんでもなく、脳が紡ぎだした幻想にすぎないことがわかってきます。こうした幻想を共有した者同士でステータスをひたすら競いあうのが人生というものだと、著者のストー氏は一貫して主張します。これはなかなか受け入れがたい考えかもしれません。人類みな平等こそ当たり前によいものとする世間一般の信念とは明らかに矛盾するからです。しかし、自分の身近な例に照らしあわせてみても、いまの道徳的価値観がほんのひと昔前と比べてもずいぶん異なってきていること、人より高いステータスを得られたときのこのうえない喜び、逆に自分が人より劣っていると感じたときの屈辱など、思い当たる節がたくさんあることに気づかされます。
本書では、なぜ人間がこのように高度に道徳的でありながらステータス・ゲームをせずにはいられない動物になったのかが、脳の仕組みや進化の過程から丁寧に紐解かれます。力ずくでステータスを得ていた人類以前の支配ゲームから、集団で行動するようになり、輪を重んじつつ人より多くのステータスを得るために編みだした美徳ゲーム、そして個人主義の成功ゲームへと、脳が少しずつ配線を変えていった経緯をたどることで、わたしたちが現在抱えている数々の社会問題の根幹にある原因が浮き彫りにされていきます。
著者ストー氏は、人の自意識や現実認識など、ステータスを追い求める人間の本質に関わる諸テーマと長年向きあってきました。本書につながる著書として、『異端児たち(The Heretics)』(未邦訳、2013年)、『セルフィー(Selfie)』(未邦訳、2017年)、『ストーリーテリングの科学(The Science of Storytelling)』(未邦訳、2019年)が出版されており、いずれも高い評価を得ています。それぞれの内容については、本書のプロローグでも触れられていますので、ぜひ参考にしてみてください。また、ストー氏はナショナル・プレス・クラブ・アワードを受賞するなどジャーナリストとしても多くの社会問題を扱っているほか、フィクション作品も手がけています。今回の邦訳を機に、社会や人間に対する彼の鋭くウィットに富んだ思考の一端が日本にも広く知られるようになれば幸いです。
本書を翻訳中に、ロシアがウクライナに侵攻しました。これほどまで進化を遂げ、道徳観念や個人の能力を高めてきた人間が、なぜまたこのような暴走モードに陥ってしまうのかと、連日のニュースを受け止めきれずにいます。しかし、本書を通じて歴史を振り返ってみると、人はこの決して逃れられないステータス・ゲームのなかで何度となくエラーを起こしては微調整を繰り返してきた事実が見えてきます。わたしたちはまだ、進化の途中なのかもしれません。これから数百年、数千年、数万年とかけて、さらなる試練のたびに脳の配線を変えつづけたその先に、人類はどんな答えを導きだしているのでしょうか。
[書き手]風早さとみ(翻訳家)
平等を貴びながらステータスを手放せない人類
近年、社会正義や道徳に対する人々の意識がますます高まりつつあるように感じます。人種・ジェンダー・セクシュアリティといった多様性の未来に向かって人類が前進している明るい兆しとも言えますが、その一方で、本書内でも言及されている「キャンセル・カルチャー」のような風潮が社会問題として取り沙汰されることも多くなりました。日本でも、誰かしらが何かしらの不祥事や不適切発言を追及され、社会的抹殺に追い込まれる一連のニュースがほぼ毎日のように報じられています。こうした悪者の退場劇を、多くの人は道徳的にそうなって当然だと、すがすがしい気持ちすら抱きながら見ていたりします。このとき、わたしたちは自分の道徳観念が普遍的なもので、絶対に間違っているはずがないと信じ切っています。ですが本書を読むと、このような道徳観念の正体が実は普遍的なものでもなんでもなく、脳が紡ぎだした幻想にすぎないことがわかってきます。こうした幻想を共有した者同士でステータスをひたすら競いあうのが人生というものだと、著者のストー氏は一貫して主張します。これはなかなか受け入れがたい考えかもしれません。人類みな平等こそ当たり前によいものとする世間一般の信念とは明らかに矛盾するからです。しかし、自分の身近な例に照らしあわせてみても、いまの道徳的価値観がほんのひと昔前と比べてもずいぶん異なってきていること、人より高いステータスを得られたときのこのうえない喜び、逆に自分が人より劣っていると感じたときの屈辱など、思い当たる節がたくさんあることに気づかされます。
本書では、なぜ人間がこのように高度に道徳的でありながらステータス・ゲームをせずにはいられない動物になったのかが、脳の仕組みや進化の過程から丁寧に紐解かれます。力ずくでステータスを得ていた人類以前の支配ゲームから、集団で行動するようになり、輪を重んじつつ人より多くのステータスを得るために編みだした美徳ゲーム、そして個人主義の成功ゲームへと、脳が少しずつ配線を変えていった経緯をたどることで、わたしたちが現在抱えている数々の社会問題の根幹にある原因が浮き彫りにされていきます。
著者ストー氏は、人の自意識や現実認識など、ステータスを追い求める人間の本質に関わる諸テーマと長年向きあってきました。本書につながる著書として、『異端児たち(The Heretics)』(未邦訳、2013年)、『セルフィー(Selfie)』(未邦訳、2017年)、『ストーリーテリングの科学(The Science of Storytelling)』(未邦訳、2019年)が出版されており、いずれも高い評価を得ています。それぞれの内容については、本書のプロローグでも触れられていますので、ぜひ参考にしてみてください。また、ストー氏はナショナル・プレス・クラブ・アワードを受賞するなどジャーナリストとしても多くの社会問題を扱っているほか、フィクション作品も手がけています。今回の邦訳を機に、社会や人間に対する彼の鋭くウィットに富んだ思考の一端が日本にも広く知られるようになれば幸いです。
本書を翻訳中に、ロシアがウクライナに侵攻しました。これほどまで進化を遂げ、道徳観念や個人の能力を高めてきた人間が、なぜまたこのような暴走モードに陥ってしまうのかと、連日のニュースを受け止めきれずにいます。しかし、本書を通じて歴史を振り返ってみると、人はこの決して逃れられないステータス・ゲームのなかで何度となくエラーを起こしては微調整を繰り返してきた事実が見えてきます。わたしたちはまだ、進化の途中なのかもしれません。これから数百年、数千年、数万年とかけて、さらなる試練のたびに脳の配線を変えつづけたその先に、人類はどんな答えを導きだしているのでしょうか。
[書き手]風早さとみ(翻訳家)
ALL REVIEWSをフォローする