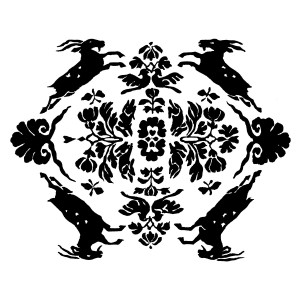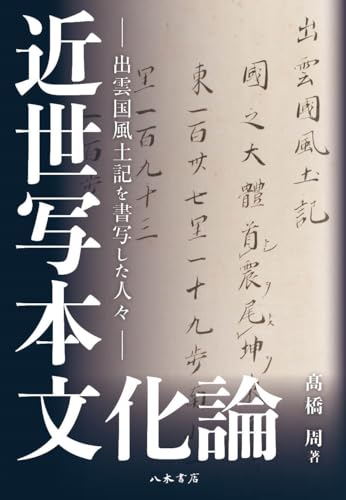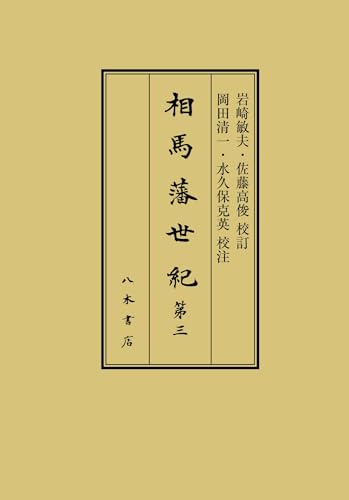自著解説
『啄木 我を愛する歌: 発想と表現』(八木書店)
なぜ石川啄木の短歌は100年の時を経てなお現代人を魅了しつづけるのか。歌集『一握の砂』の主題を形成する「我を愛する歌」151首を新たに評釈し、その魅力に迫る。
不来方(こずかた)のお城の草に寝ころびて
空に吸はれし
十五の心
やはらかに柳あをめる
北上の岸辺目に見ゆ
泣けとごとくに
このような多感な青春やつきることのない望郷への思いが、希望や不安に胸をときめかす年頃の柔らかい心に響くからでしょう。いまでは歌人としてすぐれた業績をあげている人のなかでも、短歌に関心を持ちはじめたきっかけが啄木短歌であった、という話をよく耳にします。
それはおそらく啄木短歌には技巧や知識をひけらかすようなところが感じられないからだと思います。心にうかぶ思いを素直に表現するような啄木短歌には、年齢や性差はもとより時代や地域や民族などさまざまな隔たりをこえて、ともにわかり合える魅力があります。そして啄木のように、短歌によって自分自身の思いをそのままに表現してみたいという気持ちになるのでしょう。そうした啄木短歌の魅力を凝縮したのが、1910(明治43)年に出版された『一握の砂』という歌集です。いまから100年以上もまえの短歌がいまもなお広く読みつがれていることに驚かざるをえません。
本書は啄木短歌の魅力の源泉ともいうべき『一握の砂』の主題を形成する第1章「我を愛する歌」151首を1首ごとに評釈したものです。
われ泣きぬれて
蟹とたはむる
やとばかり
桂首相に手とられし夢みて覚めぬ
秋の夜の二時
皆さんは、この「我を愛する歌」の冒頭と最後の歌をそれぞれどのように読まれるでしょうか。あるいはこの2首はまったくつながりのない歌として鑑賞されるでしょうか。それともこの2首には深いつながりがあると思われますか。「東海の小島」は啄木にかかわりのある函館の大森浜が舞台でなければならないのでしょうか。「桂首相に手とられし夢」とは、いったいどんな「夢」であったのでしょうか。さらに「東海の小島の磯の白砂にわれ泣きぬれて蟹とたはむる」「やとばかり桂首相に手とられし夢みて覚めぬ秋の夜の二時」という一行書きと、歌集の三行書きでは、イメ-ジの広がりがかわるように思いませんか。
このように『一握の砂』には、さまざまな問いかけが読者に向けてなされています。読者からすれば、ときに共感を、ときには反感をいだきながらも、その問いかけにこたえたくなります。わかりやすい表現でありながら、奥深い謎めいた問いかけが『一握の砂』にはあります。知的構築物というゆえんでもあります。まるで珠玉の短編小説を読むような醍醐味が、『一握の砂』の「我を愛する歌」にはあります。
作家にとって「作品」は人生そのものである、ということでいえば、「我を愛する歌」は啄木という詩人における人生のドラマそのものであります。すぐれた「作品」は読者の人生に大きな刺激を与える力があります。できれば、この「我を愛する歌」151首の評釈が、一人でも多くの読者によって、『一握の砂』という文学作品が読みつがれるための手引き書となることを念じています。
[書き手]太田登(おおたのぼる) 天理大学名誉教授
〔著書〕
『啄木短歌論考 抒情の軌跡』第6回岩手日報啄木賞受賞(八木書店、1991年)
『日本近代短歌史の構築―晶子・啄木・八一・茂吉・佐美雄―』(八木書店、2006年)
『与謝野寛晶子論考―寛の才気・晶子の天分―』(八木書店、2013年)
〔共編著〕
『奈良近代文学事典』(和泉書院、1989年)
『漱石作品論集成』(おうふう、1990-91年)
『一握の砂―啄木短歌の世界』(世界思想社、1994年)
さまざまな隔たりを超え読みつがれている啄木の短歌
いわゆる教科書短歌のなかでも、石川啄木の短歌は教育現場でもっとも広く知られています。不来方(こずかた)のお城の草に寝ころびて
空に吸はれし
十五の心
やはらかに柳あをめる
北上の岸辺目に見ゆ
泣けとごとくに
このような多感な青春やつきることのない望郷への思いが、希望や不安に胸をときめかす年頃の柔らかい心に響くからでしょう。いまでは歌人としてすぐれた業績をあげている人のなかでも、短歌に関心を持ちはじめたきっかけが啄木短歌であった、という話をよく耳にします。
それはおそらく啄木短歌には技巧や知識をひけらかすようなところが感じられないからだと思います。心にうかぶ思いを素直に表現するような啄木短歌には、年齢や性差はもとより時代や地域や民族などさまざまな隔たりをこえて、ともにわかり合える魅力があります。そして啄木のように、短歌によって自分自身の思いをそのままに表現してみたいという気持ちになるのでしょう。そうした啄木短歌の魅力を凝縮したのが、1910(明治43)年に出版された『一握の砂』という歌集です。いまから100年以上もまえの短歌がいまもなお広く読みつがれていることに驚かざるをえません。
本書は啄木短歌の魅力の源泉ともいうべき『一握の砂』の主題を形成する第1章「我を愛する歌」151首を1首ごとに評釈したものです。
珠玉の短編小説を読むような醍醐味
東海の小島の磯の白砂にわれ泣きぬれて
蟹とたはむる
やとばかり
桂首相に手とられし夢みて覚めぬ
秋の夜の二時
皆さんは、この「我を愛する歌」の冒頭と最後の歌をそれぞれどのように読まれるでしょうか。あるいはこの2首はまったくつながりのない歌として鑑賞されるでしょうか。それともこの2首には深いつながりがあると思われますか。「東海の小島」は啄木にかかわりのある函館の大森浜が舞台でなければならないのでしょうか。「桂首相に手とられし夢」とは、いったいどんな「夢」であったのでしょうか。さらに「東海の小島の磯の白砂にわれ泣きぬれて蟹とたはむる」「やとばかり桂首相に手とられし夢みて覚めぬ秋の夜の二時」という一行書きと、歌集の三行書きでは、イメ-ジの広がりがかわるように思いませんか。
このように『一握の砂』には、さまざまな問いかけが読者に向けてなされています。読者からすれば、ときに共感を、ときには反感をいだきながらも、その問いかけにこたえたくなります。わかりやすい表現でありながら、奥深い謎めいた問いかけが『一握の砂』にはあります。知的構築物というゆえんでもあります。まるで珠玉の短編小説を読むような醍醐味が、『一握の砂』の「我を愛する歌」にはあります。
作家にとって「作品」は人生そのものである、ということでいえば、「我を愛する歌」は啄木という詩人における人生のドラマそのものであります。すぐれた「作品」は読者の人生に大きな刺激を与える力があります。できれば、この「我を愛する歌」151首の評釈が、一人でも多くの読者によって、『一握の砂』という文学作品が読みつがれるための手引き書となることを念じています。
[書き手]太田登(おおたのぼる) 天理大学名誉教授
〔著書〕
『啄木短歌論考 抒情の軌跡』第6回岩手日報啄木賞受賞(八木書店、1991年)
『日本近代短歌史の構築―晶子・啄木・八一・茂吉・佐美雄―』(八木書店、2006年)
『与謝野寛晶子論考―寛の才気・晶子の天分―』(八木書店、2013年)
〔共編著〕
『奈良近代文学事典』(和泉書院、1989年)
『漱石作品論集成』(おうふう、1990-91年)
『一握の砂―啄木短歌の世界』(世界思想社、1994年)
ALL REVIEWSをフォローする