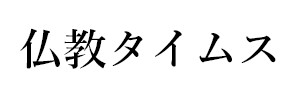書評
『信長と石山合戦―中世の信仰と一揆』(吉川弘文館)
揆を一にする力
中世末期、民衆の力を糾合し、北陸加賀に「百姓ノ持チタル国」を現出させた浄土真宗。燎原の火のごとく拡がった一向一揆の終焉を告げる最大の激戦が、石山合戦だ。しかし、11年におよぶ奮戦もむなしく織田信長の軍門に下った本願寺教団が、その後飛躍的発展を遂げていくのは何故か。「中世の信仰と一揆」というエポックを築き上げた、石山合戦の内実を縦横無尽に説き明かす。まず戦国期の本願寺教団について、「一向宗=真宗」という教科書的図式を粉砕。本願寺教団に抱え込まれた廻国聖や琵琶法師、修験者や巫女など、呪術的祈祷をよくした民間宗教者の教義こそ「一向宗」の実態であるとし、雑行雑修を排した親鸞や蓮如のそれではないと述べる。
すなわち為政者たちは、弥陀一仏に帰依する合理的な真宗の教義を警戒したのではなく、民心を一揆へと結束させていく、一向宗の強大な呪力を恐れたのである。膨大な中世文書の断片から、戦国末期の躍動する時代層を掘り起こす著者の手腕は鮮やかである。
一向一揆を、〈支配層に抗した民衆の下剋上〉という通説だけで捉えることはできない。では、伊勢長島・越前の一揆勢殲滅に、信長が込めた苛烈なメッセージとは何だったのか。そして、極楽往生のためではなく、親鸞聖人への報恩謝徳のために蜂起した門徒の想いとはどのようなものだったのか――。
見開きにカラーで掲載された「血判阿弥陀画像」は、後世のものながら一揆衆の固い絆を偲ばせる貴重なよすがであろう。
[書き手] 山崎一昭(新聞記者)
ALL REVIEWSをフォローする