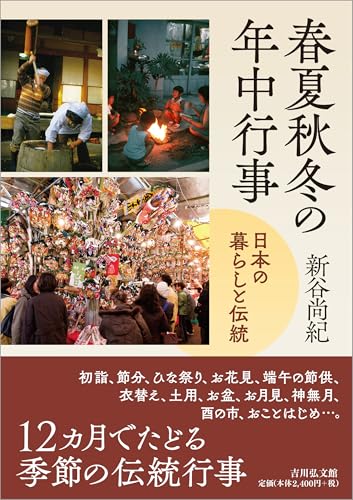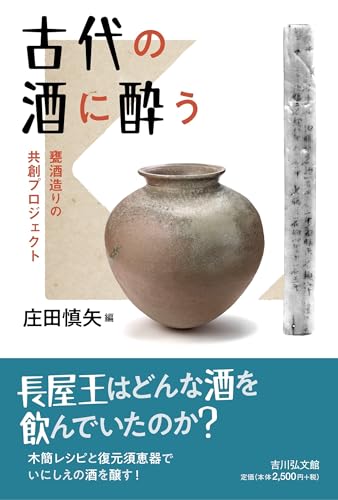後書き
『人間がいなくなった後の自然』(草思社)
戦争、原子炉のメルトダウン(炉心溶融)、自然災害、砂漠化、毒化、放射能汚染、経済崩壊に見舞われた場所……これらの壊滅的な被害を受けて人間がいなくなった場所では、なんと人間が存在しないことによって、生物たちがそこで新生し、地球上でも独特な豊かさを誇る場所になっているのです。これらの場所を訪れ、自然の回復・新生の実態を追った環境論の最先端を示す意欲作が本書です。ダークツーリズムや廃墟趣味の要素を含みつつも、それにとどまらない、新時代の環境論になっています。この本は、訪れた場所の性質から、人間の負の行為をたどる「暗黒の書」のようにも見えますが、著者はむしろ「救済の書」だといいます。「私が注目するのは、地平線の彼方に消えてゆく手つかずの自然の残照ではなく、夜明けの山際を照らす朝日の光である。ますます多くの土地が廃墟となっている今、その光は新たな野生の新たな夜明けを示しているのかもしれない」――人間の業を見つめながら、同時に自然の驚異的な力を描き出す本書から、そのエッセンスをまとめた訳者あとがきをお送りします。
「激しく破壊され、略奪され荒れ果て、汚染され毒された場所に、私は新しい生命が生まれつつあるのを見た。古いものの残骸から、その回復力によって、奇妙で、より有用性の高い生命が生まれてくるのを見た。」
本書の著者は、時々、そこにはないものを見ている。今は原野になっている場所に風に揺れる穀物の畑を見たり、使われなくなった畜舎の外で牛の群れが白い息を吐きながら歩くのを見たり、チェルノブイリのホットスポットでγ線が自分の体を通り抜けるのを感じたりする。確かに、遺跡や歴史的な建造物などに入ると、自分が過去のその時代に身を置いたような気になることはある。 「空気の中に漂う、過去の霊的啓示や信仰の危機などの感情の痕跡をあなたも感じることができるはずだ」とも著者は語るが、これはどうだろう。そこまで感じ取れる人は少ないのではないだろうか。
本書で、著者カル・フリンは多くの参考書籍や映画に言及している。その中でも一九七九年制作の旧ソ連の映画『ストーカー』は不思議な雰囲気を持つ。旧ソ連の映画をめったに見たことがないせいか、エキゾチックな画像に惹きつけられる。
[書き手]木高 恵子(きだか・けいこ)
淡路島生まれ、淡路島在住のフリーの翻訳家。短大卒業後、子ども英語講師として小学館ホームパルその他で勤務。その後、エステサロンや不動産会社などさまざまな職種を経て翻訳家を目指し、働きながら翻訳学校、インタースクール大阪校に通学し、英日翻訳コースを修了。訳書に『ビーバー: 世界を救う可愛いすぎる生物』(草思社)がある。
「朽ち果てたコンクリートと有毒廃棄物に安らぎを感じる」
本書は、本書の著者カル・フリン(Cal Flyn)が訪れた世界の一二カ所の土地について述べる紀行文の形式をとっている。ただし、読者にその地へ行きたいと思わせるような風光明媚な土地の紀行文ではない。どちらかと言えば、絶対に行きたくないような危険で不潔でさびれた土地ばかりである。著者カル・フリンが、本書でこのような土地を訪れたのには理由がある。著者の信念である「人間がいなくなると、自然は予想以上の速さで回復する」を実際に現地に出かけて、自分の五感を駆使して、証明するためである。著者はたまに第六感も駆使しているように見える。そのような土地が嫌いではないという著者の好みもあるのかもしれない。都市探検家のウィーラーが、「朽ち果てたコンクリートと有毒廃棄物に安らぎを感じる」と書いているのを読んで、本書の著者であるカル・フリンは、ウィーラーと自分には共通点があると述べている。著者は二年かけて、世界のあちこちにある、人間に見捨てられた一二の場所を訪れている。それらの土地が見捨てられた理由は、戦争、災害、病気、経済の衰退など、さまざまである。危険を顧みず、自分の足で「見捨てられた土地」を歩く
今も危険が残るチェルノブイリ、産業の衰退とともに荒廃都市となったアメリカのデトロイト、ドラッグ常用者の作り出す無政府状態のニュージャージー州パターソン、化学兵器の毒が残るフランスのゾーン・ルージュ、砂浜が、死んだ魚の骨でできているカルフォルニアのソルトン湖など、どんな危険に巻き込まれてもおかしくはない場所である。著者カル・フリンが本書の執筆後にインタビューを受け、訪れた土地で最も恐怖を感じたのはどこかと聞かれた質問に答えている。それはスコットランドのスウォナ島だった。だれもいないはずの無人島で、一人で寝ようとしていたときにその家の中で何かが走る音を聞いたときほど怖い思いをしたことはなかったという。そのためこの島では食べることも眠ることもできなかったとのことである。その土地の「見えないもの」を感じ取る
終章では聖書の引用や神秘主義的な引用も出てくるが、カル・フリン自身は、 「私は神秘主義者ではない。神の訪問を受けたこともないし、告知を受けたこともない」と、はっきり述べている。神の力に頼るだけの人ではないからこそ、著者はこのような土地を実際に訪れ、自分の足で歩いて、そこに植物や動物が力強く再生している姿を探しに行ったのではないだろうか。そして実際に見つけたのである。著者は、次のように述べている。「激しく破壊され、略奪され荒れ果て、汚染され毒された場所に、私は新しい生命が生まれつつあるのを見た。古いものの残骸から、その回復力によって、奇妙で、より有用性の高い生命が生まれてくるのを見た。」
本書の著者は、時々、そこにはないものを見ている。今は原野になっている場所に風に揺れる穀物の畑を見たり、使われなくなった畜舎の外で牛の群れが白い息を吐きながら歩くのを見たり、チェルノブイリのホットスポットでγ線が自分の体を通り抜けるのを感じたりする。確かに、遺跡や歴史的な建造物などに入ると、自分が過去のその時代に身を置いたような気になることはある。 「空気の中に漂う、過去の霊的啓示や信仰の危機などの感情の痕跡をあなたも感じることができるはずだ」とも著者は語るが、これはどうだろう。そこまで感じ取れる人は少ないのではないだろうか。
本書で、著者カル・フリンは多くの参考書籍や映画に言及している。その中でも一九七九年制作の旧ソ連の映画『ストーカー』は不思議な雰囲気を持つ。旧ソ連の映画をめったに見たことがないせいか、エキゾチックな画像に惹きつけられる。
故郷、淡路島の自然も変化している
私事ながら私は生まれ育った淡路島に五〇年ぶりに帰郷している。昔と同様に、田舎の空気はおいしい。明石海峡大橋をバスでわずか五分間ほど通過するだけなのだが、高速バスを降りると深呼吸したくなる。都会に比べ酸素が多いように思う。昔と同じように草花が咲き乱れている。黄色、ピンク、紫と、形も色も愛らしい野の花々で、だれも手入れしなくても実に生き生きと生い茂っている。その中でも鮮やかなピンクの丸い形のランタナと呼ばれる花は特に愛らしい。真ん中が黄色でその周りがピンクというのもあれば、ピンク一色のもある。川の土手から川べりまで広い範囲の斜面にこの花だけが咲き誇っている様子は極楽のシーンのようだ。しかし、この花は私が子どもの頃は見たことがない。環境省の「要注意外来種生物リスト」に指定されている。繁殖力が旺盛すぎて増えすぎるらしい。種子には毒があって注意が必要だ。[書き手]木高 恵子(きだか・けいこ)
淡路島生まれ、淡路島在住のフリーの翻訳家。短大卒業後、子ども英語講師として小学館ホームパルその他で勤務。その後、エステサロンや不動産会社などさまざまな職種を経て翻訳家を目指し、働きながら翻訳学校、インタースクール大阪校に通学し、英日翻訳コースを修了。訳書に『ビーバー: 世界を救う可愛いすぎる生物』(草思社)がある。
ALL REVIEWSをフォローする