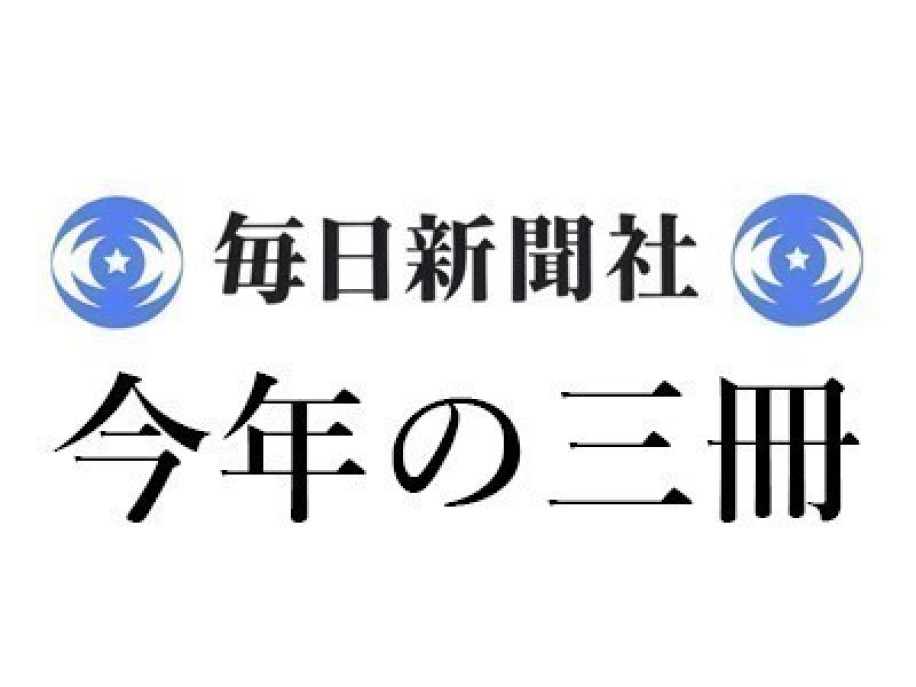書評
『巡礼』(新潮社)
橋本治の頭の中を覗いてみたい。四六時中何か考えていて、少しでも「?」ときたら、そのことについて何らかの「!」を導き出すまでは考えるのを止めない人、そんなイメージゆえに。で、脳にジャックインするのは不可能だから、著書からその思考の流れの一端を知ろうとするわけだけれど、この人がすごいのは「?」を「!」に変える試みを小説でもしてしまうところなのだと、『巡礼』を読んで改めて感心してしまった次第。
私有地内に、常軌を逸して大量のゴミを溜め込んだ老人に対する、周辺住民の怒り――この小説はそんな構図から始まる。取材に来たワイドショーのレポーターに答える主婦。なんだか、とっても通俗的。と思いきや、すぐに始まるのである、考えることが。風向きによっては悪臭に悩まされるものの、住居の位置関係的には直接の被害に遭っているわけではない、この矢嶋富子という傍観者的な主婦の内面すら徹底考察。いわんや、ゴミ屋敷の真ん前の家に住む吉田夫人の心の叫びにおいてをや。主にこの二人の女性の思考をたどることで、橋本さんは地域社会における過去と現在の人間関係の変化を明らかにし、地域住民として生きるわたしたちの周囲についての“理解”がいかに恣意的であるかや、そんないい加減な情報に基づいて発動する善意や悪意の不気味さを暴き、専業主婦がずっと漠然と抱えてきたレゾンデートル(存在理由)の不安や不満を露わにしてしまうんである。
その徹底思考は、もちろん、ゴミ屋敷の独居老人・忠市にも及ぶ。中学一年で終戦を迎え、商業高校を卒業すると、町の大きな荒物問屋「能登商店」に就職。六畳間に六人の奉公人が寝起きする劣悪な労働条件下、真面目に働くものの、小遣いに毛が生えた程度の給料では飲みに行ったり、赤線で女を買うこともできず、かといってどこに行けば素人女性と恋愛ができるのかもわからないまま、二十六歳に。やがて、生まれ育った小さな町にも発展の波が押し寄せ、実家の荒物屋が駅前の整備計画に引っかかると、父親はその立ち退き料で別の土地を買い、瓦屋という新しい商売を始めることを決意。それを機に実家に呼び戻され、恋愛経験のないまま見合いでおとなしい女性と結婚することになる忠市がゴミじじいと化すまでの、ささやかな有為転変を描く中、作者の橋本さんは戦後六十余年間における個人の、家族の、社会の、日本のあり方がどのように変わっていったのかを論理的に追求していくのだ。
しかし――。自分が集めた物がゴミであることも、片付けなくてはいけないこともわかっている忠市が、なぜ他人から見ればゴミにすぎないものを集め、貯めこむのを止めないのか。それは、ゴミの山のどこかにとても大事な何かがあると信じているからなのである。ゴミを〈片付けられて、すべてがなくなって、元に戻った時、生きて来た時間もなくなってしまう。生きて来た時間が、「無意味」というものに変質して、消滅してしまう〉ことに怯えているからなのである。忠市の大事なものとは何なのか、そもそもの最初に拾ったゴミが何であったのかが明かされる場面と、ゴミ騒動に決着がつく最終章がもたらす痛ましさと優しさは、理詰めではない。徹底的に理を追求してきた橋本さんの筆が、その場面に至って情に傾くのだ。
そして――。このような“情”をおろそかにしてきたことが、戦後日本の最大の問題点なのではないか。なんでこの国ってこんなになっちゃったのという「?」を論理で解き明かそうとしている小説から、わたしはそんな逆説的な「!」を読み取ったのである。
【この書評が収録されている書籍】
私有地内に、常軌を逸して大量のゴミを溜め込んだ老人に対する、周辺住民の怒り――この小説はそんな構図から始まる。取材に来たワイドショーのレポーターに答える主婦。なんだか、とっても通俗的。と思いきや、すぐに始まるのである、考えることが。風向きによっては悪臭に悩まされるものの、住居の位置関係的には直接の被害に遭っているわけではない、この矢嶋富子という傍観者的な主婦の内面すら徹底考察。いわんや、ゴミ屋敷の真ん前の家に住む吉田夫人の心の叫びにおいてをや。主にこの二人の女性の思考をたどることで、橋本さんは地域社会における過去と現在の人間関係の変化を明らかにし、地域住民として生きるわたしたちの周囲についての“理解”がいかに恣意的であるかや、そんないい加減な情報に基づいて発動する善意や悪意の不気味さを暴き、専業主婦がずっと漠然と抱えてきたレゾンデートル(存在理由)の不安や不満を露わにしてしまうんである。
その徹底思考は、もちろん、ゴミ屋敷の独居老人・忠市にも及ぶ。中学一年で終戦を迎え、商業高校を卒業すると、町の大きな荒物問屋「能登商店」に就職。六畳間に六人の奉公人が寝起きする劣悪な労働条件下、真面目に働くものの、小遣いに毛が生えた程度の給料では飲みに行ったり、赤線で女を買うこともできず、かといってどこに行けば素人女性と恋愛ができるのかもわからないまま、二十六歳に。やがて、生まれ育った小さな町にも発展の波が押し寄せ、実家の荒物屋が駅前の整備計画に引っかかると、父親はその立ち退き料で別の土地を買い、瓦屋という新しい商売を始めることを決意。それを機に実家に呼び戻され、恋愛経験のないまま見合いでおとなしい女性と結婚することになる忠市がゴミじじいと化すまでの、ささやかな有為転変を描く中、作者の橋本さんは戦後六十余年間における個人の、家族の、社会の、日本のあり方がどのように変わっていったのかを論理的に追求していくのだ。
しかし――。自分が集めた物がゴミであることも、片付けなくてはいけないこともわかっている忠市が、なぜ他人から見ればゴミにすぎないものを集め、貯めこむのを止めないのか。それは、ゴミの山のどこかにとても大事な何かがあると信じているからなのである。ゴミを〈片付けられて、すべてがなくなって、元に戻った時、生きて来た時間もなくなってしまう。生きて来た時間が、「無意味」というものに変質して、消滅してしまう〉ことに怯えているからなのである。忠市の大事なものとは何なのか、そもそもの最初に拾ったゴミが何であったのかが明かされる場面と、ゴミ騒動に決着がつく最終章がもたらす痛ましさと優しさは、理詰めではない。徹底的に理を追求してきた橋本さんの筆が、その場面に至って情に傾くのだ。
そして――。このような“情”をおろそかにしてきたことが、戦後日本の最大の問題点なのではないか。なんでこの国ってこんなになっちゃったのという「?」を論理で解き明かそうとしている小説から、わたしはそんな逆説的な「!」を読み取ったのである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする