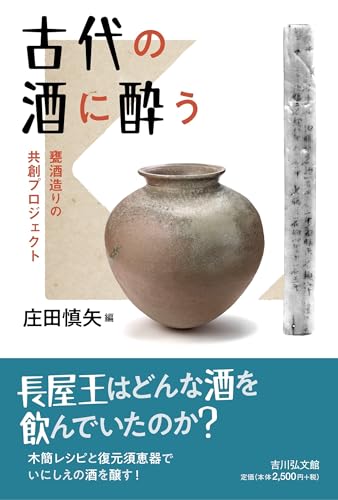書評
『柄谷行人『力と交換様式』を読む』(文藝春秋)
精神医療の試みとして「回帰」する「対話」
2022年に上梓(じょうし)された大著『力と交換様式』の解説書。本書はさしあたり、そのように位置づけることもできる。近年、ジャレド・ダイアモンドやユヴァル・ノア・ハラリらによる人類史がベストセラーになっているが、『力と交換様式』は、その哲学版とみることもできる。ただしダイアモンドやハラリよりもはるかに明晰で、それゆえの難解さがあった。本書は柄谷自身のほか、大澤真幸、渡邊英理らの「解説」によって、平易かつ立体的な理解が可能になっている。著者は、人類史を交換様式の発展の歴史としてとらえようとする。マルクスは歴史を決定づける要因として「経済的下部構造」、すなわち生産様式を挙げた。柄谷はそれに代わって交換様式を重視し、様式をA~Dの四つに分類する。すなわちA:互酬(ごしゅう)(贈与と返礼)、B:服従と保護(略取と再分配)、C:商品交換(貨幣と商品)、D:Aの高次元での回復と。いずれの交換においても物質だけではない「力」が作用している。すなわち、Aにはマルセル・モースが指摘した「ハウ」が、Bにはホッブズが名付けた「リヴァイアサン(海の怪獣)」が、そしてCにはマルクスの指摘した「物神(フェティッシュ)」といった霊的・観念的な諸力である。
以上の変遷を踏まえた上で、柄谷は「交換様式D」の到来を主張する。すでに限界の見えてきたBとC、すなわち国家や資本を揚棄することはできない。揚棄の試みそれ自体が、BとCの回復につながってしまうからだ。ならば、いかにしてDを到来させるのか。Dは交換様式A、すなわち「互酬(贈与と返礼)」の「高次元での回復」とされている。しかし、これが難しい。実は柄谷は、Dの具体的なイメージを明示していないからだ。繰り返されるのは、それが一種の「原初への回帰」であり、ユートピアの到来でもあるということ。そしてDは霊的な力として「向こうからやってくる」のであり、その到来を意図的に実現することはできない、ということだ。
Dのイメージについて、本書の中に有効な補助線を見つけた。東畑開人による解説である。東畑は交換様式の変遷をカウンセリングにあてはめる。するとAは「友」による互酬的ケア、Bは「親」的なセラピストによる治療、Cは「店」、すなわち商売としてなされる心理療法に相当する。その上で東畑はDを「鬱」であるとするのだが、その点はしばし措こう。
評者にはこの文脈におけるDこそが、「オープンダイアローグ(フィンランド発の対話実践)」であると考えている。対話実践は理論の成果というよりは、現場にいきなり「やってきた」。有効性の理由はよくわからないが、突然のように到来したのだ。対話実践は意図を持たず、計画も持たない。ただ対話することで「何か(治癒を含む)」が「向こうからやってくる」ための土壌を耕し続ける。原初において万人のコミュニケーション様式であった「対話」が、いまや精神医療の先端的試みとして「回帰」しつつあるということ。その意味でDの到来は、実は心理療法において起きつつあるのではないだろうか。牽強付会(けんきょうふかい)と言われようと、私にはこの着想が、Dの理論と対話実践の双方を豊かにする可能性をもはや疑わない。
ALL REVIEWSをフォローする