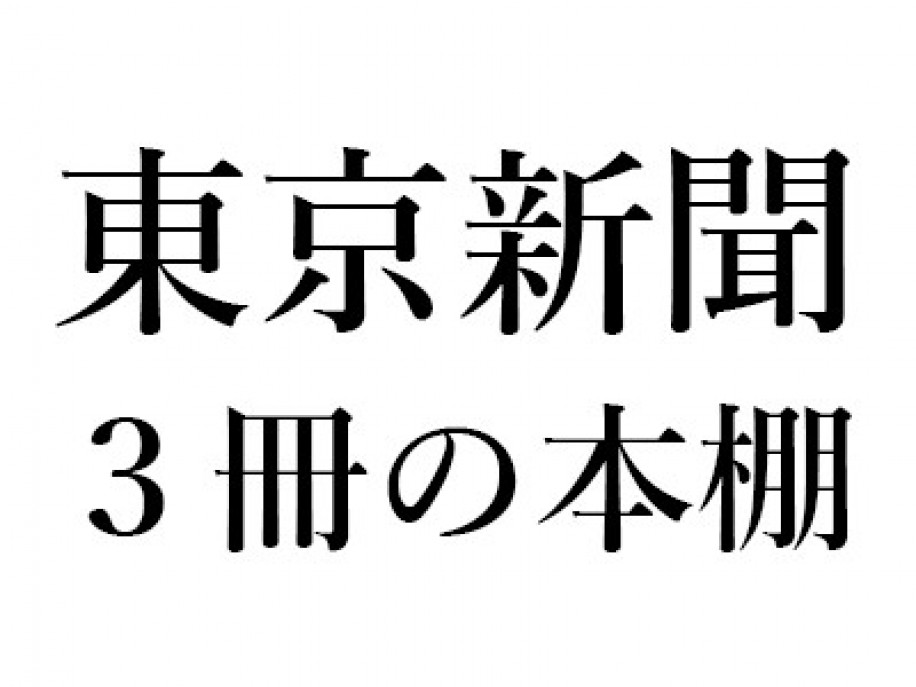書評
『一局の将棋一回の人生』(新潮社)
マジック・ミラーを通してみる棋界
羽生(はぶ)は初挑戦であっさり名人になる、と十年前にはっきり書いた人がいる。羽生善治(よしはる)が十四歳でプロ・デビューして間もないころだ。ひいきの放言ならともかく、名人十年周期説という歴史的事実を踏まえた根拠も示されている。十年に一度新名人が生まれ、名人を約束された新棋士も十年に一度しか現れない。加藤一二三、中原誠、谷川浩司とつづいて、だから次は羽生善治。
そう書かれているのを読んだのが三年前の平成六年。ちょうど羽生が初挑戦で米長(よねなが)を破って名人位についたころだ。河口俊彦の『一局の将棋 一回の人生』という文庫本だった。
当時は、将棋ファンでなくても七番勝負の帰趨にそれこそ浮き足だっていた。それを狙ってタイミングよく、平成二年刊行の予言の書が文庫化されたわけだ。将棋知らずの僕にとって、羽生はすごい、というより、河口ってひとはすごい、だった。
この本の中の、「新人類の鬼譜」にその予言は記されていて、もとは昭和六十三年から翌年にかけて「小説新潮」に連載された素人向けの啓蒙エッセーだ。いま、読み返してみると、かつて戦慄した予言や周期説はさほどことごとしいものではなく、肝心なことを託す前説としてあっさり触れているにすぎないと気づいたが。
現在大活躍中の羽生たち二十代棋士は、昭和末年当時、十代の新人として一流の棋士たちを相手にすごい勢いで勝ちまくっていた。そういう前例のない事態を、木村義雄、升田幸三、大山康晴以下の、戦後の大棋士たちの舌を巻くほどの駆け引きのうまさや勢力の消長、新人たちにとってはすでに旧人類に属する中原、谷川ら一流棋士たちの成熟ぶり、それぞれを縦軸・横軸にした座標のなかにどう位置づけたらいいか、にこの本は腐心している。
一流棋士たちの指した一手一手には、いろいろな表情がある。軽蔑や憐れみ、恐れとふるえ、笑っているときもあれば、しかめたり、泣いていることもある。……これに対して少年達の指し手は無表情で、感情がこもっていないように思える。テレビゲームをやっているようで、人間を相手にしている、の感じがない。
そのかぎりでは、新人類全盛のいまは、用済みになってしまった棋界展望といえなくもないが、棋界の事情や棋士の生態や将棋の秘奥という、門外漢にはうかがい知れない世界を、マジック・ミラーを通してみせてくれるのだから読み捨てはもったいない。別のひとが書けば別の世界が現出するとも思えない。この文章のほかには、あとは棋譜があるだけだろう。
ところが、タイトルに「鬼譜」とあっても棋譜はひとつも載っていない。それなのに将棋についてすべてわかった気になるし、へたな小説が及ばないほど面白いのだから、数式を使わずに数学の深遠を解説しきったようなものだ。そう、深遠だ。
そんな離れ技が可能だったのは、河口自身が現役の棋士だからだ。
棋士、棋士と僕は気やすく書いているが、プロの棋士には容易なことではなれない。「奨励会」という天才集団を抜けなくてはならないのだ。新人類棋士たちはそこを二、三年の最短期間で通過した。河口はなんと十七年かかった。ワースト記録だそうだ。十四歳で入会して卒業したのが年齢制限ぎりぎりの三十歳。こういうのを「年期の入った」という。苦労したんだ。面白くてためにならないわけがない。新人類棋士が、たとえ年を取ったところで逆立ちしても書けない本だ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする