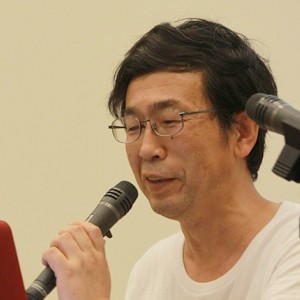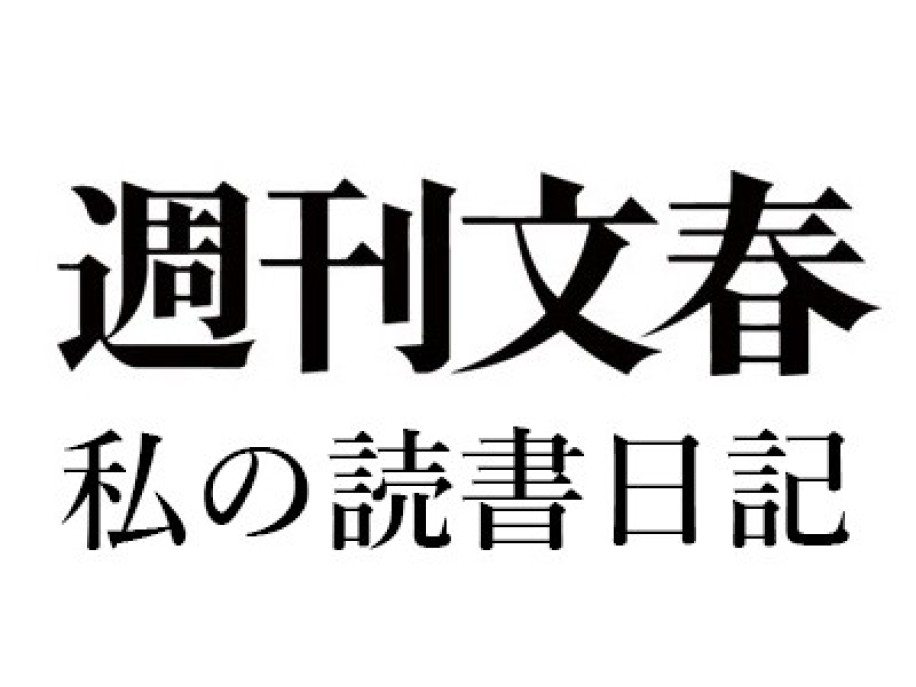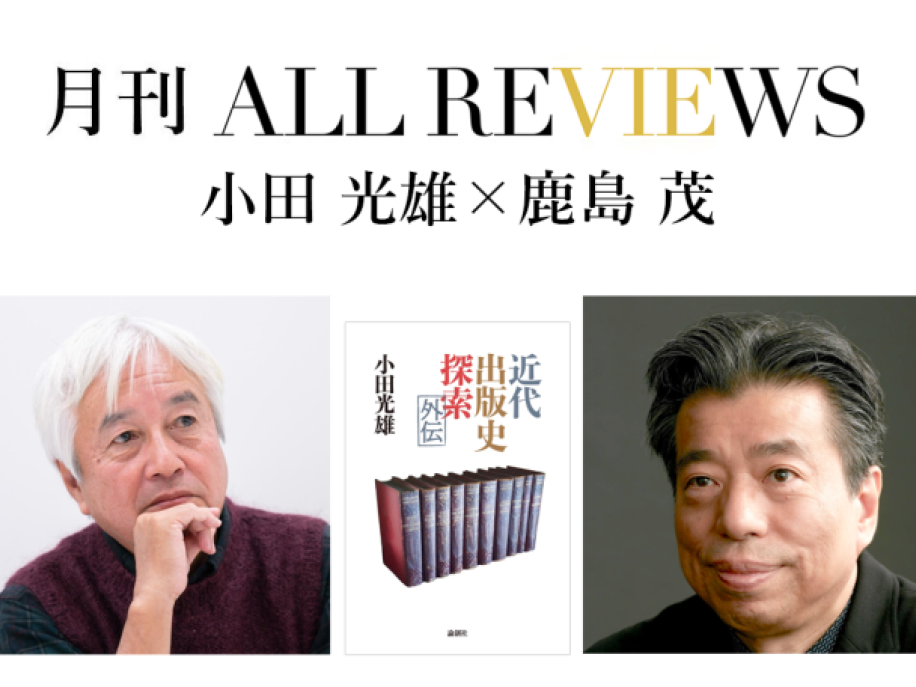書評
『不死鳥と鏡』(論創社)
凝りに凝った歴史ファンタジー
SF、ファンタジー、さらにミステリも書いたアメリカの大衆小説家アヴラム・デイヴィッドスンは、該博な知識をもとにした独特の奇想小説で知られている。それはややもすると衒学(げんがく)趣味と受け取られ、難解だと敬遠される可能性もなくはないが、代表的な長篇『不死鳥と鏡』ではそんな心配はまったく無用だ。舞台は古代ローマ。主人公の魔術師ヴァージルは、高貴な女性から、行方不明になった娘を探し出してほしいと依頼される。それには彼女の現在の居所を映し出す魔法の鏡が必要になるが、その「無垢なる鏡」を製造するためには「無垢なる鉱石」を入手しなければならない。このほとんど不可能にも思える企てを、ヴァージルは引き受けてしまうはめになる。
物語のプロットはこんなに単純な探索物で、いかにもよくありそうな歴史ファンタジーだと思えるかもしれないが、実はその作りが凝りに凝っている。まず、主人公のヴァージルとは、古代ローマの英雄叙事詩として有名な『アエネーイス』の作者ウェルギリウスその人。しかし、ここに登場するヴァージルは、史実のウェルギリウスではない。中世ヨーロッパでは、詩人としてのウェルギリウスの姿は忘れ去られ、黒魔術師だったという伝説が流布した。つまり、ここで描かれる魔術師ヴァージル、そして古代ローマは、中世の伝説という歪んだ鏡に映し出された虚像である。
そういうわけで、本書にはライオンの胴体と人間の顔を持つ人喰いマンティコアや、ゴシック建築の屋根によく見られる怪物ガーゴイルといった幻獣たちがぞろぞろ登場する。しかしその一方で、この空想世界が奇妙なことにリアルな手ざわりを持っていることもまたたしかだ。ナポリの街頭で猫の群れに餌をやっている、頭のおかしな老女は、いなくなった猫が海を渡ってエジプトに帰ってしまったんだと言う。それを聞いたヴァージルは、「どれが真実で、どれが妄想なのか」と考える。ここでは、歴史的事実と作者の想像との境界線は曖昧である。途方もないエピソードの数々には、アヴラム・デイヴィッドスンが愛情を込めて渉猟していた歴史のトリヴィアが、真実と伝説の区別なくちりばめられている。
放恣な夢想にすぎないように見える世界がなぜかリアルに思えるのは、そこで描かれた古代世界がある意味で真実を伝えているからではないのか。その時代では、世界はまだ知られていないことだらけだった。必然的に、人々は想像力でその世界を埋めざるをえなかった。『不死鳥と鏡』は、そうした世界を映し出す鏡になる。
この小説は、枠組みとしてはファンタジーであっても、そこにはミステリ的な謎解きの要素もあり、さらには独特な形でSFにもなっている。主人公のヴァージルは錬金術師でもあり、鉱石から魔法の鏡を製造する過程が詳細に語られる。この小説の中心にあるのは、錬金術という当時の「大いなる科学」、すなわちフィクションとしてのサイエンスなのだ。
そう考えると、作者アヴラム・デイヴィッドスンの姿が浮かび上がってくる。無用な知識にも思える歴史のトリヴィアから、『不死鳥と鏡』という彼にしか書けない小説を作り上げた、錬金術師あるいは魔術師としての姿が。
ALL REVIEWSをフォローする