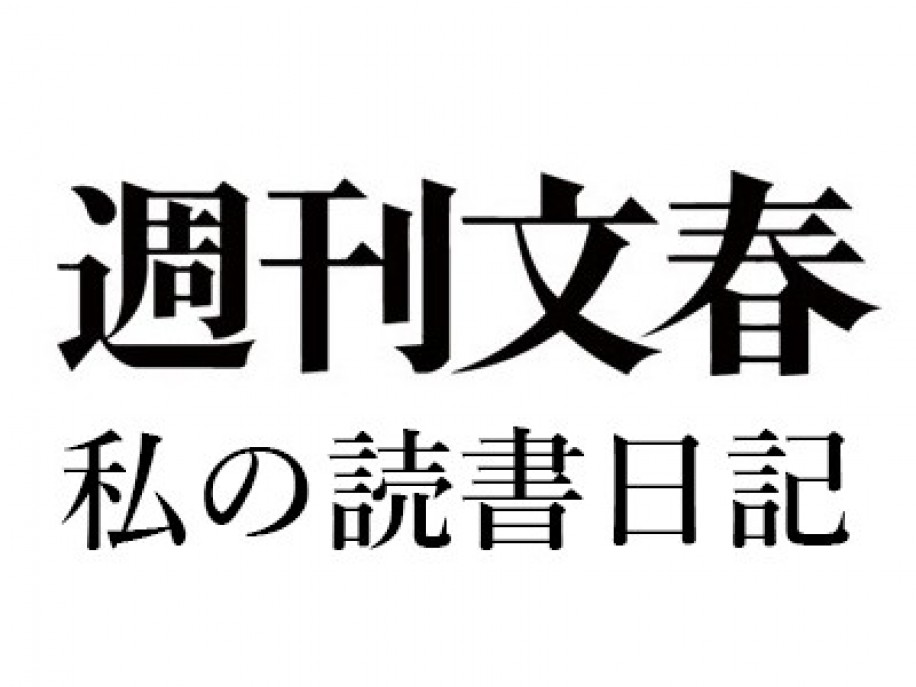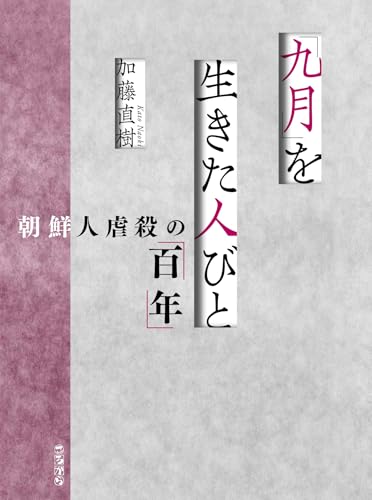書評
『入管問題とは何か――終わらない〈密室の人権侵害〉』(明石書店)
差別、暴力…人権を知らない日本人
名古屋入管で収容中に亡くなったスリランカ人女性、ウィシュマ・サンダマリさんの事件以後、「入管問題」は、ようやく、ある程度、認知されるようになった。でもいったい「入管問題」の本質はなんなのか。
編者の一人の鈴木江理子は、「暴力性」と書く。「収容の可否判断に司法は関与せず、入管職員の裁量によって、無期限の収容が可能である」施設。その対象になるのが「外国人」で「日本にいるべきではない不法な人間」とされるために、「関係者や監督者の責任が追及されることなく、やり過ごされて」きた。
本書は六章にわかれ、六人の執筆者がいて、それ以外にもコラムの形で当事者や支援者、弁護士などの言葉が差しはさまれる。
一章では鈴木が、入管収容施設は「送還という目的を達成するための追放装置としての機能を担っている」こと、そしてその背景に、日本の移民政策、難民政策の失敗があることを指摘する。
二章で、朴沙羅によってあきらかにされるのは、朝鮮半島や台湾などかつて日本の植民地だった地域の人々、とうぜん「日本国籍」を持っていた人々が「戦後」になって国籍をはく奪され「外国人」という新設されたカテゴリーに当てはめられて排除、管理されていった歴史である。
三章の高橋徹による「入管で何が起きてきたのか」の記述は、読む者の胸を抉(えぐ)る。たった二十年ほど前の入管の人権侵害ぶりは凄まじい。文字通り、殴る蹴るの暴力が日常化し、職員による被収容者のレイプまで行われていた。
四章ではクルド難民の支援に携わる周香織が、自らの活動を振り返る。国連難民高等弁務官事務所が正式に認めた「マンデート難民」であるにもかかわらず、日本の入管がクルド人親子を強制収容し、支援者や弁護士らが抗議の記者会見を開いている只中(ただなか)に、チャーター機でトルコに強制送還した、日本の入管史上特筆ものの、人権侵害事件が詳述される。
五章は小説家の木村友祐が、現在進行形の仮放免者や難民申請者の苦悩を取材する。木村は、マジョリティ側の人間はしばしば無意識のうちに、マイノリティである当事者たちに「かわいそうな人たち」であることを要求していないかと、問いかけている。
六章は共編者の弁護士、児玉晃一が、現行の収容制度の問題点と改善のためのアプローチを提言する。あまりに入管の裁量に頼った現制度による収容が、戦前の悪名高き治安維持法の予防拘禁よりも残酷な状況を作っていることも指摘されている。
二章で朴沙羅が書く、こんな言葉を嚙みしめている。「外国人という、基本的人権の及ばないような存在であるかのように思える人々を」「つねにつくりだすことは、日本人の権利に関する認識を狂わせている。もし日本人がこれまで、戦後どころか歴史の中でただの一度も、特権でないものとしての人権がどんなものかを知らないのだとしたら、その原因の一端は出入国管理制度にある」
差別を、「暴力性」を、制度の中に持っている以上、日本人はほんとうの意味では「人権」を知らない。「入管問題」とは、この事実と向き合うことだ。わたしたちは、まず、この認識から出発すべきではないかと感じた。
ALL REVIEWSをフォローする