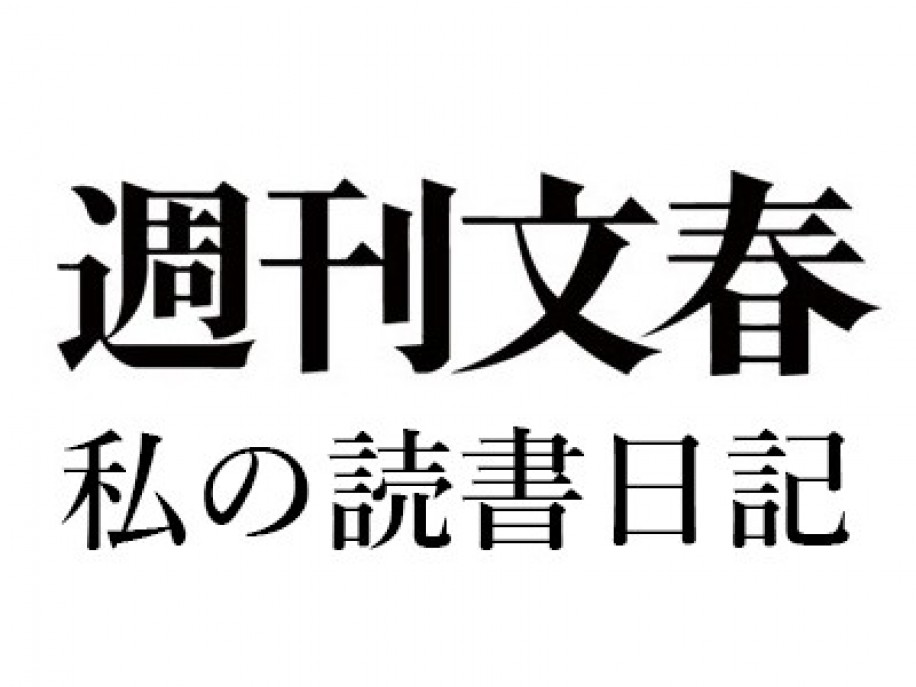書評
『「発達障害」とされる外国人の子どもたち』(明石書店)
善意が差別につながる実態が放置されている
日本の学校に通っている、日本語がよくわからない外国人の子どもたちが「発達障害」と診断され、特別支援学校に編入するケースがあると知って驚く。発達障害者支援法において、自閉症・アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害・学習障害・注意欠陥多動性障害などと定義されている「発達障害」。その定義を正確に把握できている人は教育現場にも少ない。
サブタイトルに「フィリピンから来日したきょうだいをめぐる、10人の大人たちの語り」とある。10年ほどフィリピンで暮らしたきょうだいが、日本での仕事を見つけた母親とともに来日した。教員をはじめとしたたくさんの人たちに助けられながら暮らしていたが、その教員たちが、あるときから2人を「発達障害だ」と言うようになった。そうすれば、特別支援学校に行き、職業訓練を受けることができる。そうしたほうがいい、という善意が「発達障害」という診断を生んだのだ。
外国人の子どもが何をもって「発達障害」とされてきたのか。先行研究の事例では、年明けの書き初めの時間に、墨の汚れの落とし方がわからず手を洗い続けた行為が、個人の特徴として「『発達障害』に回収されていくことにつながっ」たという。どうやったら墨が落ちるのか、誰が教えてくれるというのだろう。
本書の主人公であるきょうだいの場合も、日本語が自由ではないという問題にとどまらず、そのうちに「それ(言葉の発達の問題)だけじゃないよね」という判断につながっていく。
「大人たちの奮闘や配慮」を知りつつも、「正当化できることばかりではない」と著者。韓国人として、そして母子家庭で育った著者が実感を交えながら記す一冊を通じ、放置されたままになっている問題を知った。
ALL REVIEWSをフォローする