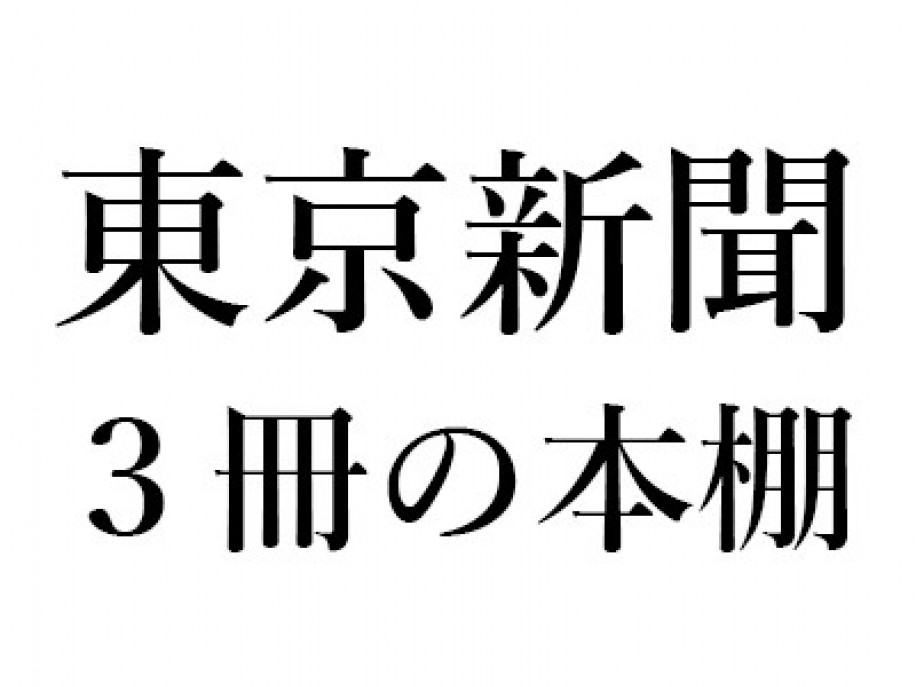書評
『深沢七郎集〈第2巻〉』(筑摩書房)
しようがねえよ、その通りなんだから
ひさしぶりに深沢七郎を読む。長篇小説『千秋楽』。妙に感心した記憶が残っているだけで、筋も何も覚えていなかった作品だ。覚えていなくて当然かもしれない。母親を山に捨てたり、誰かの首が落ちたりという物騒な場面があるわけではなし、筋立てがきわだって面白いわけでもない。修業中の若い芸人が師匠の穴埋めに檜舞台を踏むことになってから、出演したショーが千秋楽になるまでの二ヵ月あまりの出来事を、何のケレンもなく綴るだけ。
ショーの題名は「三匹の牝馬」。バラエティー・ショーとでも言うのだろう。ストリップのあいだに歌や曲芸や寸劇がはさまる仕立てになっていて、主人公の富田長次郎ことドンチョーはその寸劇の数場面で、「パリのパン助の尻を追う男爵」だの「酒場の男B」だのというチョイ役を演じる。
と言っても舞台での奮闘ぶりにはほとんど触れずに筆はもっぱら、男性出演者八人が詰めこまれる楽屋でのせわしいやりとり、舞台へのあわただしい出入りといった些事に費やされる。
みんなそれぞれ芸達者らしいのだが、芸人らしい顔をことさら見せるわけではない。そこらへんにいる人がごちゃごちゃやっているのと変わらない。ドンチョーもひよっ子芸人というより初心(うぶ)な青年だ。
しかし、二ヵ月も劇場暮らしをしているうちに、何かが板についてくる。ストリップなんて芸じゃない、と最初はばかにしているのだが、ビーバーというストリッパーの肉体の美しさに圧倒されて目を開かされる。そのビーバーがセリに落ちて大怪我をし、ほどなく見舞いのお礼に男たちの楽屋を訪ねてくる。足が不自由になったのでもうステージには出られない。そうと知ったドンチョーは、縁のない他人に思えてぷいとそっぽを向く。
あるいは、ひと晩を一緒に過ごしたストリッパーの舞台姿を見て嫌悪を感じ、もう一緒には寝ないぞ、と決心して見向きもしなくなる。
そうしたエピソードを目して、ひよっ子のドンチョーが一丁前に芸人の薄情さを身につけていく様子がつかまえられている、と言いたいところだが、作者自身、特別に芸人らしさ云々を持ちだしてはいない。世間に出たばかりの青年にありふれた出来事というふうに書いている。
深沢七郎という人は、職業その他で人間を区分けしなかった。する必要がなかった。人間がひとしなみに見えていた。『楢山節考』や『風流夢譚』を書いたり、ラブミー農場を経営したりで、事を構えてばかりいる札つきに思われているが、ただの酔狂あつかいはもったいない。端倪(たんげい)すべからざるレアリストなのだから。
芸人たちのいじましい右往左往ぶりを読んでいるはずだったのに、いつの間にか自分の姿を見せられている気がしてくるから妙だ。なるほど僕たちは三人集まればこんなことを言ったりしたりしている、と納得する。あれこれと気をつかうくせに、ザッパクでインケンでスケベで。
そう納得することは砂を噛む思いに似ている。これでは身も蓋もないじゃないかと悲鳴を上げたくなる。「しようがねえよ、その通りなんだから」と深沢の声がきこえてくる。この声にはさからえない。深沢のすごさはそのあたりだ。
ところで、出前のラーメンを楽屋の連中が食べる場面で、「ラーメンをチュッとすった」という言い方が何度か出てくる。ラーメンをすする感じが出ていて、東海林さだおより東海林さだお的だ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする