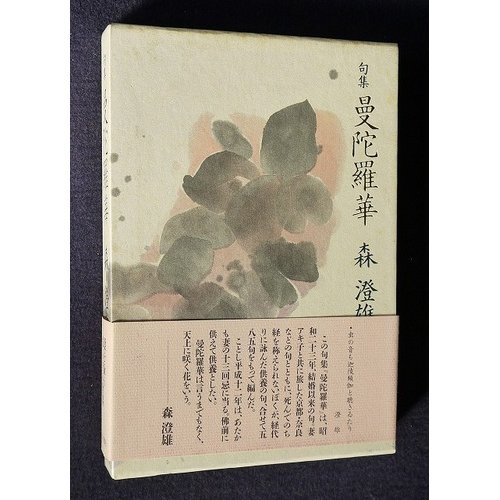書評
『限界分譲地 繰り返される野放図な商法と開発秘話』(朝日新聞出版)
タダでも安価過ぎて…「負動産」素顔
バブル崩壊の直撃を受けた不動産は、その後どうなるのだろう。土地や家屋は価格が下がり、やがて底値で売却される。もしくは人口減と相まって無人の荒野に戻る、というのが一般的な想定だろう。新幹線と関越道で交通至便の「湯沢」を名乗りながらも駅から20キロは山奥の苗場スキー場では、1990年代に数千万円で取引されたリゾートマンションがなんと10万円へ暴落している。供給過剰なうえに管理費や修繕積立金が重荷で、底値でも買い手が現れない。いわゆる「負動産」である。
一方、千葉県八街(やちまた)市周辺の場合、ローン返済の焦げ付きから2010年には競売物件数日本一となり3000万~4000万円したファミリーサイズの庭付き一戸建てが築30年で300万円に落ち込んだ。ところが近年では近隣からの住み替え需要が起き、高齢化が止まり新陳代謝し始めたという。都市機能は備わらないままだ。
吉川氏は前作『限界ニュータウン』(太郎次郎社エディタス)で成田空港周辺や総武本線、外房線といった八街を含む千葉県北東部の小規模ニュータウンを素材に、投機が不動産市場を歪める様を鮮烈に描いた。過半が都市在住の不在地主の所有である農村部の住宅分譲地では家屋もまばらで、分譲時点では全戸への供給を前提していた水道設備は半分の住民が維持している。私道や街灯、公園は自力管理が必要で、公共交通の撤退や教育施設の統廃合もあり生活の利便性が喪われている。社会インフラが欠如しているのだ。
今作ではそうした「限界分譲地」にまつわるリスクやトラブルに踏み込んでいる。空き地の所有者は大半が固定資産税や管理費、草刈り費用を払い続ける不在地主で、タダでも譲りたいが安価過ぎて不動産屋は仲介したがらない。物件を手放すには一定の不動産取引の知識が必須だ。
興味深いのは、こうした宅地が開発分譲されたのは80年代に限らない点だ。山林のまま区画整理らしきものはあっても造成がなされておらず、位置や交通情報もデタラメな「原野商法」が72年頃に現れた。分譲したのはすべて都内の会社で、完売したら会社を畳みクレームを遮断、を繰り返していた。特徴は利用法を名目ほども付けないことで、「素地のままお分けする投資向物件です」とあからさまだ。
探求はここでは終わらない。吉川氏は70年代の新聞広告を精査、詐欺と報じられた原野商法と限界分譲地の違いが曖昧だと指摘している。名目は居住用でも資産性が強調される投機的な宅地は、60年代から新聞に広告が掲載されている。70年代からは地価が安く都市計画法の規制が緩い「都市計画区域外」で開発許可が不要な小規模開発が始まり、現在の限界分譲地となった。広告主は新聞会社にとってスポンサーであり、新聞は片棒を担いだのに一部の分譲会社だけを「原野商法」と呼び断罪したのだ。
戦後に日本人が奉った地価が下がらないという「土地神話」は、土地バブルであった。「負動産」の解消により、実需を欠いたハリボテの戦後は終わる。
吉川氏は、痛快なウェブ動画配信「限界ニュータウン探訪記」も運営している。巧みな文体で批判精神も逞しい、新たな不動産ジャーナリズムの誕生だ。
ALL REVIEWSをフォローする