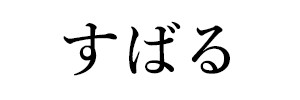書評
『永遠と横道世之介 上』(毎日新聞出版)
懐かしさと憧れが詰まった「一瞬」と「永遠」
あの夏の数かぎりなきそしてまたたつた一つの表情をせよ(小野茂樹)
夏の午後はタイムマシンだ。ふとした時に、子供時代の夏休みのある瞬間といった断片的な記憶が去来してくることがある。かと思えば、親くらいの年齢になったら何をしているのかなど、未来に向けた感情が湧き起こることもあった。そんな時間の行き来がもたらす寂しさと憧れが詰まっているのが『横道世之介』シリーズだ。読んでいると、あの頃は幸せだったなあと静かに懐かしくなったり、歳をとるってのも悪くないんだろうなあと無性にワクワクしたりと、読む人の年齢や境遇によって、今ではないいつかに気持ちが連れ去られる。
『永遠と横道世之介』はシリーズの第三作で、シリーズ完結と銘打たれている。第一作『横道世之介』(毎日新聞社、2009年)は、長崎から上京してきた大学一年生の横道世之介という青年の一年間と、彼を取り巻く人々の生活やその後の人生を描く。世之介はどこか抜けていて頼りないものの、純朴でお人好し。大きな事を成し遂げるような大人物ではないが、友人たちは彼に出会えて良かったと言って憚らない。続く第二作『続 横道世之介』(中央公論新社、2019年 ※文庫では『おかえり横道世之介』と改題)では、24歳になった世之介が、冴えないフリーターとしてぼんやりと生きながら、シングルマザーの桜子とその息子の亮太との交流や、偶然の出会いからカメラマンとなるまでを描く。
そして、本作『永遠と横道世之介』。舞台は2007年9月からの一年間。37歳の世之介はフリーのカメラマンとして活動している。住んでいるのは「ドーミー吉祥寺の南」という下宿で、管理人のあけみとは恋人同士。ドーミーに暮らすのは、元芸人で現在は会社員の礼二、書店員の大福、軟派な大学生の谷尻、そして高校を中退して引きこもりになるもひょんな縁からドーミーで暮らすことになった一歩。更には、世之介の後輩カメラマンの江原、横暴で不器用な先輩カメラマンの南郷、ブータンからの下宿人タシなど、ちょっぴり個性的な人々の何気ない日常や、ありふれているのに心に残る会話などがゆったりと描かれる。
あらすじは以上の通りで決して複雑ではない。だが、シリーズ三作目から読んでいいものかと逡巡する方がいるかもしれない。結論から言えば、この作品から読んでも全く問題はない。その証拠に、作中で語り手が「シリーズを通して、ほとんどストーリーらしきストーリーがなく、もっと言えば、起承転結はもちろん、伏線があって最後に回収などという手の込んだ仕掛けもない」から、未読でも安心してほしいと述べているほど。
それどころか、本シリーズはシリーズ物なのにも関わらず、過去作との繋がりを意図的に断ち切っている。実は、主人公の世之介を除くと、同じ人物がシリーズを跨いで登場することはほとんどない(稀にそうした例があると、必ず丁寧な補足説明が入る。)。そのことについて、作者の吉田は、ある程度の歳月が経つと付き合っている人間はガラリと変わるから、登場人物を敢えて重複しないようにしたと述べており、時間を跨ぐシリーズ物ならではの演出が意図されていることが窺える。
しかしこの点については、世之介という人間がよく表れている点も見逃せないだろう。第一、二作に顕著だが、物語を構成するのは、主人公の世之介についての描写よりも、彼を取り巻く人々の描写の方が中心となっている。つまり、彼の友人たちや恋人の家庭環境やその後の人生などは深く描かれるのに、世之介自身については彼らほど深掘りされず、彼のその後についても伝聞や断片でしか語られない。というのも物語は、世之介の活躍よりも、彼を通して描かれる人々の素顔や人間性に重きを置いている。言うなれば、世之介というフィルターで写したアルバムのようなものなのである。それは、世之介という人物が「一緒にいると何も考えずに済む」と人々から評されたり、その屈託のなさによって人々がリラックスし、友人や仕事仲間、パートナーとしても、そして職業カメラマンとしても、かけがえのない存在になっていたりすることと通じている。つまり、世之介という人間は二つの意味でカメラマンとして最適の人物なのである。となれば当然、写る(描かれる)のは被写体たちで、世之介が写る機会は少ない。裏を返せば、物語は世之介を通した世界を描く。したがって、シリーズ(世之介の立場が変わる)ごとに、被写体たる登場人物は入れ替わり、そしてフィルターの世之介の変化に応じて、人々の見せる顔も変化するのである。
人々の見せる顔という点では、本作が最もバラエティ豊かだ。というのも、シリーズ第一作ではまだ18歳だった世之介も、本作では38歳。さすがに様々な苦労を経てきたし、年少者の未熟さも分かれば、年長者の孤独にも寄り添えるようになっている。そのため世之介は、若い下宿人たちに年長者らしい絡み方をしたり、後輩のカメラマンにアドバイスめいたことを言ったり、その一方で人望と仕事を失った先輩カメラマンを慰めたり、娘を亡くした夫婦の傍に寄り添ってやったりと、色々な人々と時間を共にし、色々な顔を見守るのだ。そこで興味深いのは、彼らが過ごしているのは同じ時間なのにもかかわらず、人物の年齢によって感じている時の流れが異なること。88歳の和尚が「四年なんて私の年になったら三日前くらい」と述べているのは極端な例だが、高校生や大学生の若者は数日単位で何かに挑み、中年の世之介は少し進んでは過去に揺り戻されながら徐々に前へと進む。それぞれの時間は全く異なるが、それでもその中には「永遠」に思える一瞬が存在する。本作ではそんな永遠を鮮やかに描き、それを求め続けた世之介という男が永遠となるまでの物語である。世之介という人物を通して描かれる様々な一瞬を通して、永遠だと感じられる濃密な時間に出会ってほしい。
【下巻】
ALL REVIEWSをフォローする