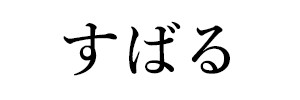書評
『荒地の家族』(新潮社)
寄せ続ける記憶の波に抗して
「すっきり晴れた感じではない。引き続き、書いていくべきだと思いました。いつか、震災から解き放たれた自由な小説もどんどん生まれてきたらいいと思います。」第一六八回芥川賞を受賞した作家の佐藤厚志は、記者の「(震災を書くことについての)悩みが晴れたという気持ち?」という問いに対して、静かに答えた。[1]佐藤は宮城県に生まれ、現在は仙台の書店に勤務をしている。デビュー作「蛇沼」、その後に続く「境界の円居」、『象の皮膚』など、作品の多くも宮城県や福島県が舞台になっており、特に『象の皮膚』では、東日本大震災当日やその後の混乱までを正面から描いた。もちろん、『荒地の家族』でも震災は重要なテーマになっている。だが丁寧に読むと、震災を正面から描いておらず、それが却って震災の生々しさを伝えていることがよく分かる。(これは『蛇沼』も同様である。)
『荒地の家族』の主人公は、坂井祐治という四十歳の植木職人だ。震災から二年後に、一人目の妻である晴海を病で亡くし、その後に再婚した知加子とは流産や不和が原因で別居。現在は、晴海との間に生まれた小学六年生の息子の啓太と、自身の母親である和子とともに三人で、宮城県の亘理町に暮らしている。祐治の職人としての実直な仕事ぶり、苦労しながらも地域の人々と助け合い暮らしていること、離婚係争中の知加子の職場にまで押し掛ける様子、年頃の息子との距離感を掴みかねていることなど、四十歳の男性の日常が淡々と紡がれていく。離婚協議はともかく、決して特殊なことはない、ありふれた日々だ。
そんな日常の隙間から、突然かつ乱暴に襲来するのが記憶である。アラブ文学者の岡真理は「人がなにごとかを「思い出す」と言うとき,「人が」思い出すのではない,記憶の方が人に到来するのだ」[2]と述べているが、人はトリガーを引かれれば、思い出すことを防げない。とりわけ、幼い頃から住んでいる土地ならば、記憶が蘇るのは日常茶飯事となる。本作では、旧友との再会を契機に、幼い頃に大きな事故の「脳内に焼きついた場面がよみがえる」こともあれば、「周りの風景を見ると、その時の生活が鮮明に思い出され」たり、祐治の昔の記憶が挿入されることが多い。しかもその多くがごく自然で、わざわざ過去の話と断らずに、現在と過去の描写が連続して描かれたり、いきなり過去に転換したりするのは、そうした突発性に由来するのだろう。
その記憶の中でも生々しいのは、やはり震災だ。亘理町は沿岸部に位置しており、大きな被害に見舞われた。復興が進んだとはいえ、津波によって荒らされた大地や、震災後に建造された巨大な防潮堤など、震災の記憶を呼び覚ますものは多い。祐治が、防潮堤を目にして「ついこの間経験したばかりの恐怖の具現そのもの」と捉える様子からは、被災地に住み続けることの苦しみが痛いほどに伝わってくる。佐藤がインタビューの中で、仙台や宮城県で生活していれば、風景の中に震災の痕跡は目に入るのだから、触れざるを得ない、と述べている通りだ。[3]
だが、確かに震災の記憶は強く残っているが、同時にそれ以外にも苦しい記憶は増え続けていることにも注目したい。十年以上も経てば、人は普通に生活を送り、その中では笑ったり、悲しんだりするような出来事もたくさん経験する。祐治の場合は震災で直接家族を失わなかったこともあって、前妻の死や妻の流産、仕事の失敗など、震災以外の苦しい記憶も実に鮮やかだ。
では、祐治はそのような苦しみに対して、どのように向き合っているのだろうか。それは、震災や家族の死を、正面から直視しないように努めることだ。そのために、彼は直接的な言葉を使用しない。例えば、「地震」や「津波」といった言葉を避け、「あの時、底が抜けたように大地が上下左右に轟音を立てて動き、海が膨張して景色が一変した」と言い、妻の流産を「腹に宿った子は成長をとめ」たと表現する。
そして、言葉への忌避感は、言葉や意識の対極にある肉体への集中に繋がっていく。彼は植木職人としての仕事に異常なまでの集中力で臨むのだ。「酷使して麻痺しかけている両腕と刈込鋏が一体となって動」くほどに打ち込み、「焼けつくような暑さの中で鋏を振るいたかった。(中略)肉体に負荷をかけたかった。(中略)死ぬほど暑くなればいい」という狂気にすら至る。だが、意識を肉体に集中したり、自らを酷使したりすることで、その間は苦しみから逃れられる上、生き残った自分への罰にもなる。なぜ生き残ったのは自分なのか、なぜ死んだ人間たちを守れなかったのか、故郷のために何かできないのか。そうした「負い目」に正面から孤独にぶつかってしまい、呵責に耐えかねて自死を選んだのが旧友の明夫だ。
しかし、祐治は人々と支え合い、無心に仕事に打ち込むことができた。それが徐々に復興へと繋がり、やがては自らの救済になる。植木職人として大地をケアする彼の働きは、東北の復興そのもののようだ。頭の中では、先々の植林を思い描き、そしてそれを地道にこなしていく。最後には、彼の仕事と東北の自然とがまるで一体になったように、歳月の歩みが描かれるのだ。春になり、「堀に沿って立つ桜が封印を解かれたように一斉に花を咲かせた」様子は、彼自身の心も解放されたようにも読める。彼は時の経過すら忘れ、無心に東北を復興させていた。そして、ようやく彼は心の平穏を取り戻す。そんな祐治を待っているのは食事だ。それまで「ラーメンの味が」せず、余計なことを考えないために「いつも弁当を詰め込むように食っ」ていた彼に、家族が食事を用意して待っていてくれる。祐治の、東北の復興はまだまだこれからだが、まずは自らのためにゆっくり食事ができるようになることを祈るばかりだ。その先に震災から解き放たれるときがある。
[1]芥川賞の佐藤厚志さん「震災どう描けるか考えてきた」 会見詳報(朝日新聞デジタル)
https://digital.asahi.com/articles/ASR1M7H4YR1MPLZU002.html?pn=6&unlock=1#continuehere
[2]岡真理『記憶/物語』岩波書店、2000年
[3]【緊急】丸善仙台アエル店 佐藤厚志さん 芥川賞ノミネートインタビュー(YouTubeチャンネル:丸善ジュンク堂オンラインコンテンツ)
https://www.youtube.com/watch?v=WkqZ-mu_W8g
ALL REVIEWSをフォローする