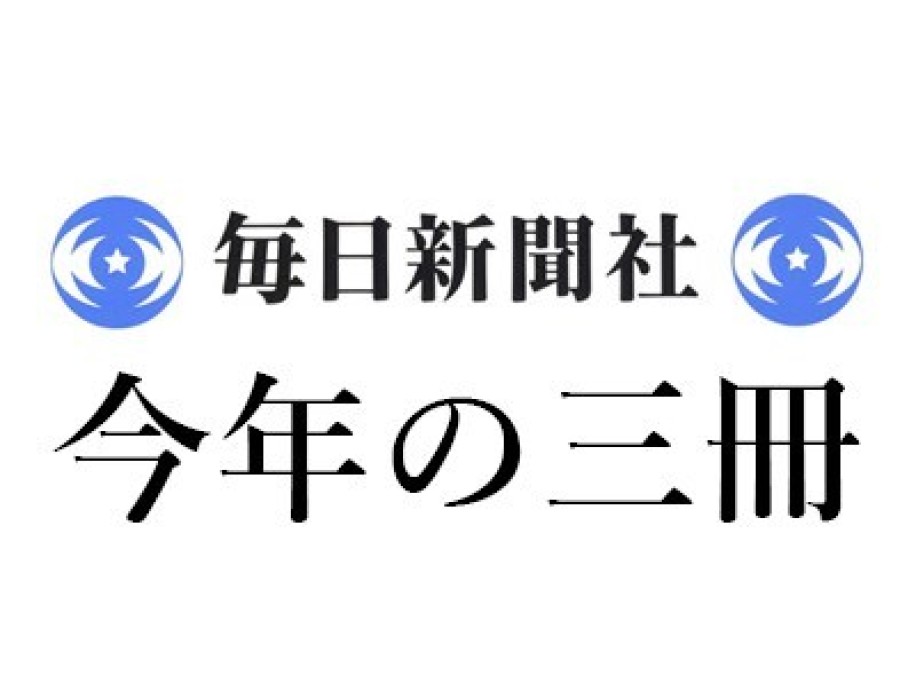書評
『橋を渡る』(文藝春秋)
今はよりよき未来なのか
東京都議会で発言していた女性議員に向けて、セクハラと見なされる野次を飛ばした議員がいる。最初の野次の発言者は特定されたが、その次の発言者はだれだかわからない。近くで聞いた人も、発言した本人も、名乗り出ない。二番目の野次は、もみ消され、結果的になかったことになる。二〇一四年に実際に起きたことが、この小説で幾度か語られる。四章から成る小説の舞台も語り手も章ごとに異なる。三章までは、どこにでもいる夫婦であり家族でありカップルが描かれる。セクハラ野次をはじめとして、登場人物たちの周囲をさまざまなニュースが流れていく。バンコクで代理出産されたとおぼしき九人の赤ん坊が保護される。女性参院議員が若いスポーツ選手にキスを強要。香港での学生たちによる抗議デモ。どのニュースも見聞きした覚えが私にもあり、自分も「どこにでもいる」ひとりとして小説内に入りこんだ錯覚を抱く。登場人物たちと同じように私もそこで、ニュースについて興味を持ったり話題にしたり、忘れたりしていく。
同時に何かよからぬことが起きつつある不穏な予感が冒頭からかすかにあり、それが知らぬまにふくれあがっていく。そして三章、これまでのニュースのようにある研究について明らかになる。ひとりの科学者がiPS細胞から精子と卵子を作る研究を進めている。それが成功すれば、ひとりの人間の細胞から子どもを作ることが可能になる。小説のなかにすっかり入りこんでいる私は、これもまた雨傘革命やマララさんのノーベル賞受賞と同じく、現実に起きていることだとつい思いこんでしまう。そうしてそのまま、四章へ放り出される。
二〇八五年の東京であり日本。そこではどうやら、人間とロボットと、それ以外の存在がいる。その存在こそ、ひとりの人間の細胞から作られた「サイン」と呼ばれる者たちである。彼らは細胞を提供した「親」とは異なる人格を持ち、ごくふつうに感情も持っているが、生殖能力を持たず、寿命が人間よりかなり短い。
描き出される七十年後は、ひどく乾いた印象の世界である。ただしく秩序立っているが、差別もその秩序に則って正しく行われている。その世界に放りこまれた私はただ茫然とするしかない。その秩序のありように、その殺伐に。そしてそこで、生を営む人たちが、案外たのしそうで、でも不幸でも幸福でもなさそうなことに、戸惑うしかない。
今まで接点がないと思っていた三章までの人たち、どこにでもいる彼らが、徐々につながっていく。あのときの、ちょっとしたできごとが彼らを複雑に結びつけ、未来を決定づけていく。
この未来、が、私の生きている今と地続きでつながっていることを身をもって実感する。今日私が見てしまったこと、してしまったこと、話したこと、そればかりか、見なかったふりをしたこと、しようとしてしなかったこと、話そうとしてのみこんだこと、そんなちいさなひとつずつが、積み重なって未来を作っていく。その結果がこの世界かとまたしても放心したように思う。
作者は、まんまと小説のなかに入りこんだ読者を七十年後の世界に置いてきぼりにはしない。ようやく小説世界から抜けだして現実に戻ってきたことに安堵しながら、今まで持っていなかった奇妙な感情が自身の内に在ることに気づく。七十年後の未来に、私はすでにかかわっている、という焦りにも似た希望だ。そして、私が今いるのは、七十年前、戦争で多くを失った人たちの願った、よりよき未来に違いないと思う。
ALL REVIEWSをフォローする