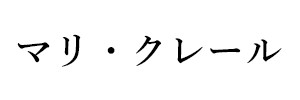書評
『モードの迷宮』(中央公論社)
『マリ・クレール』に連載中から、この未知の著作家のファッション論は、感心しながら読んでいた。どこに感心したかといえば、まず姿勢だ。ファッションについてまともに、本格的にぶつかっていることだ。つまり本邦ではじめてまともに本格的に腰をいれてファッションについてかんがえ、論じた文章があらわれたといっていい。いままでも現場ファッション・デザイナーの鋭いメモや感想のたぐいはあった。またいわゆるファッション評論家が年度ごとのファッション・コレクションの動向を紹介し、解説した文章のたぐいはあった。でもそれらはわたしたちがイメージするファッション論とはちがうものだ。わたしたちがイメージする本格的なファッション論はどんなものか易しく言ってみれば、例えばここにモデルが着込んだ一枚のファッション写真がある。それがファッション・ショーの場面のなかの、ひとりのモデルが着込んだ生身の姿態であってもいい。言葉がそのファッションに限りなく肉迫し、その実態をつかみだしながら、しかもそれと拮抗し、緊張関係を保っているようなファッション論が、まず最初に、そして最後に欲しいものだということになる。ファッションは言葉だ、あるいは広義の言葉としての記号だという認識にたっしたファッション論を、日本語で読もうとすると、ロラン・バルトとボードリヤールの訳書しかない。しかもこれらの哲学者たちの論考は、とうていファッション・ショーの現場やファッション・デザインの現場までおりてゆく気はないところで書かれている。それくらいファッションの世界では、「本格的」ということと実態に肉迫するファッション論の距離は距たっている。そしてこの距たりのすべてにわたらなければ、わたしたちのイメージは充たされることはない。もちろんさしあたって「本格的」を志向するだけであっても、一枚のファッション写真や、ファッション・ショーの一場面のモデルに肉迫するだけの言葉であってもいいのだ。
この本の著者がやっているのは、はじめての「本格的」なファッション論だという意味で、とても高く評価さるべきだとおもえる。著者のファッションにたいする基本的なコンセプションは、ファッションとしてみられた衣裳の構造が、裸の魅力を隠すようにしながら、じつはそれを強調する、また肉体の魅力で誘惑しながら、きわどいところで拒絶する、肉体を保護しながら同時に損傷させる、といったような二律背反の作用だという点にある。そしてこの背反する運動がやっと均衡しているところで、ファッションのスタイルが決定されているが、やがて身体がもつ根源的な不均衡のなかに入りこみ、その不均衡に動かされて反復移動してゆく。この基本的なコンセプションは、著者によってさまざまな形で強調されて、この本の背骨になっている。男性のカラー、ネクタイ、ベルトは首や胴を締めあげ、拘束するものだ。だがそれは同時に気品とか儀礼とかに叶うものとされる。女性のタイト・スカート、コルセットなどは腰を締めつけて内臓障害をもたらすほどだし、タイト・スカートは歩くこと、活動することを極端に不自由にする。だがそれは身体の美しさ、人格の貞淑さ、慎み深さを表現するものとされて、十九世紀ファッション史を飾った。こういったファッションのもつ二律背反の構造をつきつめてゆけば、ファッションの原則が、モデルを身体に合わせるのではなく、身体をモデルに合おせるのだということがわかると、この本の著者は強調する。シンデレラ物語は、のこされた靴にあうような足の持主を探し出そうとする王子の願望が発端になるのだし、中国の封建時代の纏足の風習は、幼児のときから足を畸形にまるめて細く小さな靴に合わせようとする飽くなき欲求に発したものだし、日本の吉原花街の太夫おいらんは高く重い木履をはいて、重力の拘束に身をゆだねることが、美と忍従と華やかさの象徴であった。この非合理、拘束と解放の二律背反と共存、禁忌と煽動の背中あわせ、そのあげくに身体を損傷し、内臓が病におかされるまで締めつけて、そのときそれが美であると信じられた。そんな何の客観性もない拘束に身をゆだねる不可能な変形、逸脱、畸形。そうとしかいいようのない美意識に従属してゆく逆説的な本質がファッションだと著者はいう。
もう一度だけ、合計三度この著者はファッションの二律背反と、不釣合、不均衡の根源的な欲求とが皮膚や衣裳の表面で演ずる逆説的なドラマについて伝えている。それは隠しながら見せるということについてだ。胸もとのボタンを外したシャツ、シースルーのブラウス、乳首が浮きでる薄手のセーター、深いスリットの入ったスカート、すれすれのミニスカート、身体の線がくっきりと出るニットのワンピース等々。著者は秘匿さるべきものへの関心を掻きたて、貞淑の焦点を逆に想像させる挑発になっているファッションの原則の例としてあげながら、しだいにファッションの本質を性的な欲望論に結びつける西欧的な衣裳論の系譜に近接してゆく。眼線から眼ざしによる皮膚や衣裳の表面への接触感をふくめて、あらためてこの本の著者のファッション論、禁止と挑発の二律背反を原則とするファッションの変遷と反復の論議をふりかえってみると、それが性的な欲望の禁忌と解放の原則にゆきつくことがわかる。人間はなぜ衣裳をまとい、しかもつぎつぎと衣裳の歴史をファッションとして循環させ反復してゆくのか。それは性的な欲望を挑発し、挑発しながら禁止するという二律背反の作用を実現するためだ。なぜ人間はそんな手のこんだことをするのか。人間の存在の根拠にはたがいに相反するようなふたつの原動機があって、このふたつの根源的な不釣合によって移動し、釣合に達し、またそこから不釣合の方へまた駆りたてられてゆく本質があるからだ。もしこの不釣合と釣合との存在論的な運動を、視線の表面性や性的な欲動の皮膜での眼ざしの接触というところからみていけば、ファッションの本質ともいうべきものに到達する。これがこの本の著者のファッション論の核になっている考え方であることがわかる。この考えはひとつの岐路に立つことになる。ファッションの表現論の方へ下りてゆくか、身体論の一般の方へ上昇してゆくか。そして著者は身体論の方へ上昇してゆくようにみえる。
まず仮面ということ。顔にマスクをつけることは衣裳の類型化を極限におしすすめることと同義だから〈私〉や〈私〉の表情がかくされ匿名化するために「顔さえ隠せば何でもできる」という欲動の解放とおなじことになっている。たとえば秘密の性的パーティでは仮面さえつけていれば、それ以外の衣裳はみんな脱ぎすてることもできるし、またドアのかわりに仮面を備えつけたトイレもあった。これはおしすすめてゆけばエロティシズムの問題に帰着する。秘部=性器自体はエロティシズムを喚起しないし、顔の写っていないヌード写真はべつにエロティックではない。このばあい背反しあう一方のヴェクトルである〈私の〉という禁忌を表象するものが欠けているからだと著者はのべている。そしてもうこのあたりから欲動の表面性と皮膜性から視られた身体論の方へはいってゆく。人間の身体のなかでそこに眼ざしを集中していると妙な気分で、視ている眼ざしの根拠から浮きあがって客体的になってしまう個所があると著者はいう。たとえば脚や髪や生殖器など。著者によればこういう部位は、仮面やマスクとおなじように〈私〉が少ない部分だからだ。髪とか生殖器とかは〈私〉の意志をはみだし、ざんばらになったりぶらぶらしてしまうし、脚は〈私〉の意志とかかわりなくある姿勢で歩きだしたり、とまったりしているようにみえる。そしてひとはなぜコスメティックに髪をセットしたり、マニキュアを塗ったり、ストッキングをつけハイヒールをはいたりしてじぶんの身体を拘束するかといえば、〈私〉の薄くなった身体の尖端の部分を、ことさら際立たせて〈私〉性を回復し、身体の輪郭をはっきりさせようと志向するからだ。このコスメティックな行為が極端になり、病的な領域に入りこんでゆけば、〈私〉の身体から〈私〉を鮮明に確かめようとして、局部を鏡に映してみたり、肛門に物体を突っ込んだり、路上で女性にペニスを見せびらかしたりする行為になってあらわれる。これは眼ざしを行使する方の側からもいえることだ。
いわゆるフェティシズムが脚をつつむストッキング、靴、髪、性器や乳房をつつむ下着などに集中されるのは〈私〉の稀薄なもの、〈私〉のないものと、〈私〉の集約的なもの、〈私〉の濃いものとが、そこで背反的に集まり、その果てに分割され、身体と意味のつながりが破綻をきたすことができるものだからだ。これは身体部位の整形というコスメティックな行為の極限にまで人間の原衝動を走らせることになる。ひとはなぜ整形美容の行為にむかうのか。著者の理解を延長してゆけば、整形美容の欲求には、あらかじめ身体から〈私〉を稀少にしてゆく極限が同時に〈私〉を極大にすることになっている身体像のイメージがあって、それに向ってそれぞれの部位に整形手術がほどこされることだからだ。仮面やマスクをつけ〈私〉をなくしてしまう身体の行為が、〈私〉を解放することがあるように、整形によって身体の部位を入れ替えてしまう行為が、身体の全部にわたったとしても、〈私〉は〈私〉でありうるのだろうか。コスメティックな行為の極限はこの本の著者のかんがえをアレンジしてゆけば、そういう問題にゆきつくことになる。そしてこれは著者によれば反復的ではあるが不朽の問題なのだ。〈私〉が〈私〉を解釈している像と〈私〉が〈私〉としてある存在とのあいだにずれ、矛盾、背反があり、〈私〉が〈私〉の眼ざしをもてあまし、〈私〉の近さと遠さのあいだに不釣合があるかぎり、ファッション行為とコスメティックな身体行為は廃棄不可能な現象だからだと著者は結語のように書いている。
この本の意義深さもおなじところにあると思う。何よりもファッションとコスメティックを不朽の現象として真正面から真摯に本格的に論じて、どこにも悪ふざけやけれんを感じさせない最初の邦書のモード論なのだ。ただ著者がいささか途中で照れたためにファッシヨンの現場の表現論におりてゆかずに身体論一般の方に上昇してしまったが、ほんとは著者みたいな人がファッション・コレクションの現場批評に乗りだす場面を空想したい気がする。
【この書評が収録されている書籍】
この本の著者がやっているのは、はじめての「本格的」なファッション論だという意味で、とても高く評価さるべきだとおもえる。著者のファッションにたいする基本的なコンセプションは、ファッションとしてみられた衣裳の構造が、裸の魅力を隠すようにしながら、じつはそれを強調する、また肉体の魅力で誘惑しながら、きわどいところで拒絶する、肉体を保護しながら同時に損傷させる、といったような二律背反の作用だという点にある。そしてこの背反する運動がやっと均衡しているところで、ファッションのスタイルが決定されているが、やがて身体がもつ根源的な不均衡のなかに入りこみ、その不均衡に動かされて反復移動してゆく。この基本的なコンセプションは、著者によってさまざまな形で強調されて、この本の背骨になっている。男性のカラー、ネクタイ、ベルトは首や胴を締めあげ、拘束するものだ。だがそれは同時に気品とか儀礼とかに叶うものとされる。女性のタイト・スカート、コルセットなどは腰を締めつけて内臓障害をもたらすほどだし、タイト・スカートは歩くこと、活動することを極端に不自由にする。だがそれは身体の美しさ、人格の貞淑さ、慎み深さを表現するものとされて、十九世紀ファッション史を飾った。こういったファッションのもつ二律背反の構造をつきつめてゆけば、ファッションの原則が、モデルを身体に合わせるのではなく、身体をモデルに合おせるのだということがわかると、この本の著者は強調する。シンデレラ物語は、のこされた靴にあうような足の持主を探し出そうとする王子の願望が発端になるのだし、中国の封建時代の纏足の風習は、幼児のときから足を畸形にまるめて細く小さな靴に合わせようとする飽くなき欲求に発したものだし、日本の吉原花街の太夫おいらんは高く重い木履をはいて、重力の拘束に身をゆだねることが、美と忍従と華やかさの象徴であった。この非合理、拘束と解放の二律背反と共存、禁忌と煽動の背中あわせ、そのあげくに身体を損傷し、内臓が病におかされるまで締めつけて、そのときそれが美であると信じられた。そんな何の客観性もない拘束に身をゆだねる不可能な変形、逸脱、畸形。そうとしかいいようのない美意識に従属してゆく逆説的な本質がファッションだと著者はいう。
もう一度だけ、合計三度この著者はファッションの二律背反と、不釣合、不均衡の根源的な欲求とが皮膚や衣裳の表面で演ずる逆説的なドラマについて伝えている。それは隠しながら見せるということについてだ。胸もとのボタンを外したシャツ、シースルーのブラウス、乳首が浮きでる薄手のセーター、深いスリットの入ったスカート、すれすれのミニスカート、身体の線がくっきりと出るニットのワンピース等々。著者は秘匿さるべきものへの関心を掻きたて、貞淑の焦点を逆に想像させる挑発になっているファッションの原則の例としてあげながら、しだいにファッションの本質を性的な欲望論に結びつける西欧的な衣裳論の系譜に近接してゆく。眼線から眼ざしによる皮膚や衣裳の表面への接触感をふくめて、あらためてこの本の著者のファッション論、禁止と挑発の二律背反を原則とするファッションの変遷と反復の論議をふりかえってみると、それが性的な欲望の禁忌と解放の原則にゆきつくことがわかる。人間はなぜ衣裳をまとい、しかもつぎつぎと衣裳の歴史をファッションとして循環させ反復してゆくのか。それは性的な欲望を挑発し、挑発しながら禁止するという二律背反の作用を実現するためだ。なぜ人間はそんな手のこんだことをするのか。人間の存在の根拠にはたがいに相反するようなふたつの原動機があって、このふたつの根源的な不釣合によって移動し、釣合に達し、またそこから不釣合の方へまた駆りたてられてゆく本質があるからだ。もしこの不釣合と釣合との存在論的な運動を、視線の表面性や性的な欲動の皮膜での眼ざしの接触というところからみていけば、ファッションの本質ともいうべきものに到達する。これがこの本の著者のファッション論の核になっている考え方であることがわかる。この考えはひとつの岐路に立つことになる。ファッションの表現論の方へ下りてゆくか、身体論の一般の方へ上昇してゆくか。そして著者は身体論の方へ上昇してゆくようにみえる。
まず仮面ということ。顔にマスクをつけることは衣裳の類型化を極限におしすすめることと同義だから〈私〉や〈私〉の表情がかくされ匿名化するために「顔さえ隠せば何でもできる」という欲動の解放とおなじことになっている。たとえば秘密の性的パーティでは仮面さえつけていれば、それ以外の衣裳はみんな脱ぎすてることもできるし、またドアのかわりに仮面を備えつけたトイレもあった。これはおしすすめてゆけばエロティシズムの問題に帰着する。秘部=性器自体はエロティシズムを喚起しないし、顔の写っていないヌード写真はべつにエロティックではない。このばあい背反しあう一方のヴェクトルである〈私の〉という禁忌を表象するものが欠けているからだと著者はのべている。そしてもうこのあたりから欲動の表面性と皮膜性から視られた身体論の方へはいってゆく。人間の身体のなかでそこに眼ざしを集中していると妙な気分で、視ている眼ざしの根拠から浮きあがって客体的になってしまう個所があると著者はいう。たとえば脚や髪や生殖器など。著者によればこういう部位は、仮面やマスクとおなじように〈私〉が少ない部分だからだ。髪とか生殖器とかは〈私〉の意志をはみだし、ざんばらになったりぶらぶらしてしまうし、脚は〈私〉の意志とかかわりなくある姿勢で歩きだしたり、とまったりしているようにみえる。そしてひとはなぜコスメティックに髪をセットしたり、マニキュアを塗ったり、ストッキングをつけハイヒールをはいたりしてじぶんの身体を拘束するかといえば、〈私〉の薄くなった身体の尖端の部分を、ことさら際立たせて〈私〉性を回復し、身体の輪郭をはっきりさせようと志向するからだ。このコスメティックな行為が極端になり、病的な領域に入りこんでゆけば、〈私〉の身体から〈私〉を鮮明に確かめようとして、局部を鏡に映してみたり、肛門に物体を突っ込んだり、路上で女性にペニスを見せびらかしたりする行為になってあらわれる。これは眼ざしを行使する方の側からもいえることだ。
いわゆるフェティシズムが脚をつつむストッキング、靴、髪、性器や乳房をつつむ下着などに集中されるのは〈私〉の稀薄なもの、〈私〉のないものと、〈私〉の集約的なもの、〈私〉の濃いものとが、そこで背反的に集まり、その果てに分割され、身体と意味のつながりが破綻をきたすことができるものだからだ。これは身体部位の整形というコスメティックな行為の極限にまで人間の原衝動を走らせることになる。ひとはなぜ整形美容の行為にむかうのか。著者の理解を延長してゆけば、整形美容の欲求には、あらかじめ身体から〈私〉を稀少にしてゆく極限が同時に〈私〉を極大にすることになっている身体像のイメージがあって、それに向ってそれぞれの部位に整形手術がほどこされることだからだ。仮面やマスクをつけ〈私〉をなくしてしまう身体の行為が、〈私〉を解放することがあるように、整形によって身体の部位を入れ替えてしまう行為が、身体の全部にわたったとしても、〈私〉は〈私〉でありうるのだろうか。コスメティックな行為の極限はこの本の著者のかんがえをアレンジしてゆけば、そういう問題にゆきつくことになる。そしてこれは著者によれば反復的ではあるが不朽の問題なのだ。〈私〉が〈私〉を解釈している像と〈私〉が〈私〉としてある存在とのあいだにずれ、矛盾、背反があり、〈私〉が〈私〉の眼ざしをもてあまし、〈私〉の近さと遠さのあいだに不釣合があるかぎり、ファッション行為とコスメティックな身体行為は廃棄不可能な現象だからだと著者は結語のように書いている。
この本の意義深さもおなじところにあると思う。何よりもファッションとコスメティックを不朽の現象として真正面から真摯に本格的に論じて、どこにも悪ふざけやけれんを感じさせない最初の邦書のモード論なのだ。ただ著者がいささか途中で照れたためにファッシヨンの現場の表現論におりてゆかずに身体論一般の方に上昇してしまったが、ほんとは著者みたいな人がファッション・コレクションの現場批評に乗りだす場面を空想したい気がする。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする