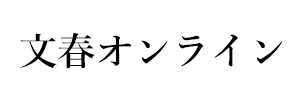書評
『倉本美津留の超国語辞典』(朝日出版社)
「必死」は、ほとんどの場合、死なない。日本語にツッコミ入れて遊びたおした辞典
言葉で、こんなに遊べるのか! と驚かされる。たとえば「大げさ表現語」。日本語の慣用句に対して、大げさすぎるんじゃね? とツッコミを入れるという遊びだ。「必死」←ほとんどの場合、死なない。「顔に泥を塗る」←秘境の部族でもあるまいに。「毒舌」←まず自分が死ぬ。などなど。
「お言葉・御の字」では、「御」をつけることで、言葉がさまざまに変化する様子を楽しむ。「ネガティブになる」コーナーを見てみると「上手に御をつけたらイヤミになる(お上手)」「荷物に御をつけたら厄介者になる(お荷物)」「めでたいに御をつけたらバカになる(おめでたい)」といった具合。
他にも「おかしな名前つけられて(安全ピンは安全じゃない、膝枕はモモ枕など)」「比喩表現の夕べ(飯に種はあるか、豆腐の角に頭をぶつけると死ぬか、などを検証)」「そんなたとえやめてくれ(馬の骨や野次馬への馬からの反論、犬死や負け犬への犬からの反論)」などなど、これでもほんの一部にすぎないほど、とにかく日本語で遊びたおしている一冊だ。
遊びの内容の充実度もすごいが、そもそもこんな遊びを思いつけるというところがすごい。私たちが普段、何の疑問も抱かずに、あたりまえに使ってしまっている日本語に、著者はいちいち「なんで? なんで?」とからんでいる。まるで小学生男子が、大好きな女の子にちょっかいを出すかのように。つまり、これは言葉に対して、子どものように真っ直ぐでなければ思いつけない遊びの数々だ。
ちなみに、我が家には本物の小学生男子がいる(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2016年2月)。先ほどの「顔に泥を塗る」に対して、彼は「びよう」と答えていた。「膝枕」という語を知ったときには、私の膝に頭を載せてみないと気がすまなかった(もちろん痛くて、すぐにやめた)。
そんな子ども同様の純粋さに加えて、著者には大人としての半端じゃない言葉への見識がある。
私は、画家の有元利夫の言葉を思い出した。
……使い古された言い方は、『手垢にまみれた』とかなんとか因縁をつけられて、だんだん敬遠されてしまう。考えてみれば、通俗な表現というのは、人間のどこかにそれだけ深く根差しているものだからこそ、広く行きわたって『通俗』になったと思うのです。(『有元利夫 女神たち』)
この「手垢」の成分を徹底分析したのが本書なのだ、とも言えるだろう。
ALL REVIEWSをフォローする