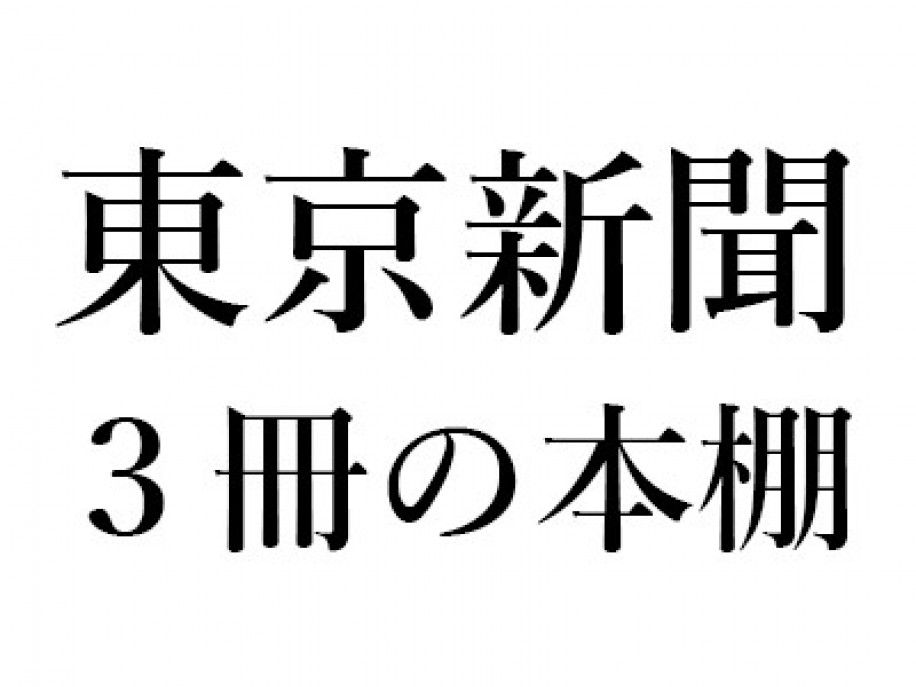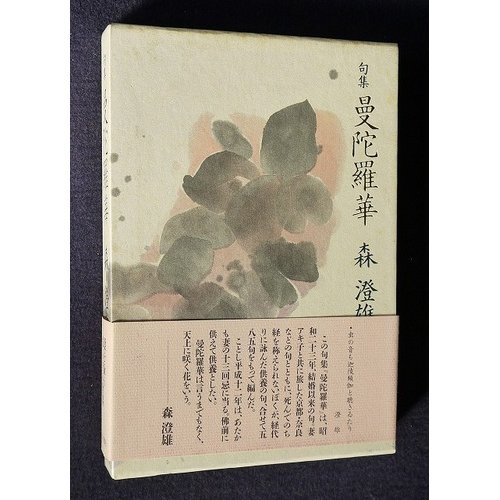書評
『川端康成・三島由紀夫往復書簡』(新潮社)
九八年一月某日 正月に読んだ本のなかで『川端康成・三島由紀夫 往復書簡』(新潮社)は興味深く、いろいろなことを考えさせられる作品であった。雑誌「新潮」に掲載された時もそうだったが、三月以上の間があって単行本になってみると、私にはこの往復書簡が読む者に与える感動を混えた痛切さの内容がさらに明確に伝ってくるようであった。
まずはじめに、師と仰いでいた先輩への三島由紀夫の礼儀正しさと心遣いの美事さに驚かされた。しかしその雰囲気はノーベル賞に関連する事柄が二人の間に介在するようになって変りはじめる。礼儀正しさは変らないのだが、三島由紀夫の川端宛書簡から、何か目に見えない香気のようなものが消えてゆくのである。それは、世上勘ぐられているような競争心や嫉妬心とは違う。むしろ、何かを「見てしまった」という気分が三島由紀夫の方に生れたとしか思えない。二人の美意識の相似と差異もこの頃になればはっきりし、しかしお互を認める点では二人とも変らないのだ。本質の違う芸術家同士の関係の困難と緊張と深さをこの書簡集ぐらい正直に語っている例は少いのではないか。これは「君子のまじわり」が持っている輝しさと暗部の開示といってもいいのではないか。
二人と面識のあった私としては、ギリシャと陽明学は川端康成の理解の外にあり、川端流の雪月花への感動は三島由紀夫とは縁がなかったように思う。世代的には川端康成よりは三島由紀夫に近かった私には、彼の歯に衣を着せない川端評を耳にする機会が多かったのである。
そんなことを考えながら、今の作家や詩人はこうした関係を誰かと持っているだろうかと考えざるを得なかった。友人はいる。親しい仲間も多い。しかし私の場合、年齢では私の方が上でも、文学の世界では私より先輩の作家詩人がたくさんいるのだ。それは私にとって一種の不幸かもしれないという気がする。
【この書評が収録されている書籍】
まずはじめに、師と仰いでいた先輩への三島由紀夫の礼儀正しさと心遣いの美事さに驚かされた。しかしその雰囲気はノーベル賞に関連する事柄が二人の間に介在するようになって変りはじめる。礼儀正しさは変らないのだが、三島由紀夫の川端宛書簡から、何か目に見えない香気のようなものが消えてゆくのである。それは、世上勘ぐられているような競争心や嫉妬心とは違う。むしろ、何かを「見てしまった」という気分が三島由紀夫の方に生れたとしか思えない。二人の美意識の相似と差異もこの頃になればはっきりし、しかしお互を認める点では二人とも変らないのだ。本質の違う芸術家同士の関係の困難と緊張と深さをこの書簡集ぐらい正直に語っている例は少いのではないか。これは「君子のまじわり」が持っている輝しさと暗部の開示といってもいいのではないか。
二人と面識のあった私としては、ギリシャと陽明学は川端康成の理解の外にあり、川端流の雪月花への感動は三島由紀夫とは縁がなかったように思う。世代的には川端康成よりは三島由紀夫に近かった私には、彼の歯に衣を着せない川端評を耳にする機会が多かったのである。
そんなことを考えながら、今の作家や詩人はこうした関係を誰かと持っているだろうかと考えざるを得なかった。友人はいる。親しい仲間も多い。しかし私の場合、年齢では私の方が上でも、文学の世界では私より先輩の作家詩人がたくさんいるのだ。それは私にとって一種の不幸かもしれないという気がする。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする