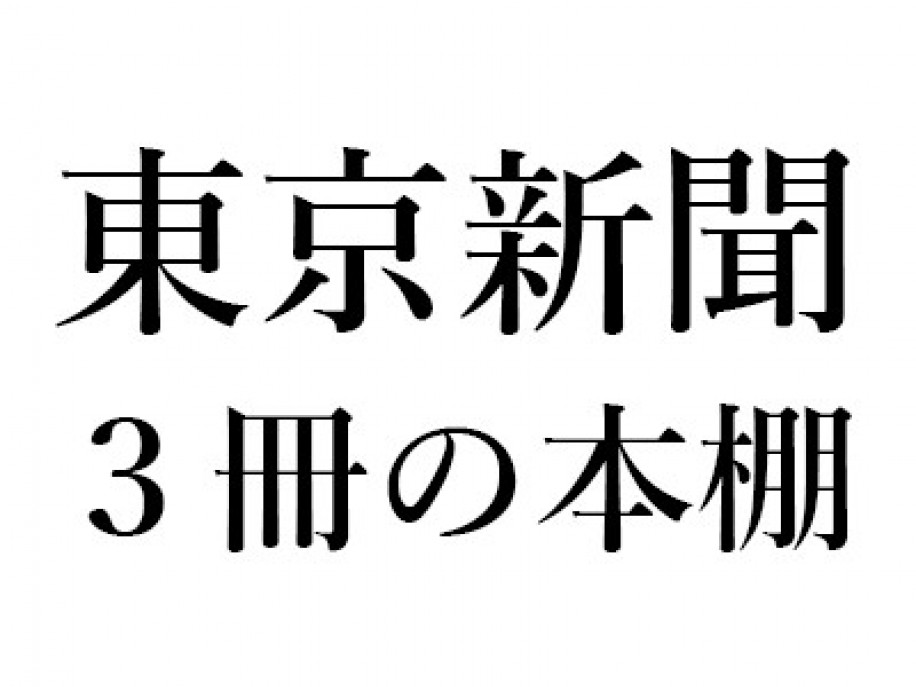書評
『銭湯の女神』(文藝春秋)
女性誌や広告の世界で幅をきかせている言葉の数かず――「ほんとうの私」「自然体で生きる」「ワンランク上の女になる」などにウンザリしている人には『銭湯の女神』(文藝春秋)をぜひ読んでもらいたい。
三十過ぎて一人暮らしを始め銭湯に通う著者に言わせれば「銭湯で体を洗う人々を眺めていると、『自分らしく生きる』とか『私らしさ』という言葉に笑ってしまいたくなる。人間は生きているだけでどうしようもなく個性的だ」というのだから。
女性誌や広告の世界とはまったく違った所から、ほとんど正反対の所から、この世の中を、自分を、みつめている。
銭湯の話ばかりではない。ファミリーレストラン、一〇〇円ショップ、ゴミ出し問題、インターネット……などについて語った三十九のエッセー集だ。あくまでも重心低く、具体的な事柄を題材としながら、どれもカツンと手ごたえのある文明批評になっている。
その中で私が最も感動を持って読んだのは「一〇〇円の重み」という章だ。著者は日本人の高級ブランド熱に違和感を持っているが、一〇〇円ショップにも奇妙な「うしろめたさ」を抱いている、「物には最低限の価値というものがあり、その価値は自分で金を払って覚えていくものである」一○○円ショップはいうなれば、あらかじめ邪険にされる運命を負わされた悲しい商品の墓場である」
ある日、一〇〇円ショップでプラスチック製の健康青竹を買って、実家に持って行くと、長年町工場(鋳物業)を経営していた父親は「これ、型を作るのは大変なんだ」「これが一〇〇円だったら、型を作った奴には一体いくら入るんだろう」と眩き、それだけだったが、結局一度も青竹を踏まなかった――。
著者はそういう父親の行動に注目し、深く何かを感じ取らずにいられない人間なのだ。私はそういう著者の感受性を信頼する。「日本人は下品になったというより鈍感になったのだ」という言葉もみごとだ。
【この書評が収録されている書籍】
三十過ぎて一人暮らしを始め銭湯に通う著者に言わせれば「銭湯で体を洗う人々を眺めていると、『自分らしく生きる』とか『私らしさ』という言葉に笑ってしまいたくなる。人間は生きているだけでどうしようもなく個性的だ」というのだから。
女性誌や広告の世界とはまったく違った所から、ほとんど正反対の所から、この世の中を、自分を、みつめている。
銭湯の話ばかりではない。ファミリーレストラン、一〇〇円ショップ、ゴミ出し問題、インターネット……などについて語った三十九のエッセー集だ。あくまでも重心低く、具体的な事柄を題材としながら、どれもカツンと手ごたえのある文明批評になっている。
その中で私が最も感動を持って読んだのは「一〇〇円の重み」という章だ。著者は日本人の高級ブランド熱に違和感を持っているが、一〇〇円ショップにも奇妙な「うしろめたさ」を抱いている、「物には最低限の価値というものがあり、その価値は自分で金を払って覚えていくものである」一○○円ショップはいうなれば、あらかじめ邪険にされる運命を負わされた悲しい商品の墓場である」
ある日、一〇〇円ショップでプラスチック製の健康青竹を買って、実家に持って行くと、長年町工場(鋳物業)を経営していた父親は「これ、型を作るのは大変なんだ」「これが一〇〇円だったら、型を作った奴には一体いくら入るんだろう」と眩き、それだけだったが、結局一度も青竹を踏まなかった――。
著者はそういう父親の行動に注目し、深く何かを感じ取らずにいられない人間なのだ。私はそういう著者の感受性を信頼する。「日本人は下品になったというより鈍感になったのだ」という言葉もみごとだ。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 2001年12月16日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする