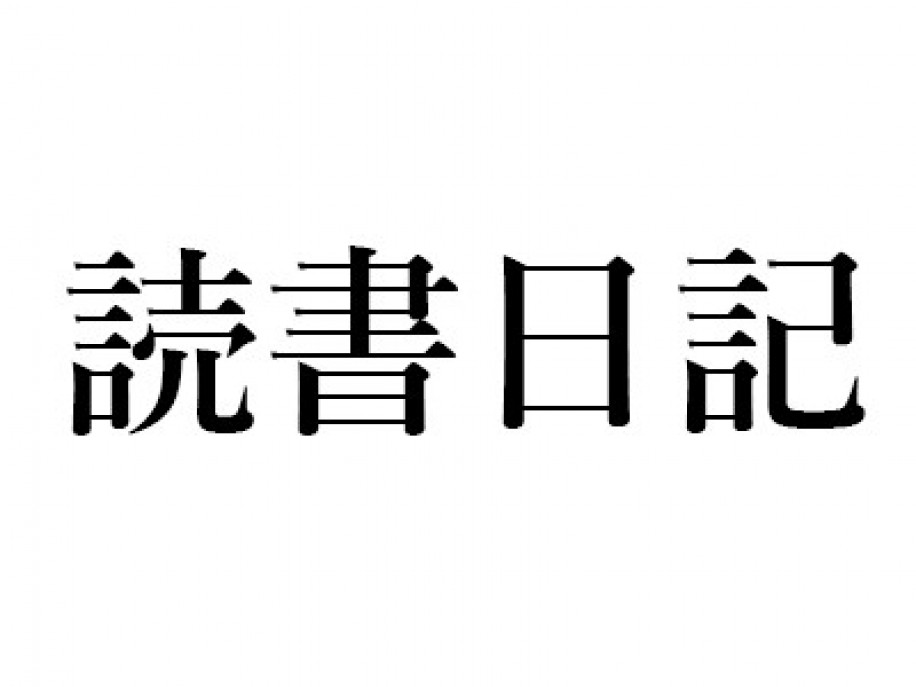解説
『和菓子屋の息子―ある自伝的試み』(新潮社)
私は「下町情緒」が嫌いだ。美しくないから。
今、目にしたり耳にしたりする「下町情緒」ほど怪しく気味の悪いものはない。
そもそも、あの、勘亭流まがいのぐにゃぐにゃとした筆文字の看板が厭だ。「下町情緒」が売り物の街を歩くと必ずあの手の看板を派手にかかげた店がある。もんじゃ焼の店だったりカラオケ・スナックだったりみやげ物屋だったりするわけだが、店員はたいてい妙な半纏(はんてん)のような作務衣(さむえ)のようなものを着ていて、洗面所の扉には「音入(オトイレ)」なんて書いてあったりするのだ。
TVの下町人情ドラマとなると必ずガラガラ声の肥満系おばさん女優が茶髪に原色のTシャツとスパッツといういでたちで出て来て、家族・親類・隣り近所のもめごとに暑苦しく介入し、ツバを飛ばしそうないきおいでわめき散らし、かと思うとささいなことですぐめそめそ泣いてみせたりするのだ。
東京の下町というものに対して、何か大きな誤解が横たわっているとしか思えない。人びとは東京の下町に下町を求めるのではなく、田舎を求めているようにさえ思える。奇妙な「下町」ファンタジー。そして、ある時期から、下町に対するこの誤解は商売になるようになった。80年代バブル期、「地上げ」で下町が食い荒されていったのと、ほとんど時を同じくして。下町が消えて行くのと同時に皮肉にも「下町」ファンタジーが幅を利かせるようになったのだ。
「これは違うんじゃないか、おかしいんじゃないか」と憤懣やるかたなかったが、いかんせん私は下町のネイティブではない。家の墓は江戸時代から浅草だが、戦争直前に東京を引き払ってしまったので、無念残念、私が生まれ育ったのは東京ではない。ヨソモノが何か言ったってあんまり説得力はないだろう。
小林信彦『和菓子屋の息子』(新潮文庫)は、異様な記録癖に恵まれた(この際やっぱり「恵まれた」と言うべきだろう)ネイティブによる「下町」ファンタジー粉砕の書である。
今の「下町」ファンタジーに洗脳されている人びとは、著者が日本橋生まれだということの格別な意味が、まず、わからないだろう。「お江戸日本橋七つだち……」と東海道五十三次の起点として歌にも詠み込まれているが、今の人たちにとっては(いや、私自身にとっても)、日本橋という所が江戸以来の下町文化の最も洗練された中心地であったという事実はなかなか実感としてはわからない。戦後はいくつかのデパートのある所だという印象だけで、「昔の日本橋は江戸の真んなかで、江戸っ子のお守りはここから出ますといったような気稟(きっぷ)の土地だった」(鏑木清方『明治の東京』岩波文庫)と言われても、全然ピンと来ないのだ。
だからこそ、『和菓子屋の息子』は表紙写真からして意表をつく。昭和十一年(36年)七五三の時の小林一家の記念写真。つばの広い帽子、エレガントなスーツ(ベルベットか?)、エナメル靴といったリトル・プリンスのごときハイカラないでたち。後ろのおとうさん(その名は、九代目・小林安右衛門だ)のいかにも上等のあつらえの正装、ふちなしめがね。結婚指輪にも注目したい。もしかして今よりずうっと本格じゃあないか。
戦前昭和の、東京下町の、比較的豊かな商家の姿。それは当時の日本全体の中では、やっぱり、そうとう特殊な世界だったに違いない。層としては薄いものであったに違いない。
しかし、限定された世界の中ではあったものの、そのモダニズムは思いのほか本格的で、生活の中に深く根をおろしていたようである。
(次ページに続く)
今、目にしたり耳にしたりする「下町情緒」ほど怪しく気味の悪いものはない。
そもそも、あの、勘亭流まがいのぐにゃぐにゃとした筆文字の看板が厭だ。「下町情緒」が売り物の街を歩くと必ずあの手の看板を派手にかかげた店がある。もんじゃ焼の店だったりカラオケ・スナックだったりみやげ物屋だったりするわけだが、店員はたいてい妙な半纏(はんてん)のような作務衣(さむえ)のようなものを着ていて、洗面所の扉には「音入(オトイレ)」なんて書いてあったりするのだ。
TVの下町人情ドラマとなると必ずガラガラ声の肥満系おばさん女優が茶髪に原色のTシャツとスパッツといういでたちで出て来て、家族・親類・隣り近所のもめごとに暑苦しく介入し、ツバを飛ばしそうないきおいでわめき散らし、かと思うとささいなことですぐめそめそ泣いてみせたりするのだ。
東京の下町というものに対して、何か大きな誤解が横たわっているとしか思えない。人びとは東京の下町に下町を求めるのではなく、田舎を求めているようにさえ思える。奇妙な「下町」ファンタジー。そして、ある時期から、下町に対するこの誤解は商売になるようになった。80年代バブル期、「地上げ」で下町が食い荒されていったのと、ほとんど時を同じくして。下町が消えて行くのと同時に皮肉にも「下町」ファンタジーが幅を利かせるようになったのだ。
「これは違うんじゃないか、おかしいんじゃないか」と憤懣やるかたなかったが、いかんせん私は下町のネイティブではない。家の墓は江戸時代から浅草だが、戦争直前に東京を引き払ってしまったので、無念残念、私が生まれ育ったのは東京ではない。ヨソモノが何か言ったってあんまり説得力はないだろう。
小林信彦『和菓子屋の息子』(新潮文庫)は、異様な記録癖に恵まれた(この際やっぱり「恵まれた」と言うべきだろう)ネイティブによる「下町」ファンタジー粉砕の書である。
今の「下町」ファンタジーに洗脳されている人びとは、著者が日本橋生まれだということの格別な意味が、まず、わからないだろう。「お江戸日本橋七つだち……」と東海道五十三次の起点として歌にも詠み込まれているが、今の人たちにとっては(いや、私自身にとっても)、日本橋という所が江戸以来の下町文化の最も洗練された中心地であったという事実はなかなか実感としてはわからない。戦後はいくつかのデパートのある所だという印象だけで、「昔の日本橋は江戸の真んなかで、江戸っ子のお守りはここから出ますといったような気稟(きっぷ)の土地だった」(鏑木清方『明治の東京』岩波文庫)と言われても、全然ピンと来ないのだ。
だからこそ、『和菓子屋の息子』は表紙写真からして意表をつく。昭和十一年(36年)七五三の時の小林一家の記念写真。つばの広い帽子、エレガントなスーツ(ベルベットか?)、エナメル靴といったリトル・プリンスのごときハイカラないでたち。後ろのおとうさん(その名は、九代目・小林安右衛門だ)のいかにも上等のあつらえの正装、ふちなしめがね。結婚指輪にも注目したい。もしかして今よりずうっと本格じゃあないか。
戦前昭和の、東京下町の、比較的豊かな商家の姿。それは当時の日本全体の中では、やっぱり、そうとう特殊な世界だったに違いない。層としては薄いものであったに違いない。
しかし、限定された世界の中ではあったものの、そのモダニズムは思いのほか本格的で、生活の中に深く根をおろしていたようである。
最近の研究において、関東大震災後の東京下町の建造物がけっこう〈計画されたモダニズム〉で統一されていたことが知られるようになった。たとえば、小学校はアール・デコ調の鉄筋コンクリート建築で、暖房完備、トイレは水洗、という規定である。映画、音楽、カフェだけがモダンではなかったのだ。モダニズムは個人の家の建て方にまで侵入していた。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする