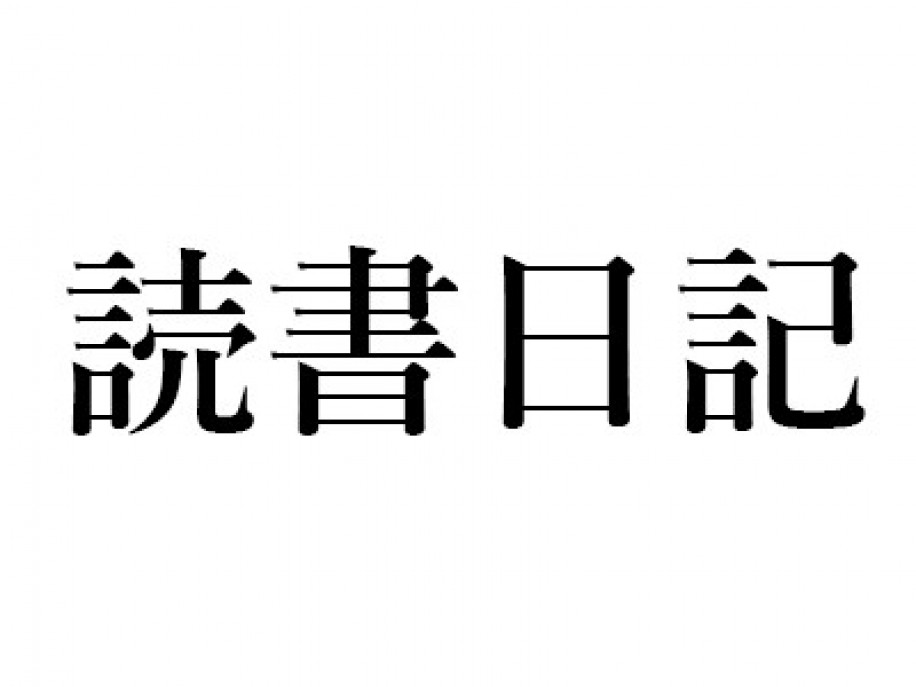解説
『和菓子屋の息子―ある自伝的試み』(新潮社)
著者の父親は当時は珍しい車マニアで、「一九三〇年代といえば、モーリス・シュヴァリエ調のカンカン帽、白麻の上下のスーツに蝶ネクタイ(水玉模様のが多い)、白か、白と茶のコンビネーションの靴という時代だが、じっさいにそういう恰好をして」いた。
著者は母方のおじいさんの遺した膨大な日記、手紙、文学作品、映画、当時のレストランのメニューまで駆使して、いつの頃よりか世間に流布している「下町」ファンタジーを粉砕し、記憶の中にある、いやもはや記憶の中にしか存在しない〈幻の町〉の姿をよみがえらせている。
私がこの本の中で最も面白く思ったのは、著者が〈下町の人間の特徴〉として六項目をあげている、その最後の「説明しない〈批評〉」という言葉だ。
著者はこんなふうに書いている。
とても僭越(せんえつ)な言い方になってしまうが、私はこのくだりを読んだとき、「わが意を得たり!」と興奮したのだ。
その興奮には二重の意味がある。一つは、「江戸っ子」「江戸前」「都会的」「東京風」「粋」などの言葉を振り回すのはひとごとながら何だかとても恥ずかしいという気持があったので。
また、もう一つ、「不可視の拘束力」がどうのこうのとか「言説の時空」がああだこうだといった文章は知的には違いないんだろうが、何だかとても野暮ったいという気持があったので。
私のそういう感じ方は、まっとうなものなのだか変なものなのだかは、よくわからない。とにかく、この『和菓子屋の息子』の中の「説明しない〈批評〉」という言葉と出会って、「あ、私の感じ方、それほどまちがってはいなかったのね。同じような感じ方をする人はちゃんといるのね。そういう感じ方のほうが王道という世界はあったのね」と思ったのだ。
「説明しない〈批評〉」という言葉は、また、「見巧者(みごうしゃ)」という、今や死語となった言葉を思い起こさせた。芸や芸人に対する鑑識眼はすぐれているのだが、評論家のように理屈立てて説明することはできないし、また、する気もない。そういう人を昔は「見巧者」と言った。それが死語となったというのは、やっぱりそういう層が薄くなった、ということだろうか。評論家の多い世の中より見巧者の多い世の中のほうが、私には豊かな世の中に思えるのだけれども。
かつての下町文化の美しさは、著者の父親の姿に結晶されて描かれている(駄目な部分も含めて、美しいのである)。文化や歴史というのは、博物館や記念館や図書館などの中にあるわけではない。具体的に人間の中に、人びとの生活の中にその生命を持っている。〈幻の町〉をよみがえらせようとしたこの本は、父・小林安右衛門という、一人の独得にかっこいい男の肖像画にもなっている。
下町(神田)に生まれ育った評論家・福田恆存のこんな言葉を思い出す。
そういう意味で、この『和菓子屋の息子』は、失われたある教養の物語と言ってもいいと思う。
【この解説が収録されている書籍】
著者は母方のおじいさんの遺した膨大な日記、手紙、文学作品、映画、当時のレストランのメニューまで駆使して、いつの頃よりか世間に流布している「下町」ファンタジーを粉砕し、記憶の中にある、いやもはや記憶の中にしか存在しない〈幻の町〉の姿をよみがえらせている。
私がこの本の中で最も面白く思ったのは、著者が〈下町の人間の特徴〉として六項目をあげている、その最後の「説明しない〈批評〉」という言葉だ。
著者はこんなふうに書いている。
このような生活の中心には、ある種の批評がある。〈粋〉とか〈野暮〉というものがそれで、彼の生活は〈粋〉であることを軸にして動いている。彼が興味を抱かないものは、〈粋〉ではないと判定されたものだ。その判定を他人に説明することはしないし、気むずかしさを他人に悟られるのも好まない。
批評はもっと具体的に、他人に対しても下されるが、口にすることはめったにない。ただ芸人に関しては、××(落語家)も荒れてきたな、とか、マーナ・ロイの色気は今が旬じゃないか、などとつぶやく。まちがっても〈粋〉というキイ・ワードを口にしないのは、〈粋〉が云々(うんぬん)と言った瞬間、自分が最悪の存在(野暮天)に落ちるのを充分に自覚しているからである。
とても僭越(せんえつ)な言い方になってしまうが、私はこのくだりを読んだとき、「わが意を得たり!」と興奮したのだ。
その興奮には二重の意味がある。一つは、「江戸っ子」「江戸前」「都会的」「東京風」「粋」などの言葉を振り回すのはひとごとながら何だかとても恥ずかしいという気持があったので。
また、もう一つ、「不可視の拘束力」がどうのこうのとか「言説の時空」がああだこうだといった文章は知的には違いないんだろうが、何だかとても野暮ったいという気持があったので。
私のそういう感じ方は、まっとうなものなのだか変なものなのだかは、よくわからない。とにかく、この『和菓子屋の息子』の中の「説明しない〈批評〉」という言葉と出会って、「あ、私の感じ方、それほどまちがってはいなかったのね。同じような感じ方をする人はちゃんといるのね。そういう感じ方のほうが王道という世界はあったのね」と思ったのだ。
「説明しない〈批評〉」という言葉は、また、「見巧者(みごうしゃ)」という、今や死語となった言葉を思い起こさせた。芸や芸人に対する鑑識眼はすぐれているのだが、評論家のように理屈立てて説明することはできないし、また、する気もない。そういう人を昔は「見巧者」と言った。それが死語となったというのは、やっぱりそういう層が薄くなった、ということだろうか。評論家の多い世の中より見巧者の多い世の中のほうが、私には豊かな世の中に思えるのだけれども。
かつての下町文化の美しさは、著者の父親の姿に結晶されて描かれている(駄目な部分も含めて、美しいのである)。文化や歴史というのは、博物館や記念館や図書館などの中にあるわけではない。具体的に人間の中に、人びとの生活の中にその生命を持っている。〈幻の町〉をよみがえらせようとしたこの本は、父・小林安右衛門という、一人の独得にかっこいい男の肖像画にもなっている。
下町(神田)に生まれ育った評論家・福田恆存のこんな言葉を思い出す。
一時代、一民族の生き方が一つの型に結集する処(ところ)に一つの文化が生れる、その同じものが個人に現れる時、人はそれを教養と称する。
そういう意味で、この『和菓子屋の息子』は、失われたある教養の物語と言ってもいいと思う。
【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする