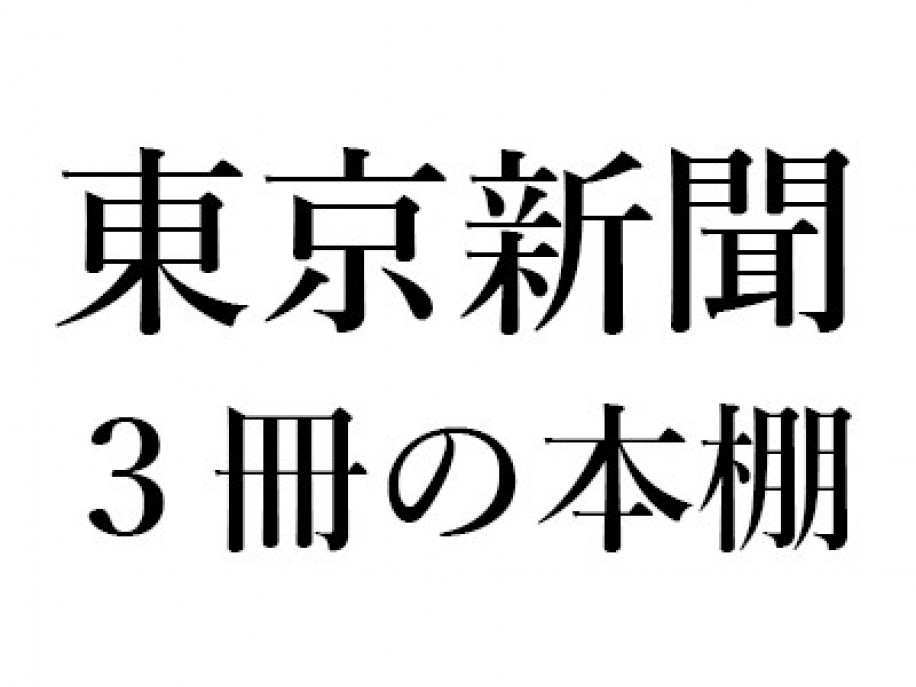対談・鼎談
『父京助を語る』 (教育出版)|丸谷才一+木村尚三郎+山崎正和の読書鼎談
木村 だれでもご承知のように、金田一京助さんはアイヌ語、アイヌ文学ないしアイヌ民俗研究の第一人者で、『アイヌ叙事詩ユーカラの研究』によって帝国学士院恩賜賞を授けられた大学者です。そのお子さんの春彦さんが、父親の素顔を非常に素直に語ったのがこの本なんですが、淡々とした語り口の中に、大学者というものの姿が、じつによく描かれている。これによると、金田一京助さんはたいへんに愉快な人なんですね。天皇陛下の御前講義で、十五分の持ち時間をはるかにオーバーして一時間も話してしまったとか、教え子の結婚式に行って、フルコースを全部食べたあと、違う人の結婚式だったことに気がついたとか……(笑)。
丸谷 前の日にすんでいたんですね(笑)。
木村 原稿依頼の速達に返事を出して一文を草したところが、それは二年前の郵便で、雑誌はとうに廃刊になっていたという話とか、放送局から春彦さんに出演の依頼があったところが、迎えの車がこない。車が間違えて近くに住んでいる京助先生のほうに迎えに行ってしまったんですね。ところが何と京助先生は、あろうことかその車に乗って放送局へ来てしまう。あとで慌てて春彦さんが行ってみると、ニコニコして待っていて、結局、期せずして父子共演になった。
丸谷 あの父子共演の話、ぼくは、とっても愉快だった。いい話ですね。
木村 また、父親と精神的に関わりのあった七人の女性の話が出てくる。この中には、〈世が世ならば父親と結婚したかもしれない人が数人いることを私は断言する〉などという穏やかならぬ表現もあります。その反面、奥さんというのは、つまり、自分の母親のことですが、学者よりも役者のほうが好きだという人で、悪妻であった。ソクラテスの妻、クサンチッペみたいな存在だったといいます。この著者はかなりクールな感覚をもっていて、父親と母親の姿を客観的に冷静に描いている。
著者は父親をつねにライバルと考えながら、今日まできたようで、最後に、父親と自分の点数づけをやっている。父親はNHKから放送文化賞というものをもらっているけれども〈(私のほうが)NHKへの貢献ははるかに多く、放送回数も断然上回る。この分では、こちらも文化賞とやらをもらえそう〉などと記すところ、相当な神経の持ち主ではないかという気もするわけですが、全体として非常にさわやかな読後感があります。
山崎 やんごとない家の人というのは、われわれ常人のような恥ずかしさという感覚がないんですってね。つまり、人の前で裸になるというようなことは何でもない。
そういう意味の臆面のなさというか、恥ずかしさをまったく知らない感覚が、学問の名門に生まれたこの筆者にあるんですね、
丸谷 馬関の春帆楼の三助は、伊藤博文が風呂場の中で前をしっかり押えたのを見て、ああ、この人は生まれが卑しいなあ、と思ったそうです(笑)。
山崎 親父と自分とを比較して、どちらが偉いか点数をつけてみる、その天真燗漫さね。余人が書けばいやらしくなるところが、抜け抜けとしていておもしろいんですな。
丸谷 父親は友達に石川啄木という大詩人をもっている。私のほうは菱山修三と野上彰の二人がいる。二人合わせても人気は石川啄木に及ばないだろう。ここで父親に一点負ける、というのはよかったねえ(笑)。
ぼくだったら、友達二人を出した以上、二人を合わせて啄木と同点になる、いまはともかく将来の文学史的評価はそうなるにちがいない、と、どうしても書いてしまう(笑)。この人は、そういうところ、既成の文学史的評価に非常に忠実な人ですね(笑)。
山崎 わたくしは、これを読んでいて、斎藤茂吉のことを思い出したんです。どちらも東北の比較的貧しい家から東京へ出て来て、東京の中産階級の娘と結婚するんですね。妻は、学者よりも役者のほうが好きだという派手好きの性格をもっている。夫は、野暮天で学問しかない。そのあいだで、家庭はギクシャクしながら、しかし壊れないで、死ぬまでいくわけですよね。これが、日本の近代の家庭が「文化」を備えて行く、ひとつの典型的ケースであって、そこから春彦さんのような二代目が生まれてきたんだな、という妙に感慨深い思いがしました。
丸谷 平野謙さんが日本の小説についていった説で、「女房的文学論」てのがあるんです。たしか、冒頭に引いてあるのは、有島武郎の『或る女』で、この女主人公の葉子は、国木田独歩の別れた細君がモデルでしょう。国木田独歩らしき文学者を、女主人公である細君が冷やかに見るわけです。つまり女房の視点で男を見れば、どんな冷酷無惨なことも書ける。近代日本の小説家はその冷酷無惨さで男を書き続けてきたというんですよ。
山崎 なるほどね。
丸谷 ところが、この本はいわば息子的視点であって、息子の視点に立てば、どんなひどいことでも書けるわけね。親父というものはこれほどつまらない存在になってしまうわけですよ。しかしこの息子は、不幸なことに親父と専門が非常に近い。だから親父の偉大さがわかるから、そういう意味での冷酷さに徹することができなくて、困っていますね。
(次ページに続く)
丸谷 前の日にすんでいたんですね(笑)。
木村 原稿依頼の速達に返事を出して一文を草したところが、それは二年前の郵便で、雑誌はとうに廃刊になっていたという話とか、放送局から春彦さんに出演の依頼があったところが、迎えの車がこない。車が間違えて近くに住んでいる京助先生のほうに迎えに行ってしまったんですね。ところが何と京助先生は、あろうことかその車に乗って放送局へ来てしまう。あとで慌てて春彦さんが行ってみると、ニコニコして待っていて、結局、期せずして父子共演になった。
丸谷 あの父子共演の話、ぼくは、とっても愉快だった。いい話ですね。
木村 また、父親と精神的に関わりのあった七人の女性の話が出てくる。この中には、〈世が世ならば父親と結婚したかもしれない人が数人いることを私は断言する〉などという穏やかならぬ表現もあります。その反面、奥さんというのは、つまり、自分の母親のことですが、学者よりも役者のほうが好きだという人で、悪妻であった。ソクラテスの妻、クサンチッペみたいな存在だったといいます。この著者はかなりクールな感覚をもっていて、父親と母親の姿を客観的に冷静に描いている。
著者は父親をつねにライバルと考えながら、今日まできたようで、最後に、父親と自分の点数づけをやっている。父親はNHKから放送文化賞というものをもらっているけれども〈(私のほうが)NHKへの貢献ははるかに多く、放送回数も断然上回る。この分では、こちらも文化賞とやらをもらえそう〉などと記すところ、相当な神経の持ち主ではないかという気もするわけですが、全体として非常にさわやかな読後感があります。
山崎 やんごとない家の人というのは、われわれ常人のような恥ずかしさという感覚がないんですってね。つまり、人の前で裸になるというようなことは何でもない。
そういう意味の臆面のなさというか、恥ずかしさをまったく知らない感覚が、学問の名門に生まれたこの筆者にあるんですね、
丸谷 馬関の春帆楼の三助は、伊藤博文が風呂場の中で前をしっかり押えたのを見て、ああ、この人は生まれが卑しいなあ、と思ったそうです(笑)。
山崎 親父と自分とを比較して、どちらが偉いか点数をつけてみる、その天真燗漫さね。余人が書けばいやらしくなるところが、抜け抜けとしていておもしろいんですな。
丸谷 父親は友達に石川啄木という大詩人をもっている。私のほうは菱山修三と野上彰の二人がいる。二人合わせても人気は石川啄木に及ばないだろう。ここで父親に一点負ける、というのはよかったねえ(笑)。
ぼくだったら、友達二人を出した以上、二人を合わせて啄木と同点になる、いまはともかく将来の文学史的評価はそうなるにちがいない、と、どうしても書いてしまう(笑)。この人は、そういうところ、既成の文学史的評価に非常に忠実な人ですね(笑)。
山崎 わたくしは、これを読んでいて、斎藤茂吉のことを思い出したんです。どちらも東北の比較的貧しい家から東京へ出て来て、東京の中産階級の娘と結婚するんですね。妻は、学者よりも役者のほうが好きだという派手好きの性格をもっている。夫は、野暮天で学問しかない。そのあいだで、家庭はギクシャクしながら、しかし壊れないで、死ぬまでいくわけですよね。これが、日本の近代の家庭が「文化」を備えて行く、ひとつの典型的ケースであって、そこから春彦さんのような二代目が生まれてきたんだな、という妙に感慨深い思いがしました。
丸谷 平野謙さんが日本の小説についていった説で、「女房的文学論」てのがあるんです。たしか、冒頭に引いてあるのは、有島武郎の『或る女』で、この女主人公の葉子は、国木田独歩の別れた細君がモデルでしょう。国木田独歩らしき文学者を、女主人公である細君が冷やかに見るわけです。つまり女房の視点で男を見れば、どんな冷酷無惨なことも書ける。近代日本の小説家はその冷酷無惨さで男を書き続けてきたというんですよ。
山崎 なるほどね。
丸谷 ところが、この本はいわば息子的視点であって、息子の視点に立てば、どんなひどいことでも書けるわけね。親父というものはこれほどつまらない存在になってしまうわけですよ。しかしこの息子は、不幸なことに親父と専門が非常に近い。だから親父の偉大さがわかるから、そういう意味での冷酷さに徹することができなくて、困っていますね。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする