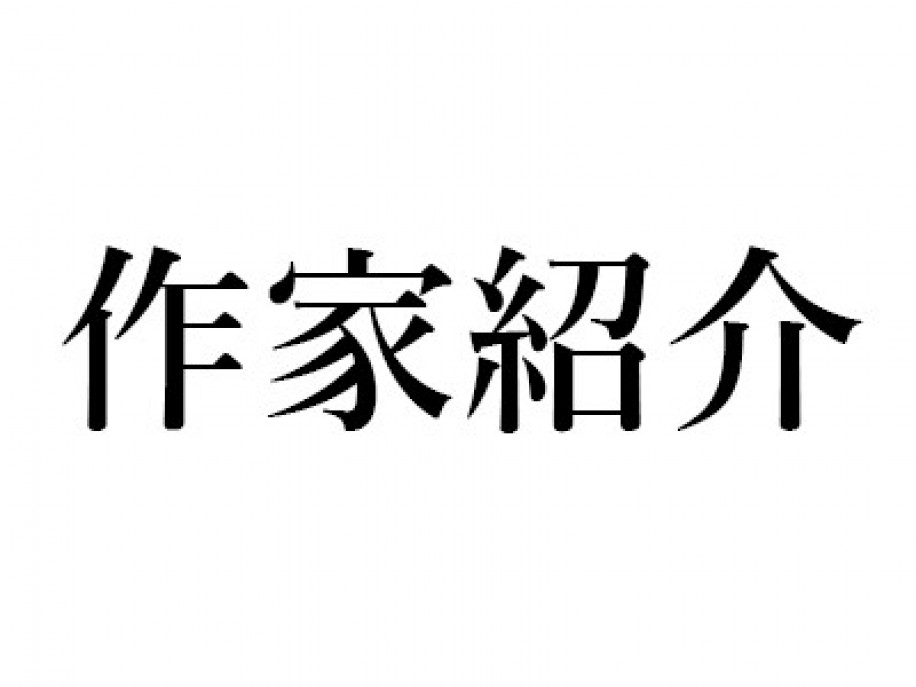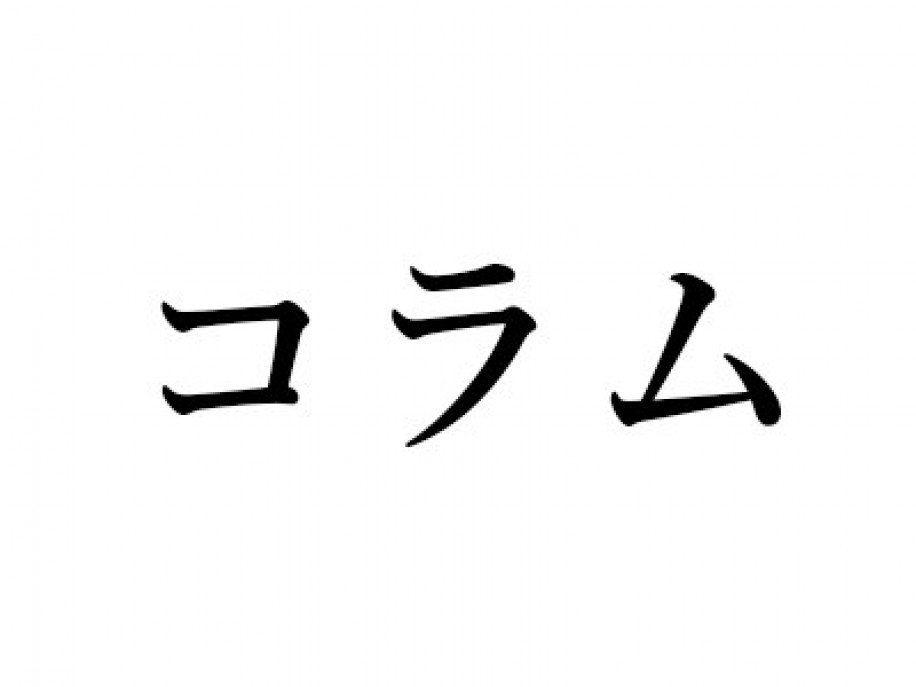読書日記
米原万里「私の読書日記」週刊文春2002年2月28日号|打ちのめされるようなすごい小説『夜の記憶』『心の砕ける音』『笹まくら』
×月×日
そう、丸谷才一の『笹まくら』(新潮文庫)だった。三六年も前に、最近のミステリーで斬新(ざんしん)と讃えられる手法を自在に駆使して書かれていることに改めて驚き、早速Hに電話をする。「クックで書く気無くす前に『笹まくら』で打ちのめされなさい!」「エッ、でも……」とHは明らかに気乗りしない様子である。まだ三十代のHにとって、丸谷の小説といえば『女ざかり』で、これ一作の印象を他の作品にまで敷衍(ふえん)している。ちなみに三十代前半のわが秘書までもがかなりの読書家なのだが、『女ざかり』止まりで、私の世代ではほぼ必読だった『笹まくら』も『たった一人の反乱』も読んでいない。丸谷作品に限ったことではなく、新しい書物を追いかけるのに忙しくて、過去に書かれた名著を顧みない若者が多い、などと嘆く自分の歳を感じて苦笑い。差し当たってHと秘書を口説くためにも、『笹まくら』を読み返すことにした。
太平洋戦争をはさんだ五年間、徴兵を忌避するために実家を捨て学歴を隠し偽名を使って日本各地を、ときには朝鮮半島にまで足をのばして逃げ回った過去を持つ浜田庄吉は、二〇年後の今は某私立大学の職員におさまり、若く美しい妻をめとり、地味で平凡ながら概ね満足な暮らしを送っている。そこへ、逃走中懇(ねんご)ろになり命の恩人ともなった年上の元恋人阿貴子の死亡通知が届く。浜田の心に徴兵忌避者として過ごした過去のシーンがしばしば映し出されるようになる。官憲の目に怯(おびえ)えつつ日銭を稼ぎ、各地を転々と渡り歩いた日々のそれだけでもスリリングな物語を、阿貴子なる女性の正体、彼女との出会いと別れの謎が引っ張っていく。
一方、現在の物語の方もサスペンスに富む。昇進話が持ち上がり、浜田は大学内での派閥間の軋轢(あつれき)に巻き込まれていく。戦後二〇年を経て右傾化してきた日本社会の空気を映して本来の国粋色を出し始めた大学内では浜田の過去を政治的に利用しようとする動きもあり、彼は失職の危機に見舞われる。明確な意図を持つ者は誰一人いないのに、何となくいつのまにか流されるようにして悪意が形成されていく様が言語で表現できてしまうことに驚嘆する。小心翼々として希望と絶望のあいだを揺れ動く浜田の意識は、ますます頻繁に過去と現在を往復する。
その度に薄皮の剥けるようにして(細胞膜並みの薄さで、これに較べるとクックの薄皮は、バナナの皮の厚み)浜田の忌まわしくも輝かしい過去がより鮮明に甦り、現在の日常の閉塞感と矮小(わいしょう)さが浮き立ってくる。などと粗筋を記すのは躊躇(ためら)われるほどに、情景や登場人物たちの微妙な心理の綾やその空気までが伝わってくる。と同時に、国家と個人というマクロな主題が全編を貫いている。徴兵忌避に実際に踏み切る直前まで逡巡(しゅんじゅん)し思索を重ねた浜田が到達した結論「国家の目的は戦争だ」は、世紀を隔てた今も切実に響く。作品全体を通して日本と日本人の戦後が、冷静に穏やかに洞察される。
思いがけない不祥事によって現在の日常が崖っぷちに追い込まれた瞬間、浜田の脳裏を阿貴子と初めて結ばれた日の場面がよぎる。そこは桜の咲き誇る隠岐(おき)。「晴れやかで悲しくて」滑稽で、胸が痛くなるほど美しいラブシーンである。過去に脅かされ続けていた浜田は、ここで初めて過去によって現実から解放される。
書き言葉の日本語は、これほど柔軟で多彩で的確な表現が可能だったのか。丸谷の筆によって描き出される状況も人物たちも、悲惨で深刻であるとともに滑稽で矮小で、作品内の随所で笑わせてくれる。この人間たちの入り組んだ内面に翻弄された後は、ミステリー畑では抜きんでて細やかなはずのクックの文章の肌理(きめ)が可哀想になるぐらいに粗く感じられ、登場人物たちが仰々しく単細胞に見えてくるのだから、罪作りではある。
米原万里全書評1995‐2006。絶筆となった壮絶な闘病記(「私の読書日記」週刊文春)を収録した最初で最後の書評集。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする