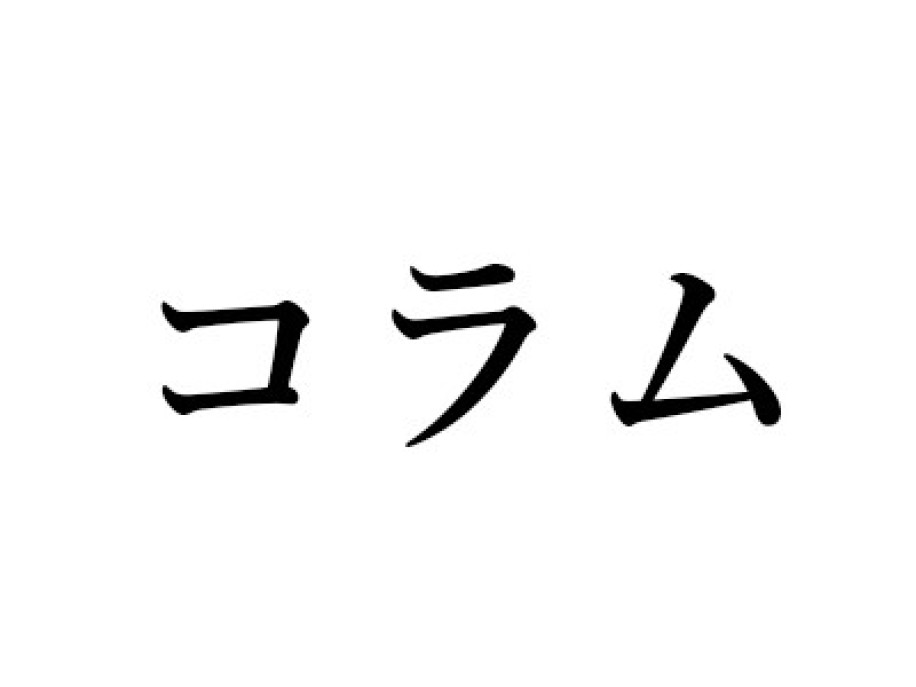解説
『空のオルゴール』(新潮社)
愛を惜しみなく炸裂させ
この、『空のオルゴール』という小説の際立っている点は、いたるところに作者の愛が溢れているという点である。もっとも目につくのは作者の人間に対する愛で、どこにみられるかというと、いろんなところに見られるが、例えば冒頭に、
「しかし何だねえ、自分で選んだ道とはいえ、この人文科学というのは、つくづく厄介なしろものだねえ」
「ひとつの壁をのり越えたと思えば、すぐにまた別の壁が現われてくる。私はときどき思いっきり手打ちうどんを打ちたくなることがあるよ」
という丸尾教授の述懐があり、大抵の人はこれを読んで笑うと思うが、しかしその後、自分が仕事やその他のことで行き詰まったとき、ふと、思いっきり手打ちうどんを打ちたくなってしまっている自分を発見して驚く。
というのはどういうことかというと人間というものはそもそも、むしゃくしゃしたり、行き詰まったりすると手打ちうどんを打ちたくなるものだということである。
ところがこれまでそのことに気がついた小説家はなく、小説家は本来、「五郎は思いっきり手打ちうどんを打ちたいような気分だった」と書くべきところを、「五郎は喚き散らしたいような気分だった」などとしてお茶を濁してきたのである。
ではなぜ、中島らもだけがそのことに気づき、他の小説家はそのことに気がつかないのかというと、中島らもだけが際立って、自分や他人の心の動きを仔細に観察しているからで、つまり、人間への興味、関心が深い、つまり、人間に対する愛が深いということなのである。
しかし、人間愛が深いとはどういうことであろうか。
人間は善いことをするよりも悪いことをしているときの方が楽しいと感じる愚かな生き物で、人間というのは愚行を演じる生き物と定義することもできる。
その人間を愛するというのだから、愚行もまた愛するということになるが、この小説には、そうした人間愛に端を発する愚行愛というものも随所に見られる。
例えば、カリオストロの通夜(つや)の席での警官や奇術師たちの体たらく。
乱酔の挙げ句、普段はその気を意識しない刑事が男色家の手品師と脚をからませて接吻をする。時友は別の刑事と関節技を互いに掛け合った状態で眠ってしまい、翌朝、外そうと思っても外せない。リカは酔ったときの癖で、いつものように全裸になり、警部はその下着を頭にかぶって眠り、翌朝、気がつかないでそのまま二日酔いを治療するために病院に出掛けていってしまうのである。
これらは完全な愚行で、崇高なもの、気高いもの以外は打ち捨てて顧みない人であれば、こんな愚行は土台、描かないし、描いても、見下げる視線で描く。
人間は自ら進んで、或いは、強制的に社会から一定の役割を与えられ、その役柄からなるべく逸脱しないようにして生きている。大きく逸脱すると役をおろされる。会社員が会社のカネを個人的に費(つか)い、それが発覚すれば首になる。
なぜなら、そうしないと社会が成り立たないからである。
小説や映画の世界においてこの傾向はますます顕著で、所詮、ひとりの人間が頭で考えて拵えた作りものの世界だからで、警官は警官らしく、奇術師は奇術師らしく、振る舞わないと、作品は破綻して、その世界やその世界の人間は、読者や観客の頭のなかで像を結ばず、「しょうむない作品や」と言われる。
しかし、警官といえども顔も名前もある人間である以上、人間らしい失敗や愚行を演じているはずで、作者は登場人物を作品世界における役割の側からとらえるのではなく、まず一個の人間としてとらえ、描くことによって作品世界に深みと迫力、現実感を与えることに成功しているのである。
というと、ただ逸脱すればよいのか。だったら、文盲の作家とかシャブ中で凶暴な高級官僚とか、そんなことにすればよいのではないか、という話になるかも知れないが、当然、そうではなく、その逸脱の方向と領域が、誰が聞いても合点の行く、いわばその他人のなかに自分を見いだすことのできるような方向と領域でなければならず、それは実は非常に難しいことなのだけれども作者は人間に対する愛あるまなざしによってそれを成し遂げているのである。
その他にも作中にはさまざまの作者の愛が炸裂しているが、例えば、作者の言語に対する愛というのもいたるところに見受けられる。
時友、リカと奇術師たちが、食後、劇場に出掛ける場面があるが、その席上ですでに酒に酔っていたリカは、
「きれいなお姉ちゃんたちのおろり」
と言う。「踊り」と言うべきところを、酒に酔って呂律が回らなくなり、「おろり」と言ってしまった様をそのままダイレクトに表記してあるのだけれども、小説でこのように音声に忠実な表記をすることは少ない。
なぜかというと、話して理解を得られる言葉をそのまま文章にしても理解を得られないからで、こういう表現を多用すると、「わいしゃがら、手形書いちゃるけ」といった具合に、なにが言いたいのかさっぱり分からなくなるからである。
そんなことは重々分かっているのに、ここをどうしても、「おろり」と書きたかったのは作者の言葉への愛であると私は思う。
このような箇所は他にもあって、例えば、奇術師マミーの妻は、久しぶりに帰還したマミーの頭をフライパンで殴り、
「やかましいわい、この泥亀(どろがめ)」
と罵倒するが、これは当然、人生幸朗生恵幸子の漫才を意識して書かれた台詞(せりふ)であり、ここにあえてこの台詞を使うのは作者の言葉に対する愛であり、範囲を狭めて言えば、大坂語、そして、上方の演芸に対する愛が炸裂している。
そのことに関係して言うと、この作品にはあまりにも説明的な台詞が多いが、これは作者の技術が未熟なためではなく、わざとやっていることで、それは作者のB級というのも勿体(もったい)ない、Z級とも言うべき映画や演劇への愛ゆえで、作者は未熟と思われるのを恐れず、果敢に愛を炸裂させている。
この他に格闘技、ことにプロレスに対する愛があり、また、基調としての酒精愛があって、登場人物はいつも酒を飲んでいるが、この小説には二つの軸があって、ひとつは、アンチ・マジック・アソシエイション、略称、U・M・Aと奇術師たちの闘いであり、もうひとつは、フランソワ師、フーディーニによって、また、『ロベール・ウーダン打ち明け話』という作者の書物への愛がうかがえる書物によって語られる、奇術師ロベール・ウーダンの足跡である。
ロベール・ウーダンのことは文中に詳しいが、とりわけ作者の興味と想像力をかき立てたのは、アルジェリアに赴き、奇術で暴動を鎮圧したというエピソードではないか、と思う。
奇術を別のいい方で言うと手品であり、手品師は、演芸場で紐やカードを弄び、懐から鳩を出したりしている連中のことで、平和的な、闘いや争いからもっとも遠い人たちである。その手品師が、武力で鎮圧すべき暴動を手品でもって平和裡に鎮圧してしまったというのが作者の想像力を刺激したのではないかと思うのである。
この作品のモチーフは殺しあいである。
相容れぬ思想の持ち主を殺そうとする集団と殺された仲間のために復讐をする集団の血みどろの争いである。
普通にやれば陰惨な物語になるに決っている。
しかし、作者は自らの愛を惜しみなく炸裂させ、そんな陰惨な話を、かく愉快な物語として著わすことに成功した。
この作品そのものが中島らもの奇術なのである。
【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする