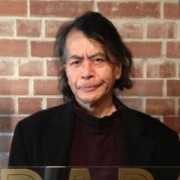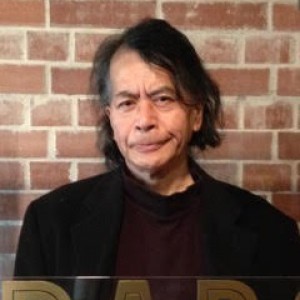前書き
『ブック・カーニヴァル』(自由國民社)
ずい分いろいろ「暗躍」した。きみ、あなたの知ってる(あるいは知らない)企画や特集雑誌のかなりのものがぼくのこのみすぼらしい机の上の小さな思いつきからうまれたのだが、そうした事情も少しは伺えるようになっている。それぞれの文章に、そこで扱った問題の「その後」をめぐって加筆しようかと思わないでもないが、若干の明らかな誤りを訂正するくらいで、一切やめておく。切りがないし、「その時点」ということに自分なりにも愛着があるからだ。
この十年で、近代西欧に関して自分なりに物差しをつくる作業は終了した(す、すっごいこと、言うすね!)。何を見ても一応は切れる。その切れ方にも自分なりに、もう、いいよというデジャ・ヴュ感覚で、飽きてきた。もう十年、許されて永らえ得るものなら、少し、ちがったテーマ系列を組み立ててみたい。あるいは、もはや「文化史」「表象論」などという益体もないもの自体にも、飽きた。
公私ともさまざまなけじめがあったし、とにかく一度全部吐きだす。よほど小さなコラムで選択のスクリーンにかからなかったものを除いて、ほぼこの十四センチで全部である。その中で、書物と、そうした書物のつくる新しい意味の宇宙を論じたものが、この高山宏の『ブック・力ーニヴァル』にすべてそれぞれの所を得て、おさまっている。これらすべてを読み通す最初の読者ともなった初出媒体の編集者諸兄諸姉のアレンジメントなければ、到底不可能であった。感謝あるのみだ。
*
ぼくの書斎は、たまたま訪れてきた若い人をいたく失望させる。学者というものをよく分かってくれたまたとない妻をさえ嘆かせるほど稼ぎをことごとく注ぎこんだ本も、「用」が済めばあちこちの図書館にあげ、友人知己にあげ、売りとばし、要するに愛書家でも、蔵書家でもない。だから、その時々のぼくの関心というか脳の構造を映す何百冊かの本が(それなりの秩序で)そこいらにころがっているだけ。美酒もなければ、いわゆる稀覯本のたぐいも一冊もない。「お書斎を」と言って訪ねてくる人たちは、その辺にがっかりして、はっきりそう言う。荒涼が身についている。どうもすいませんねえ。
ボルヘスの「砂の本」という観念が好きだ。あるいは種村季弘「愚者の旅」の、沙漠行く放浪の民のポータブル図書館がタロット・カードではなかったかという話。一瞬、見る人間を啓発し、役が了われば、習々と吹きたわむれる風に散らされていく、そういう知識。カルヴィーノの『見えない都市』も、そうではないか。
万巻の本を読んだ人に限って、そういういやみを言うもんですよ、と言われる。そうかも知れない。団塊知識戦士は疲れた。走りながら、荒俣宏と同じで、解体にあこがれる。あこがれながら、走る。
こうして、一挙にまとめることで、ぼくはぼくを清算する。この彪大な知識の幻影は新たな風にのって、きみ、あなたの机の上に姿を現わす。ぼく自身持たないぼくを、きみ、あなたは持つ。それを快楽の時だと感じていただければ、幸せなのだ。
自分も勉強しなきゃ、とかつまらぬことを考えるなら、きみは多分不幸になるだろう。幸せな家庭、目と体の健康、すべてを犠牲にする愚かな道に迷いこむことになるよ。現に、このぼくがそうだもの。
ぼくは人に会うことが好きだ、これらの本が記しとどめたものの何十倍もの知識が、そうした人たちの出会いでやりとりされたから。老若男女は、関係ない。その人たちの「肉声」もこの本は記録する。
でも、やっぱり年老いた。疲れた。会いに行くまでが、そして帰路がつらくなった。
幻影にしかすぎないが、この本を通して、きみ、あなたは、きっと一度は会っておいてよかったと思う一人の人間の輪郭に会うことができたことになる。
それでいい。カーニヴァルの真の価値は、狂奮のあとの幻影だ。たしかに、出会った。それでいい。
この十年で、近代西欧に関して自分なりに物差しをつくる作業は終了した(す、すっごいこと、言うすね!)。何を見ても一応は切れる。その切れ方にも自分なりに、もう、いいよというデジャ・ヴュ感覚で、飽きてきた。もう十年、許されて永らえ得るものなら、少し、ちがったテーマ系列を組み立ててみたい。あるいは、もはや「文化史」「表象論」などという益体もないもの自体にも、飽きた。
公私ともさまざまなけじめがあったし、とにかく一度全部吐きだす。よほど小さなコラムで選択のスクリーンにかからなかったものを除いて、ほぼこの十四センチで全部である。その中で、書物と、そうした書物のつくる新しい意味の宇宙を論じたものが、この高山宏の『ブック・力ーニヴァル』にすべてそれぞれの所を得て、おさまっている。これらすべてを読み通す最初の読者ともなった初出媒体の編集者諸兄諸姉のアレンジメントなければ、到底不可能であった。感謝あるのみだ。
*
ぼくの書斎は、たまたま訪れてきた若い人をいたく失望させる。学者というものをよく分かってくれたまたとない妻をさえ嘆かせるほど稼ぎをことごとく注ぎこんだ本も、「用」が済めばあちこちの図書館にあげ、友人知己にあげ、売りとばし、要するに愛書家でも、蔵書家でもない。だから、その時々のぼくの関心というか脳の構造を映す何百冊かの本が(それなりの秩序で)そこいらにころがっているだけ。美酒もなければ、いわゆる稀覯本のたぐいも一冊もない。「お書斎を」と言って訪ねてくる人たちは、その辺にがっかりして、はっきりそう言う。荒涼が身についている。どうもすいませんねえ。
ボルヘスの「砂の本」という観念が好きだ。あるいは種村季弘「愚者の旅」の、沙漠行く放浪の民のポータブル図書館がタロット・カードではなかったかという話。一瞬、見る人間を啓発し、役が了われば、習々と吹きたわむれる風に散らされていく、そういう知識。カルヴィーノの『見えない都市』も、そうではないか。
万巻の本を読んだ人に限って、そういういやみを言うもんですよ、と言われる。そうかも知れない。団塊知識戦士は疲れた。走りながら、荒俣宏と同じで、解体にあこがれる。あこがれながら、走る。
こうして、一挙にまとめることで、ぼくはぼくを清算する。この彪大な知識の幻影は新たな風にのって、きみ、あなたの机の上に姿を現わす。ぼく自身持たないぼくを、きみ、あなたは持つ。それを快楽の時だと感じていただければ、幸せなのだ。
自分も勉強しなきゃ、とかつまらぬことを考えるなら、きみは多分不幸になるだろう。幸せな家庭、目と体の健康、すべてを犠牲にする愚かな道に迷いこむことになるよ。現に、このぼくがそうだもの。
ぼくは人に会うことが好きだ、これらの本が記しとどめたものの何十倍もの知識が、そうした人たちの出会いでやりとりされたから。老若男女は、関係ない。その人たちの「肉声」もこの本は記録する。
でも、やっぱり年老いた。疲れた。会いに行くまでが、そして帰路がつらくなった。
幻影にしかすぎないが、この本を通して、きみ、あなたは、きっと一度は会っておいてよかったと思う一人の人間の輪郭に会うことができたことになる。
それでいい。カーニヴァルの真の価値は、狂奮のあとの幻影だ。たしかに、出会った。それでいい。
ALL REVIEWSをフォローする