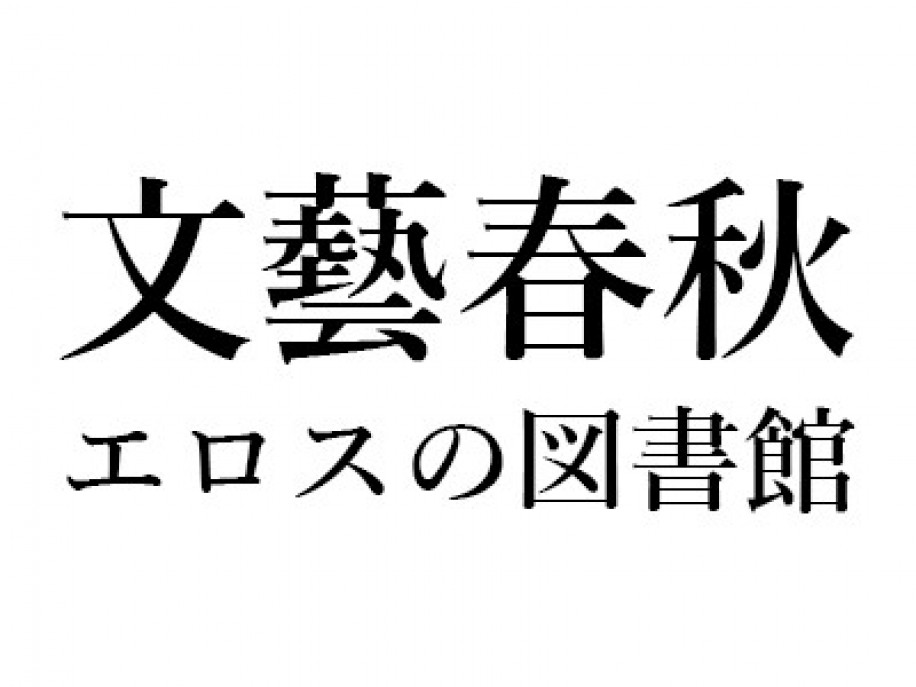書評
『江戸の身体を開く』(作品社)
「切って知る」オランダの知
タイモン・スクリーチの『江戸の身体(からだ)を開く』(高山宏訳、作品社、一九九七)は、刺戟的な比較文化論だ。比較の二項はオランダと日本。主眼は日本にある。日本がオランダという西洋の最先端の知に触れた江戸後期が舞台である。具体的には、『解体新書』の刊行された一七七四年という年がメルクマールとなる。江戸の人々は、このとき、オランダの知が「切って知る」ことであることに衝撃を受けたというのである。『解体新書』に象徴される蘭学とは何であったか。著者はこう書いている。「蘭学とは要するに、困難にもめげずに事物を開くことが、そして……事物を開くことで『内』を見、『内』にあるものに対処することがいかに重要かを言う知的主張の謂に他ならなかった」。
スヴェトラーナ・アルパースは、その『描写の芸術』(一九八三)において、十七世紀オランダの絵画、とりわけ静物画が「内部への文化的衝迫」とでもいうべきものによって突き動かされている次第を論じたが、著者の論述にアルパースの議論は色濃く影を落としている。オランダの静物画では、果物は皮を剥かれ、あるいは刃を入れられ、ティーカップは転がって内側を見せ、牡蠣(かき)は殻をこじあけられている。風俗(ジャンル)画でも窓や扉や戸棚は開いている。そこでは「内へ向かう視線(インテリア・ヴィジョン)の価値」こそが称揚されているのだ。
日本にはこの「内へ向かう視線」が端的に医学の姿をとって上陸した。「切る医者」が登場したのだ。身体を切る、切って内を見るという思想が日本にはなかった。だから「切る医者」という概念の衝撃は、脱領域的に思考を横断していくことになったというのである。
「日本人そのものは対象の全体性(ホーリズム)を以て物事を考える族」というのが、著者の基本的な見方である。「身体に対する解剖学的(アナトミカル)な読み」をこととする蘭方には、「全体的(ホリスティック)な読み」をこととする漢方が対立することになるだろう。蘭方vs漢方というのは、しかしひとつの典型的対立にすぎない。同様の比較対照が「脱領域的に」確認されるはずである。
まずは解剖図において。西洋の解剖図に描かれる男はすべて筋肉隆々たる胸板をしており、女はすべてたおやかな太腿をもっているという具合に、そこには客観性・美化への志向があって、個が一般的なものへと昇華されている。ところが、日本の絵では、いつ、だれがということへの関心が強く、しかも解剖の実践行為を最初から最後まで追うというかたちをとっている。「紙上解剖のふしぎな時空」と著者はいう。
解剖しつくした挙句、残るのが骸骨である。しかし、西洋では骸骨がはかない肉身のうちに住む「永遠の実体」というふうに考えられることが多かったのに対し、日本では骨が身体の他の部分より長持ちするわけではなく、同じようにむなしいものと見られていたことを著者は指摘する。「ヨーロッパとは対照的に、骸骨は日本では身体(パーソン)の絶対性のメタファーとはなりえなかった」。日本に実体的な骸骨の幽霊などが登場するのは十八世紀末以降のことである。
比較は医学や解剖にとどまらない。料理において対照はもっと際立つ。西洋人の肉食は、あらゆる外の部分を棄てて内部を内部に取りこむ行為である。ある動物の内が別の動物の内になるわけである。肉食は食物連鎖を「内」に保つ装置である。対するに菜食は、食する相手の外側を残す。日本料理においては、食材はその元の状態のままで食される。目に見える外部が取りこまれるのだ。料理人たちの切り方も違う。「オランダ人の刃の入れ方が人工的で、肉を切り開いて内部を出し、普通は見えない部分をさらけ出させるのに対し、日本の料理人たちは自然の線に沿って切っている」。
著者のこうした観察は、抽象的思弁ではない。おびただしい図版が援用されている。大変な視覚資料である。しかしやはりただ見ていただけでは、こういう論述は出てこない。比較のポイントというものを冷静に用意しておかなくてはならない。ポイントは、外と内といってもいいし、全体と部分といってもいい。行為としては「切る」「切り開く」というその一点である。
興味深い指摘がいろいろある。たとえば、「刀を佩いての性行為において、ペニスと同じ向きを向くのは柄であって、剣先ではなかった」というような。春画においても、「内」はさらけ出されないということか。
十八世紀末以降、しかし日本も変わり始めるだろう。「旅行者は風景の解剖学者(アナトミスト)になる」と著者はいう。「蘭方医がどこでも切ろうとするように、江戸後期の旅はいろいろな所へ行った」と。風景と身体、地図と解剖図との重ね合わせの視点から出てくる指摘である。
だが、本書において蘭学以降の、『解体新書』以降の問題についての記述は少ない。オランダと日本の比較対照に焦点が絞られているからだが、著者は結論的にこう書いている。「開くことの知は日本では大きな力とはならなかった。……オランダでは内部に向かう凝視が必ずやリアリティに向かう眼差しであったのに比して、日本ではそれはせいぜい何か一時的な状態をあばき見せることにすぎず、内部を見るといっても究極の真理ではなく、内部のもう一枚の積層を見ているだけという、ラッキョウの皮むき的な感覚が強かった」と。
私が本書の内容に特に惹かれたのは、実は私自身、外部の礼讃ともいうべき二冊の著書(『鏡と皮膚』『文学の皮膚』)を上梓しており、問題意識において交叉するところがあったからである。私は、外と内とか、表と裏とか、ホンネとタテマエとか、そういったいかにも日本的(と思われる)二元論を解体したいと考えていた。ところが著者によれば、外とか全体とかの尊重は日本的なものであるという。日本人の「内」への信仰は相当強いと私は思うけれども、だとすればそれは近代(明治)以降の問題なのだろうか。むしろ「切る」ことなしに「内」を言挙げすることをどう考えるべきか。本書は、そういった問題に取りくむ上でも必読の一冊というべきだろう。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア

國文學(終刊) 1998年9月号
ALL REVIEWSをフォローする