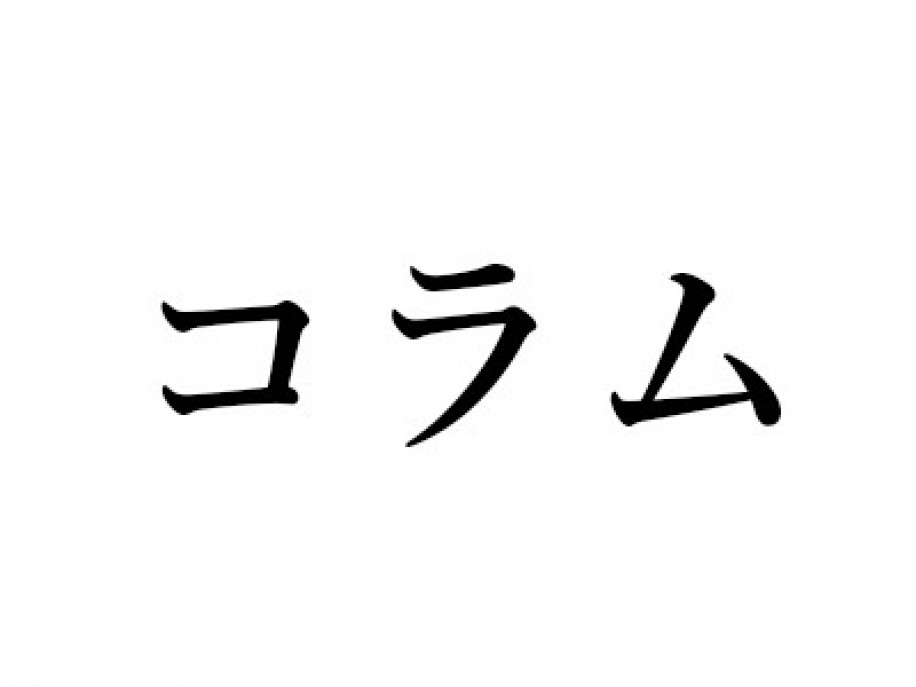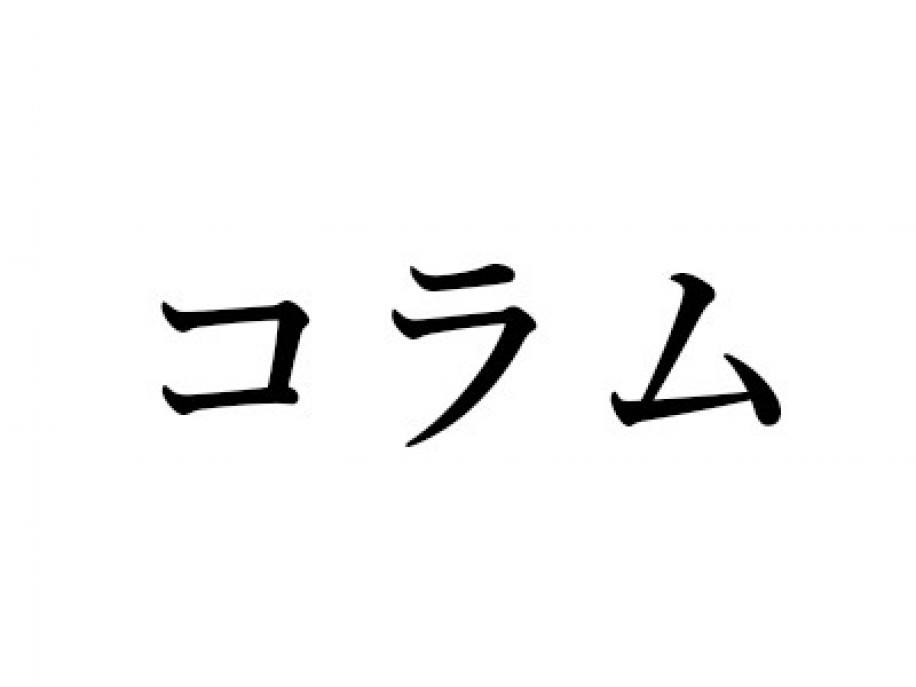解説
『鴎外の坂』(新潮社)
明治の男はつらかった
明治の男はつらかったと思う。鎌倉時代から数百年にわたって培われてきた武士道の美学と倫理、つまり禁欲と痩せ我慢があらゆる行動の指針になっているにもかかわらず、時代は確実に、金銭と欲望だけが支配する資本主義の方に進みつつあったからだ。つまり、いかにすれば、男子としての品位を汚さず、家族を養うだけの金銭を手に入れ、それでいながら、忠・孝・恩という儒教的モラルを侵犯せずに、おのれの感情に正直でいられるのか? 悩みはつきなかったにちがいない。
だが、そのつらさから、世界でも類を見ない文学が生まれた。それが漱石の文学であり、鴎外の文学である。とりわけ、一家の長男として、のちには家長として、ありとあらゆるしがらみの中で格闘しながら、文学を生み出していった鴎外のつらさは、また格別だっただろう。まさに、それは「しがらみ草紙」というほかない文学だった。
したがって、鴎外の伝記や研究書のほとんどは、この「しがらみ」を解くことにその努力の大半を傾注する。しかし、「しがらみ」が「しがらみ」であるゆえんは、どこか一か所をスッキリさせようとすると、他の箇所でしがらみの紛糾がいっそうひどくなることにある。だから、どんなによくできた鴎外の評伝や伝記でも、ある部分が明快であればあるほど、他の部分の混迷が深まるのが常である。
その原因ははっきりしている。「しがらみ」の中心である鴎外その人に焦点を当てようとするからだ。「しがらみ」となる肉親たちへの鴎外の視線を分析しようとすると、どうしても、他の「しがらみ」への視線が抜け落ちる。これは仕方のないことかもしれないが、それでも単純化、類型化のそしりを免れない。
これに対して、著者が取った方法はまったく違う。「鴎外その人を描くよりも、鴎外の側にいた、共に暮した家族に光を当てることによって、鴎外にも反射させようと考えた」のである。つまり、鴎外にとっての「しがらみたち」のほうに焦点を当てて、その「しがらみたち」が鴎外へ送る視線を分析することで、総合的に「家族の記憶の中にある『微笑する鴎外』」を浮かび上がらせるというのである。
この方法が見事に成功している。だが、これは思ったよりもはるかに難しい方法である。なぜなら、「しがらみたち」の側から描くといっても、その「しがらみたち」というのは、たいていが非表現者であるからだ。非表現者として一生を終わった人たちの内面に入り込んで、彼らをして語らしむるとなったら、最もたやすいのは「小説」を書くことだが、著者としてはこの道は取りたくない。ではどうするのか?
著者が採用した書き方は、鴎外のそれである。つまり、鴎外が非表現者たちの生涯を描こうとしたときに用いた方法、たとえば『渋江抽斎』のような史伝で使った「掃苔(そうたい)小説」とよく似たものだ。まず第一に来るのは、自分と同じような境遇にあった非表現者の対象に対する敬慕の念と親愛の情。次は、その対象に関する「書を集め、子孫の現在をたしかめ、墓を探す」こと。そして「戒名と忌日から家系をたどってゆく」という方法。そのさい「『敬慕』『親愛』していた人物の事蹟(じせき)や生活のみならず、筆は周辺の人々、子孫にまで及ぶ」ことになる。このとき、忘れてはならないのは、その周辺の人々や子孫が親しんできた土地感覚への目配りだ、「『渋江抽斎』はいわば本郷・下谷(しもや)の地霊が呼び出した物語なのである」
と、ここまで書けば、慧眼なる読者にはもうおわかりのことと思うが、これは、鴎外について書くずっと以前から著者が地域雑誌『谷中・根津・千駄木』、通称『谷・根・千』で採っていた方法、すなわち、ある特定人物に関係した地域を徹底的に歩き回り、その歴史的背景を調べた上で、土地の古老から聞き書きをして、その人物のイメージをふくらませてゆく方法とよく似ているのである。違うのは、著者が鴎外の住んだ地域の雑誌を編集するさいに「無意識」に用いていた方法を、今度は多分に「意識的」に鴎外のそれに重ね合わせ、鴎外にとっての「しがらみ」となっていた肉親の人々に接近していったことだ。
それが「意識的」であることの宣言は、「プロローグ『青年』が歩く」で、鴎外が考案し『青年』で小泉純一に持たせた東京方眼図を、著者自らが携えて、小泉純一の歩いたあとをたどりなおすときに、つぎのような形で表現される。
鴎外はたしかに「竿(さを)と紐尺(ひもじゃく)とを持つて測地師が土地を測るやう」に小説を書いている。風景の叙情的な形容は少なく、地名や地理関係が重視され、文章にリズムを与えている。歩いてみるといちいちの符合に驚く。鴎外はなぜ、これほどの小説の舞台を正確につくり、何の変形も虚構も加えなかったのだろうか
ようするに、著者は『青年』の小泉純一の視点を借りて描き出された谷中・根津・千駄木の風景が、見たままの風景の羅列ではなく、鴎外自身に関係した肉親や知己・親類の住んでいた家を周到に配置した「しがらみの方眼図」であることを見抜いて、そこから個人史探偵としての疑問を育ててゆくのである。「意識的である」とは、探偵の視点を採用したことの表明である。
やがて、この探偵は、『青年』にわざわざ「色川国士邸」と固有名詞で記されている人名に興味を持つ。すると、その人物の子供だった協和銀行名誉会長色部義明氏から手紙が届く。なんと、この人の父、すなわち色部庸男(つねお)氏は、海軍中将赤松則良(のりよし)氏の四男、ということは鴎外の最初の妻の赤松登志子の弟だから、鴎外の義弟に当たるのである。
これは、ほんの一例だが、地霊を信じ、聞き書きの有効性を確信する著者のもとには、「書を集め、子孫の現在をたしかめ、墓を探す」鴎外と同じように、次々と、こうした思いがけない僥倖(ぎょうこう)が訪れ、非表現者であったはずの「しがらみたち」のイメージが次第に明らかになり、陰影をましてゆくのである。
その結果、これまで鴎外の関係者の残した記録では、ほぼ抹殺されていた「無縁坂の女」、鴎外が最初の妻赤松登志子と離婚してから第二の妻荒木しげと再婚するまでの九~十年間に、鴎外に奉仕するため、森家に「妾奉公」していた児玉せきの面影が、歴史の闇の中からあらわれてくる。そして、名作『雁』のヒロインお玉は、児玉せきの印象を色濃く残していた女性であり、妾を囲う末造は鴎外その人だったという事実が判明する。
こうしてみると鴎外は常に末造の立場に身を置いている。岡田など大して心理は書き込まれていないが、小説をていねいに読むと、末造だけには詳細な心理描写がある
そして、この場合もまた聞き書きが大きな威力を発揮する。昭和十六年まで生きていた児玉せきを知っている人物がいたのである。鴎外の末っ子類と学友で、しばしば鴎外邸に遊びに行ったMさんである。
その時分、せきさんはもういいかげん腰のまがったお婆さんでしたが、子供の僕に根掘り葉掘り、鴎外邸の中の様子や、鴎外さんのことを聞くんですよ
前妻と後妻、そして、そのどちらとも折り合わなかった母、この三本の「しがらみ」の中にあって、フィクションの中にだけしか登場を許されず、鴎外から「しがらみ」とも意識されなかった児玉せきが鴎外に向ける視線の切なさを、この証言の中に読み取ることは可能だろう。もちろん、児玉せきに対する著者自身の共感の視線も。
対象が作家であれ誰であれ、あまりプライバシーに踏み込むのは私の好むところではない。(中略)しかし、これまで児玉せきについて書かれた文章にはやはり相当の異和感を感じる。これは一種の鎮魂歌と思って許していただきたい。私は児玉せきが好きなのである
本書に一貫して脈打っているのが、この「好きだ」という感情である。これまで、鴎外という人物のくっきりとしたイメージを抽出するために、あるいは希代の悪妻として、あるいは影の薄い不美人の妻として、はたまた権力欲の強い教育ママとして、それぞれ強いコントラストで描かれていた「しがらみたち」に対して、同性として感情移入しつつ、かといって、決して、その人物の視点から鴎外を裁断しようとしないこと、これが本書を読後感の爽やかなものにしているのである。
彼女たちの抱えた問題は私の問題である。しかし、それによって現時点から鴎外を断罪しようというつもりもない
「しがらみたち」の間で苦闘する鴎外、だが、著者によって描き出されたその苦しむ鴎外にはなんという「優しさ」が満ちていることか。
たしかに明治の男はつらかったろうが、そのつらさを耐えることによって生まれた「優しさ」もまた確実に存在したのである。
一人の人を描くことで一つの時代をも描き切った真の傑作と呼んでいい。
【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする