書評
『悪の哲学ノート』(岩波書店)
題名から、悪についての徹底した哲学的考察を期待した読者は肩すかしを喰うだろう。本書はあくまでも「ノート」なのだ。著者は、悪と関係のありそうな著作を渡り歩く。いったい著者自身はどう考えているのと幾度も尋ねたくなったが、最後まで答えは見えてこない。
西田幾太郎をはじめ、善についての研究は山ほどあるが、悪の研究は少ない。これが本書を思いついた動機だと、著者は言う。たしかに日本人は、悪を考えるのが苦手だ。着眼は悪くない。だがそれにしては、悪を哲学するための道具だてが不足している。
正統の西欧哲学は、悪を「善の欠如」と規定してきた。いっぽう著者は、悪を「存在の過剰」と考えるグノーシス派や、ヨハネ黙示録を反キリスト的テキストと考えるD・H・ロレンスをヒントにする。
本書の前半はこうした道具だての紹介であるが、後半はドストエフスキーの小説に話がとぶ。このつながりがよくわからない。『悪霊』をはじめとする作品に、黙示録の寓意がちりばめられているというのが著者の指摘だが、「悪の哲学」はほとんど展開されておらず、小説のプロット紹介が大部分のページを占めている。
「悪」をとりあえずの行き先にした、哲学散歩、文学散歩として、本書を楽しむ読者もいるのだろう。あいにく私はそんなに暇でない。続編を考えているという著者には、ずばり悪の核心を突く展開をこそ期待したい。
【この書評が収録されている書籍】
西田幾太郎をはじめ、善についての研究は山ほどあるが、悪の研究は少ない。これが本書を思いついた動機だと、著者は言う。たしかに日本人は、悪を考えるのが苦手だ。着眼は悪くない。だがそれにしては、悪を哲学するための道具だてが不足している。
正統の西欧哲学は、悪を「善の欠如」と規定してきた。いっぽう著者は、悪を「存在の過剰」と考えるグノーシス派や、ヨハネ黙示録を反キリスト的テキストと考えるD・H・ロレンスをヒントにする。
本書の前半はこうした道具だての紹介であるが、後半はドストエフスキーの小説に話がとぶ。このつながりがよくわからない。『悪霊』をはじめとする作品に、黙示録の寓意がちりばめられているというのが著者の指摘だが、「悪の哲学」はほとんど展開されておらず、小説のプロット紹介が大部分のページを占めている。
「悪」をとりあえずの行き先にした、哲学散歩、文学散歩として、本書を楽しむ読者もいるのだろう。あいにく私はそんなに暇でない。続編を考えているという著者には、ずばり悪の核心を突く展開をこそ期待したい。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
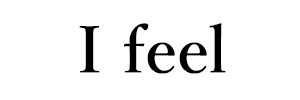
I feel(終刊) 1995年3月
ALL REVIEWSをフォローする







































