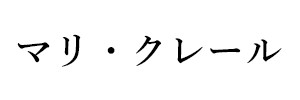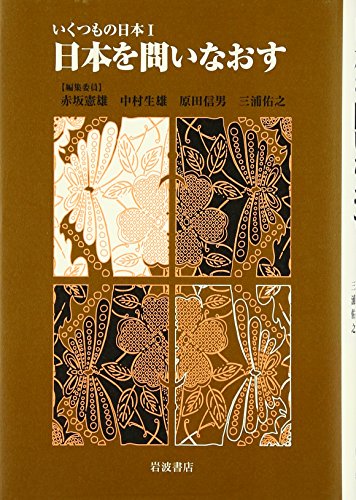書評
『精神の生態学』(新思索社)
射撃場があって、向うには同心円を描いたマトがあり、真ん中にあたれば五点、いちばん外側にあたれば一点になっている。こちらから狙ってできるかぎり中心を射あてるようにして、どれだけ高得点がとれるか。これがわたしたちが手慣れている学習・研究・調査・解剖のやり方だ。ベイトソンがこの本でとっているやり方はまったくちがう。草原のなかで自然なまま動きまわっている獲物を、こちらもまた動きまわりながら狙って射っているようなダイナミックな迫力を感じさせる。何とあらっぽいことをするもんだ、どうして獲物が静止した瞬間を狙わないのか、いったいつづまりがつくものか、ほんとうにマトに当たるんだろうか、この本はそんな危惧とスリルを最後まで発散しつづける。しかし兎に角やってしまおうとして、何も術がなくて途方にくれそうなところから、何とか手がかりや足場を作り、形を整えていって、こういうやり方をすれば何とかなるのだと納得させるところまでもっていってしまう。この溌剌としたベイトソンのガンさばきは、射撃場内の名手しか知らないわたしたちに、奇想天外な衝撃をあたえる。この本の著者ベイトソンは、落ちこぼれ、劣等生タイプが、形からはみ出しながらどれだけやれるか、それが天道まで達してしまうと何が出来上ってしまうかを鮮やかに示しているお手本だとおもう。もしつづまりがつかなかったら何の意味もない無駄骨おりになってしまう。そんな冒険にのりだして兎に角最後までやってしまったという印象が、この本から受けた最大の新鮮な驚きだった。兎に角やっちゃうんだからねえ。これはアメリカの学問と本の良さだ。
ましてこの本の主題は、眼に視えないが、いつも環境の状態に応じて刻々に変化している「精神」という獲物を、できるかぎり背景の野に放ちながら、狙いを定め、射止めなくてはならないし、射止める方の「精神」が刻々に位置と場所を変えているところも記述しなくてはならない。どこに緒口を見つけてゆけば、よいのか。ベイトソンのやり方の特徴をいくつか挙げてみる。
まず動いている個々の生命体や精神体と、それをそうあらせている社会的な、また生態的な構成体を、切り離せない生きたひとつのシステムと見做している。つまり「わたし」という狩人が動きながら、おなじく草原のなかで動いている獲物を狙って、これを仕止めようとしているという図解の仕方をやめて、「わたし」のように動いている狩人も、それに追われておなじく避難するため動いている獲物も、その動くふたつを乗せている草原という環境も、切り離せないひとつの生きたシステムとみて、そのシステムの要素が変化するために刻々にシステムの構図が変化しているという見方をするのだ。人間の精神を包含したこのシステムをひとつの生物的なシステムとかんがえれば、このシステムは個々の要素の変化によって、刻々に変化する第一次変化だけでなく、できるかぎり外界との適応をよくし、試行錯誤を減らすためにフィードバック回路をもっていると同時に、第二次的な変化の統御装置のレベルをもち、これで逐次に次元の高いところから統御するひとつの階程的なヒエラルキーをつくっていると見做される。たとえばわたしたちが習慣とか習俗とか慣例とか呼んでいるものは、試行錯誤の不経済性を減らして適応をよくするための、硬く強い統御のレベルを意味している。そしてベイトソンが採用している前提によれば、適応を強化し試行錯誤を少なくするための統御の層がつくるヒエラルキーは、ラッセルの数学基礎論のいう意味での「論理階型」の性質をもつものとされる。たとえばひとつの「クラス」はそれ自体のメンバーから除外されるし、「クラスのクラス」はそのレベルのメンバーである「クラスのメンバー」からは除外される。もっとこの「クラス」を現実の事物に近づけてゆくと「湯気のたちのぼる料理」とその料理の名前を指し記した「メニューの紙きれ」とは「論理階型」のレベルがまったくちがうから、混同されてはならないことになる。
いま学習ということについて、わたしたちの生物的なヒエラルキーが、どんな論理階型に従うかを調べてみる。ベイトソンの挙げている例でいえば「工場のサイレンから、いま正午だということ」が分かる(learn)。このばあいの学習はサイレンが鳴ったという出来ごとから、単純に直接に情報を受信して、正午だということを学んだということだから「ゼロ学習」ともいうべきものだ。でもつぎにサイレンが鳴り、その都度、いま正午だと識知することが繰返されるようになったときは、単なる情報の受信ではなく、受信の受信ともいうべき方向づけが、受信のなかに這入りこんでくる。これはもう「ゼロ学習」ではなく「学習」Iともいうべき論理階型に包括されるといっていい。ところでつぎに断続音の単位長さが異った二つのサイレンを正午に鳴らしたとする。どちらも正午を告げることを、充分に学習(学習I)した後に、二つのサイレンの単位長さを、両方ともその中間の長さに近づけてゆく。そして二つのサイレンの相違を無くすようにして接近させてゆくと、学習するものに精神的な混乱が起る。この状態の学習を学習IIとすれば、これは分裂病者の認知のなかにおこるダブル・バインドの状態の原型といってよい。ベイトソンは、わたしたちの現実の世界は、この学習IIに関わるような現象で満ちみちていると述べている。
ベイトソンによれば、個々の人間の「性格」とかんがえられているもの、たとえばあの人は勝ち気だ、お調子者だ、気むずかしい、大胆だ、臆病だ、ひょうきんだ……といった形容の言葉でいわれるものは、みな学習IIのレベルにある状態を記述する言葉だ。けれど「性格」というものをよく考察し、こういう形容で語られるような反応の変化(学習II)が固定するようになる過程は、学習Iの状態がひとつのコンテクストに沿って進んでいった結果なのだから、そうなる反応の固定化の方向性をつかまえなくてはならない。たとえば「宿命観」の強い人というのは、その人の振舞い方を含む生体システムのなかで、その人と環境とのあいだのやりとりがゼロ学習の次元で繰返されたために固定化された人だということができる。
ベイトソンは学習IIがいちばん露わにあらわれる例として、フロイト派の精神分析療法の例をもってくる。診察室にきた患者は相手のセラピストが過去に親がじぶんに接したとおなじやり方で接してくれるように、無意識的に要望し、セラピストとのやりとりをかつて親(母)とのやりとりの学習IIとおなじように鋳型しようとする。これは乳幼児期に行われ、いまは無意識になって身についているものだ。この学習IIは正しいか間違っているかとは何のかかわりもない、あるひとつの「見方」や「振舞い方」として身についている。じぶんの行動を成就させることで、身につく度合を強化しようとして、目的が不成功におわっても、べつに打撃をこうむったり、挫折感をもったりするわけではない。それは「目的」の前提となる精神の状態と、なまの物質的な事実とは、「論理階型」の次元がちがうから、矛盾が起っても具体的な経験としては示されることはないからだ。過去の乳幼児のとき無意識になされた学習IIは、たえず自分をそこに落着かせるように作用するから、一度学習がなされると根本から消し去ることはほとんど不可能になる。それが成人の事象へのかかわり方が、フロイト学派のいうように、乳幼児のときに根をもつことの、ベイトソンによる理解の仕方ということになる。
ところでベイトソンは、学習IIについての学習(つまり学習IIIの段階)を実現することは可能だとみなしている。わたしたちがベイトソンのやり方、考え方を究極のところまでもっていって検討しようとすると、ベイトソンは学習IIIとその結果について語らざるを得なくなってゆくようにみえる。
まず、(1)学習IIのレベルにある行動を習慣にまで固定化し、パターン化するのを助け、スムーズに進行させる能力を身につけるようにする。また、(2)同時に学習IIIを成就したときに学習IIIから抜け出せるような通路を、開いたり塞いだり自在にできるような能力を獲得するように修練する。また、(3)無意識に学習IIのレベルにあることを実行することができ、また実行しながらそれを客体視できるように修練する。こういったことはすべて学習IIIのレベルに属している。この学習IIIが身についたとして、それは学習IIを強化する方向にもゆくが、また学習IIを制限し、抑圧する方向にもゆくことができる。だから学習IIIに属することを身につけることは、いいことなのか悪いことなのかにわかに断定することはできない。ただ学習IIで得られたものに、おおきな流動性を与えることだけが確かなことだ。いいかえれば学習IIに固執して離れられないでいる自分を解き放った状態におくものだということはできる。
わたしたちが「自己」と呼んだり「性格」とか「個性」とか呼んでいるもの、わたしが「わたし」だとおもっているものは、ひとつの生体システムのなかでの学習IIの集合物を意味している。そこで学習IIIのレベルによって自分の行動の「コンテクストのコンテクスト」を客体視しながら行動する能力を獲得するにつれて「自己」は虚しさに漂いはじめ、学習IIの集積体として経験を型としてもっている「自己」という存在は、あまり有用性を感じなくなってゆく。
ベイトソンはもうひとつのことを主張している。学習IIIのレベルに跳躍しようとすることは、もし失敗すれば精神病と呼ばれる場所に陥ちこんでゆく危険をともなっている。「自己」に重さをもたなくなり、漂いはじめるので、一人称を使うことに困難を覚えるようになってゆく。また学習IIの集積にともなう矛盾は、和らげられて解消してゆくことが考えられる。「自己」が行動の組織者として働くことをやめてしまうから、個人的なアイデンティティは関係性のなかに溶け出してしまう体験をもつようになるかもしれない。
ベイトソンによればこの状態は「宇宙的な相互作用のエコロジーと美のなかで、生存が成り立っ」ている状態で、このレベルに達した人は、経験の微細なところに意識のフォーカスを当てる方法を身につけて、大洋的感覚へ溺れてゆくことを食いとめるほかないかもしれない。そのディテールの意識化から「宇宙全体の姿があらわれでる」ことになる。
ベイトソンはこの学習IIIのレベルへの精神の跳躍を最高の段階とみなして、そこから「進化の遠大なプロセスを展望するとき、それは遺伝的な決定がゆっくりと、上のレヴェルへ押し上げられていく歴史として見えてくるようである」という歴史の意味づけを述べている。ほんとうはここから入ってアルコール中毒症治療の宗教的な団体である〈アルコホリックス・アノニマス〉(アル中匿名者の会)の治療方法を解析してゆくベイトソンの風貌をみることになる。それはいかがわしい東洋風宗教の理解と、山師的な迫力ある情熱と、見事な解析力との異様な混融であり、それはすでに学習IIIのレベルについて説いているところに予感としてあらわれているものの展開に当っている。わたしたちはだんだんとベイトソンの方法の風貌と、学習IIIのレベルとの融合によってもたらされる迫力ある異形のベイトソンのイメージのなかに這入りこんでゆくことになる。興味深いから、少なくとも一度は体験して損はない世界だとおもえる。
【この書評が収録されている書籍】
ましてこの本の主題は、眼に視えないが、いつも環境の状態に応じて刻々に変化している「精神」という獲物を、できるかぎり背景の野に放ちながら、狙いを定め、射止めなくてはならないし、射止める方の「精神」が刻々に位置と場所を変えているところも記述しなくてはならない。どこに緒口を見つけてゆけば、よいのか。ベイトソンのやり方の特徴をいくつか挙げてみる。
まず動いている個々の生命体や精神体と、それをそうあらせている社会的な、また生態的な構成体を、切り離せない生きたひとつのシステムと見做している。つまり「わたし」という狩人が動きながら、おなじく草原のなかで動いている獲物を狙って、これを仕止めようとしているという図解の仕方をやめて、「わたし」のように動いている狩人も、それに追われておなじく避難するため動いている獲物も、その動くふたつを乗せている草原という環境も、切り離せないひとつの生きたシステムとみて、そのシステムの要素が変化するために刻々にシステムの構図が変化しているという見方をするのだ。人間の精神を包含したこのシステムをひとつの生物的なシステムとかんがえれば、このシステムは個々の要素の変化によって、刻々に変化する第一次変化だけでなく、できるかぎり外界との適応をよくし、試行錯誤を減らすためにフィードバック回路をもっていると同時に、第二次的な変化の統御装置のレベルをもち、これで逐次に次元の高いところから統御するひとつの階程的なヒエラルキーをつくっていると見做される。たとえばわたしたちが習慣とか習俗とか慣例とか呼んでいるものは、試行錯誤の不経済性を減らして適応をよくするための、硬く強い統御のレベルを意味している。そしてベイトソンが採用している前提によれば、適応を強化し試行錯誤を少なくするための統御の層がつくるヒエラルキーは、ラッセルの数学基礎論のいう意味での「論理階型」の性質をもつものとされる。たとえばひとつの「クラス」はそれ自体のメンバーから除外されるし、「クラスのクラス」はそのレベルのメンバーである「クラスのメンバー」からは除外される。もっとこの「クラス」を現実の事物に近づけてゆくと「湯気のたちのぼる料理」とその料理の名前を指し記した「メニューの紙きれ」とは「論理階型」のレベルがまったくちがうから、混同されてはならないことになる。
いま学習ということについて、わたしたちの生物的なヒエラルキーが、どんな論理階型に従うかを調べてみる。ベイトソンの挙げている例でいえば「工場のサイレンから、いま正午だということ」が分かる(learn)。このばあいの学習はサイレンが鳴ったという出来ごとから、単純に直接に情報を受信して、正午だということを学んだということだから「ゼロ学習」ともいうべきものだ。でもつぎにサイレンが鳴り、その都度、いま正午だと識知することが繰返されるようになったときは、単なる情報の受信ではなく、受信の受信ともいうべき方向づけが、受信のなかに這入りこんでくる。これはもう「ゼロ学習」ではなく「学習」Iともいうべき論理階型に包括されるといっていい。ところでつぎに断続音の単位長さが異った二つのサイレンを正午に鳴らしたとする。どちらも正午を告げることを、充分に学習(学習I)した後に、二つのサイレンの単位長さを、両方ともその中間の長さに近づけてゆく。そして二つのサイレンの相違を無くすようにして接近させてゆくと、学習するものに精神的な混乱が起る。この状態の学習を学習IIとすれば、これは分裂病者の認知のなかにおこるダブル・バインドの状態の原型といってよい。ベイトソンは、わたしたちの現実の世界は、この学習IIに関わるような現象で満ちみちていると述べている。
ベイトソンによれば、個々の人間の「性格」とかんがえられているもの、たとえばあの人は勝ち気だ、お調子者だ、気むずかしい、大胆だ、臆病だ、ひょうきんだ……といった形容の言葉でいわれるものは、みな学習IIのレベルにある状態を記述する言葉だ。けれど「性格」というものをよく考察し、こういう形容で語られるような反応の変化(学習II)が固定するようになる過程は、学習Iの状態がひとつのコンテクストに沿って進んでいった結果なのだから、そうなる反応の固定化の方向性をつかまえなくてはならない。たとえば「宿命観」の強い人というのは、その人の振舞い方を含む生体システムのなかで、その人と環境とのあいだのやりとりがゼロ学習の次元で繰返されたために固定化された人だということができる。
ベイトソンは学習IIがいちばん露わにあらわれる例として、フロイト派の精神分析療法の例をもってくる。診察室にきた患者は相手のセラピストが過去に親がじぶんに接したとおなじやり方で接してくれるように、無意識的に要望し、セラピストとのやりとりをかつて親(母)とのやりとりの学習IIとおなじように鋳型しようとする。これは乳幼児期に行われ、いまは無意識になって身についているものだ。この学習IIは正しいか間違っているかとは何のかかわりもない、あるひとつの「見方」や「振舞い方」として身についている。じぶんの行動を成就させることで、身につく度合を強化しようとして、目的が不成功におわっても、べつに打撃をこうむったり、挫折感をもったりするわけではない。それは「目的」の前提となる精神の状態と、なまの物質的な事実とは、「論理階型」の次元がちがうから、矛盾が起っても具体的な経験としては示されることはないからだ。過去の乳幼児のとき無意識になされた学習IIは、たえず自分をそこに落着かせるように作用するから、一度学習がなされると根本から消し去ることはほとんど不可能になる。それが成人の事象へのかかわり方が、フロイト学派のいうように、乳幼児のときに根をもつことの、ベイトソンによる理解の仕方ということになる。
ところでベイトソンは、学習IIについての学習(つまり学習IIIの段階)を実現することは可能だとみなしている。わたしたちがベイトソンのやり方、考え方を究極のところまでもっていって検討しようとすると、ベイトソンは学習IIIとその結果について語らざるを得なくなってゆくようにみえる。
まず、(1)学習IIのレベルにある行動を習慣にまで固定化し、パターン化するのを助け、スムーズに進行させる能力を身につけるようにする。また、(2)同時に学習IIIを成就したときに学習IIIから抜け出せるような通路を、開いたり塞いだり自在にできるような能力を獲得するように修練する。また、(3)無意識に学習IIのレベルにあることを実行することができ、また実行しながらそれを客体視できるように修練する。こういったことはすべて学習IIIのレベルに属している。この学習IIIが身についたとして、それは学習IIを強化する方向にもゆくが、また学習IIを制限し、抑圧する方向にもゆくことができる。だから学習IIIに属することを身につけることは、いいことなのか悪いことなのかにわかに断定することはできない。ただ学習IIで得られたものに、おおきな流動性を与えることだけが確かなことだ。いいかえれば学習IIに固執して離れられないでいる自分を解き放った状態におくものだということはできる。
わたしたちが「自己」と呼んだり「性格」とか「個性」とか呼んでいるもの、わたしが「わたし」だとおもっているものは、ひとつの生体システムのなかでの学習IIの集合物を意味している。そこで学習IIIのレベルによって自分の行動の「コンテクストのコンテクスト」を客体視しながら行動する能力を獲得するにつれて「自己」は虚しさに漂いはじめ、学習IIの集積体として経験を型としてもっている「自己」という存在は、あまり有用性を感じなくなってゆく。
ベイトソンはもうひとつのことを主張している。学習IIIのレベルに跳躍しようとすることは、もし失敗すれば精神病と呼ばれる場所に陥ちこんでゆく危険をともなっている。「自己」に重さをもたなくなり、漂いはじめるので、一人称を使うことに困難を覚えるようになってゆく。また学習IIの集積にともなう矛盾は、和らげられて解消してゆくことが考えられる。「自己」が行動の組織者として働くことをやめてしまうから、個人的なアイデンティティは関係性のなかに溶け出してしまう体験をもつようになるかもしれない。
ベイトソンによればこの状態は「宇宙的な相互作用のエコロジーと美のなかで、生存が成り立っ」ている状態で、このレベルに達した人は、経験の微細なところに意識のフォーカスを当てる方法を身につけて、大洋的感覚へ溺れてゆくことを食いとめるほかないかもしれない。そのディテールの意識化から「宇宙全体の姿があらわれでる」ことになる。
ベイトソンはこの学習IIIのレベルへの精神の跳躍を最高の段階とみなして、そこから「進化の遠大なプロセスを展望するとき、それは遺伝的な決定がゆっくりと、上のレヴェルへ押し上げられていく歴史として見えてくるようである」という歴史の意味づけを述べている。ほんとうはここから入ってアルコール中毒症治療の宗教的な団体である〈アルコホリックス・アノニマス〉(アル中匿名者の会)の治療方法を解析してゆくベイトソンの風貌をみることになる。それはいかがわしい東洋風宗教の理解と、山師的な迫力ある情熱と、見事な解析力との異様な混融であり、それはすでに学習IIIのレベルについて説いているところに予感としてあらわれているものの展開に当っている。わたしたちはだんだんとベイトソンの方法の風貌と、学習IIIのレベルとの融合によってもたらされる迫力ある異形のベイトソンのイメージのなかに這入りこんでゆくことになる。興味深いから、少なくとも一度は体験して損はない世界だとおもえる。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする