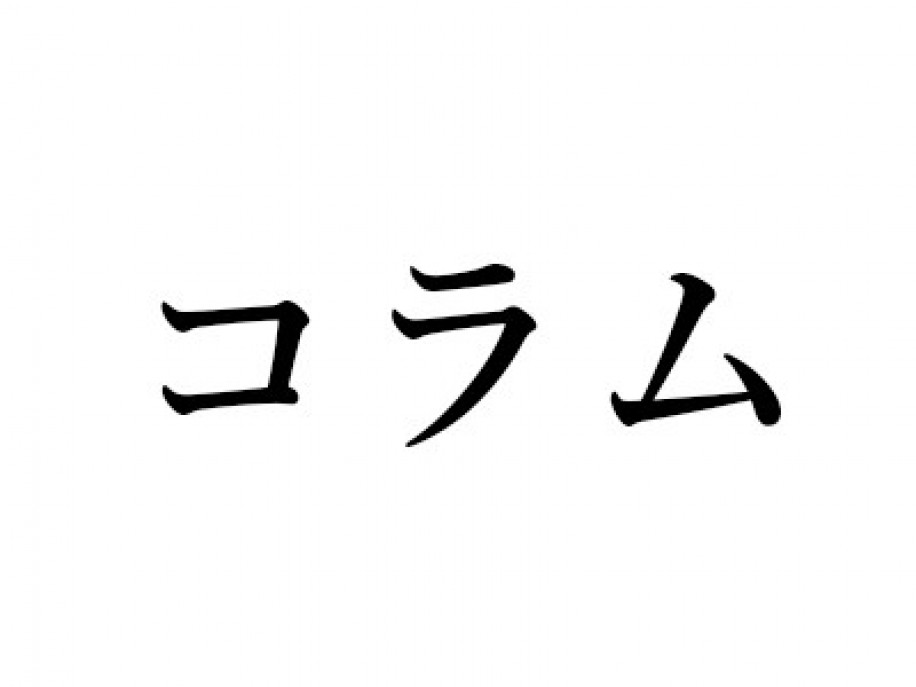書評
『世界を食べよう! ―東京外国語大学の世界料理―』(東京外国語大学出版会)
異文化研究者三十人が語る食の多様性
なんと贅沢(ぜいたく)な一冊だろう。世界の食文化案内であり、食いしん坊を舌なめずりさせる読み物であり、旅のガイドであり、しかもレシピ付き。東アジアから始まってヨーロッパ、オセアニア、アフリカまでぐるり、いながらにして食卓の遊覧旅行だ。本書のオリジナリティーは、三十人余の執筆者にある。東京外国語大学の異文化研究者たち。つね日頃から異文化と格闘している研究者が、精通する各国の歴史や文化を背景にしつつ、食をどう読み解くのか。“違いの際立つ”内容そのものが、おのずと食文化の多様性を物語るかっこうだ。編者、沼野恭子はロシア文学や比較文学の研究者として知られ、翻訳も多く手がける東京外国語大学教授である。
沼野は書く。
世界料理とは『文化の翻訳』にほかならない
翻訳とは、異文化の擦り合わせ、あるいは能(あた)う限りの他者への歩み寄りでもあるだろう。いっぽう、解釈をほどこし、理解を深めれば深めるほど、違和や異質性もまた浮き彫りになってくる。それらすべてをひと匙(さじ)のスプーンにのせて味わうとき、おのずと私たちは、他者の認めかた、敬意の払いかたを訓練しているのだと思う。
さて、三十人余の料理人の腕前はそれぞれユニークで、興趣に富む。ベトナム料理編「いろいろ妄想しながら米製麺を食べてみる」(野平宗弘・講師 ベトナム文学)では、詩人トゥー・モーのフォーを礼賛する詩を紹介。フランス料理編「多様性の饗宴」(博多かおる・准教授 フランス19世紀文学)では、バルザック『ゴリオ爺さん』『老嬢』『従兄ポンス』、ゾラ『獲物の分け前』、モーパッサン『ペルル嬢』などが登場。食と文学との親和性を再認識させられる。
食を語る文章そのものにも、香気がある。たとえば、セルビア料理編「仲間で囲むよき食物」(山崎佳代子 セルビア文学・比較文学 ベオグラード大学教授)、この一節には感銘を受けずにはおられない。
(前略)セルビアの料理は繊細ではないし、器の色彩や形にこだわったり切り方に工夫をしたり、視覚的な美を追及することもない。だが村文化に発するセルビア料理は、食べて生きるという人間の課題に、まっすぐに応えている
いかなる料理も、人間の課題に応えて生まれたもの。本書の意義を余すところなく伝えている。
読むほどにおなかが空き、台所に立ちたくなること請け合い。長年の謎も解いてくれた。ドイツ人がゆでたじゃがいもを食べるとき、ナイフで切らず、フォークの脇で押して切るのは、「じゃがいもの成分によって銀製のナイフがくもるのを避けるため」。なるほど! コラム「世界にひろがる日本料理」も目配りが効いており、ロシアの甘い寿司(すし)やウクライナの段々状の巻き寿司の写真にびっくり。旅に出たくなって困る本でもあるのだった。
ALL REVIEWSをフォローする