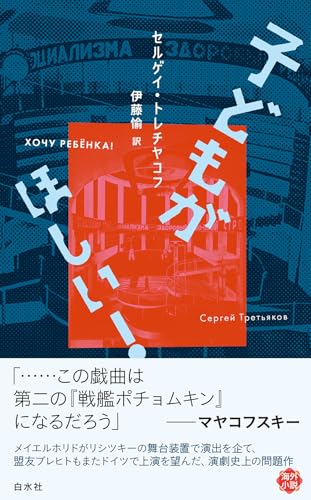書評
『むずかしい年ごろ』(河出書房新社)
ロシア発のSF 独特の語り口
著者のアンナ・スタロビネツは、“ロシアのスティーヴン・キング”と呼ばれているそうだが、初の邦訳書となる本書を読むと、むしろ“ロシアのP・K・ディック”と呼びたい誘惑にかられる。これは、彼女が2005年に26歳の若さで出版したデビュー作品集だが、収録の8編が描くのは、たとえば――。人間ではない何者かに体を乗っ取られる恐怖。人間とロボットの違いは何か。アイデンティティ(または記憶)の不確実性。“シナリオ”によって操作される現実……。ディックが1950年代に短編でくりかえし描いたテーマが、ゴーゴリやブルガーコフを育んだロシア幻想小説の土壌に移植され、21世紀のモスクワに鮮やかに甦(よみがえ)った感じ。その意味では、ホラー読者よりもSF読者のほうが、よりシンパシーを抱くかもしれない。
心臓も呼吸も止まっているのに(医学的には死んでいるのに)なぜかふつうに出勤する会社員の悲哀を描く「ヤーシャの永遠」にしても、ネタ的には70年代の日本SF(かんべむさしや筒井康隆の不条理な短編群)そのままだが、料理の仕方は現代的。ジャンル小説と純文学のあいだで絶妙の綱渡りを見せる。
本書の中核は、全体の3分の1以上を占める、巻頭の表題作。原題を直訳すると「過渡的な年齢」らしいが、「むずかしい年ごろ」とはまさに名訳だ。物語の始まりは、離婚後、8歳の双子(マクシムとヴィーカ)を連れてモスクワ郊外に引っ越したマリーナが、近所の森を子どもたちと散策する場面。数年後にふりかえって、マリーナはそれが“自分たちの人生最後のいい日”だったと思い当たる。というのも、その翌日、マクシムは重い病気になり、3週間以上も寝込んだ挙(あ)げ句、別人のように変貌してしまうからだ。
注意散漫、集中力の欠如、過食。枕の中やベッドの下に甘いものを溜(た)め込み、部屋には悪臭が立ちこめる。いったいマクシムに何が起きたのか?(帯や訳者あとがきにはその答えがモロに書いてあるが、知らずに読んだ方が衝撃度が高いかも)。アイデアそのものは珍しくないが、複数視点を織り交ぜ、さらにマクシムの日記や児童向けの科学書からの引用をちりばめた独特の語り口で、たっぷりぞくぞくさせてくれる。
著者は、村上春樹論を書いたり、日露合作の超能力SF戦争アニメ『ファースト・スクワッド』(2009年/芦野芳晴監督)の小説化を手がけたりと、日本とも縁が深い。本書に続いて、長編の邦訳にも期待したい。
ALL REVIEWSをフォローする