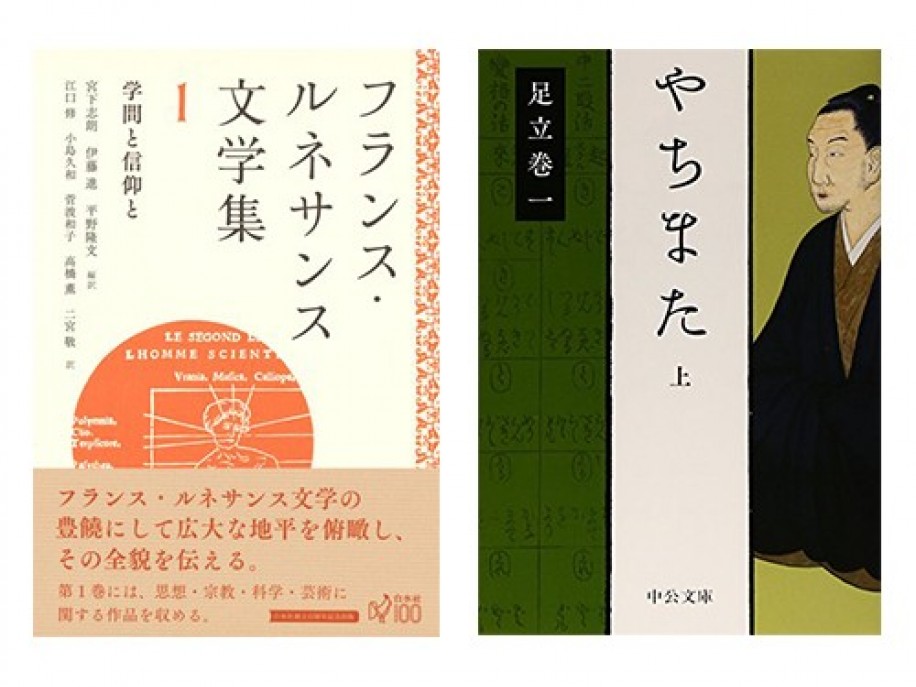書評
『ガルガンチュア―ガルガンチュアとパンタグリュエル〈1〉』(筑摩書房)
「読み進ませる力」みなぎる新訳
蛮勇とは、この訳者のためにこそふさわしい言葉だろう。なにしろ、日本におけるフランス文学の大先達、かの渡辺一夫の名訳中の名訳、フランソワ・ラブレー『ガルガンチュアとパンタグリュエル』の新訳に挑んだのだから。そのプレッシャーたるや、恐ろしいものがあったはずだ。にもかかわらず、訳者はあえて新訳を世に問うた。なぜか?訳者は「解説」でこう述懐している。「古典にはいくつも訳があっていい、ダンテを見よ、シェイクスピアを見よと、口でいうのは簡単だ。しかし、渡辺一夫訳には、そうしたものいいを許さないほどの威厳が備わっている。この歴史的な名訳を、尊崇の念で仰ぎつつも、なるべく明快な訳文を実現すること――このことを念頭に、原文にアタックした」。訳者の意図は最後の文章にさりげないかたちで表現されている。そう「明快な訳文」、これである。
思うに渡辺一夫訳は、高次元のレベルでは漢詩・漢文、低いレベルなら義太夫、浪曲、落語などが日本人共通の言語記憶であった時代の名訳である。たとえば冒頭に置かれたラブレーの「作者の序詞」はこう訳されている。「世にも名高い酔漢(さけのみ)の諸君、またいとも貴き梅瘡(かさ)病みのおのおの方よ、――かくのごとく呼び申上げるしだいは、私の書物(かきもの)が捧げられるのは正に諸君にであって、よそのお方たちにではないからだ」
対するに、テレビと漫画とネットしかリファレンスのない現代の「明快な訳」とは? 宮下訳は以下の通り。「世にも名高いよっぱらいのみなさま、そして、ほら、そこのあなた、なんとも貴重な梅毒病みのみなさま、――だって、わたしの書物が捧げられるのは、まさにあなたがたなのですよ」
渡辺訳ではとたんにつかえてしまう若い読者も、この訳文ならなんとかページをめくろうと思うだろう。この調子で、渡辺訳のかの有名なガルガンチュア作の便器の歌「雲谷(うんこく)斎よ、/びり之助よ/ぶう兵衛よ、/糞まみ郎よ、/そなたのうんこが、/ぼたぼたと/わしらの上に/まかれるわい。/臭太郎よ、/糞次郎よ、/たれ三郎よ、/聖アントワヌ熱で焼かれてしまえ!/もし仮に/みんなの穴が、/閉まっていれば、/尻は拭かずに退却じゃて!」は、次のように訳しかえされる。
「うんち之助に、/びちぐそくん、/ぶう太郎に、/糞野まみれちゃん、/きみたちのきたないうんこが、/ぼたぼたと、/ぼくらの上に、/落ちてくる。/ばっちくて、/うんちだらけの、/おもらし野郎、/あんたの穴がなにもかも/ぱかんとお口を開けたのに、/ふかずに退散するなんて、/聖アントニウス熱で焼けちまえ!」
なんだか「ひらけ!ポンキッキ」でオン・エアーしたら子供たちに馬鹿受けしそうな訳文だが、これは五歳のガルガンチュアが父親のグラングジエに披露したスカトロジー・ソングという設定なのだから、決して悪くはないのである。
このように、渡辺訳に親しんだ読者には少し拍子抜けするかもしれない訳文だが、渡辺訳にはなかったものがこの新訳にはある。それは、先へと進ませる力。私がひそかに「散文パワー」と命名している力である。おそらく、宮下訳はブレス(息継ぎ)がうまいのだろう。ゆえに、渡辺訳ではパンタグリュエルの巻まで進めなかったという経験を持つ読者もこの新訳なら完読も不可能ではない。
訳注に見るラブレー学の最新成果も興味深い。(宮下志朗訳)
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする