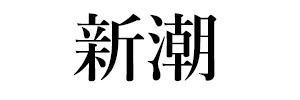選評
『ロック母』(講談社)
川端康成文学賞(第32回)
受賞作=角田光代「ロック母」/他の候補作=黒井千次「久介の歳」、池澤夏樹「20マイル四方で唯一のコーヒー豆」、村上春樹「ハナレイ・ベイ」、辻井喬「書庫の母」、西村賢太「一夜」、日和聡子「尋牛図」、桐野夏生「植林」/他の選考委員=秋山駿、小川国夫、津島佑子、村田喜代子/主催=川端康成記念会/発表=「新潮」二〇〇六年六月号音の力
男に逃げられたまま臨月を迎えようとしている女が「実家に戻れば少しは楽ができるか」もしれないなどと虫のいいことを考えながら、瀬戸内の小島に帰ってきて、いろいろあった末に子を産む。これだけならば別にどうということもない平凡な話であるが、「ロック母」の作者は赤ん坊の泣き声やロック音楽などの〈音〉を作品の芯に染み込ませ、この平凡な話を非凡な短篇に高め、その上、わたしたちの時代の気分という目に見えないものを、はっきりと小説の言葉にした。作品の進行につれて明らかになる時代の気分とは、たとえば次のようなものだ。
……そうだよな、何しろ彼は結婚もしてくれないようだしな、シングルマザーなんて私には無理だわな、でも堕胎なんてこわいしな、子ども産めなくなったりしたらやばいよな、などとのらりくらり考えているうちに、今日に至っている。人が意志で決断しなくともものごとは決まるらしい。私は迷っていただけで何ひとつ決めていないのに、もうすぐ赤ん坊は産まれてきて、私はシングルマザーになる。
何ひとつ自分の意志で決められずに、なるがままに漂って生きるしかないように見える時代、彼女はその時代の申し子である。
少女時代の彼女はイヤホンから注ぎ込まれる大音量のロックで、退屈な島のすべてを遮断し、その音の洪水のなかで大都会を思い浮かべ、島からの脱出を夢みていた。そしていま帰郷してみると、母親が少しおかしくなっていて、かつて自分が聞いていた音楽を大音響で鳴らしている。作品はこのあたりから好ましい歪みを見せはじめるが、出産の瞬間、女は、左耳にほとんど絶叫に近い母の励ましの声を、そして右耳に赤ん坊のふりしぼるような泣き声を聞いた。つまり、ロック音楽は過去の絶叫であり、新しい生命の声でもあるという主題がみるみる浮かび上がってきて、読む者の心を動かす。これらの音は、時代の気分への劇しい抗議なのだ
【この選評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする