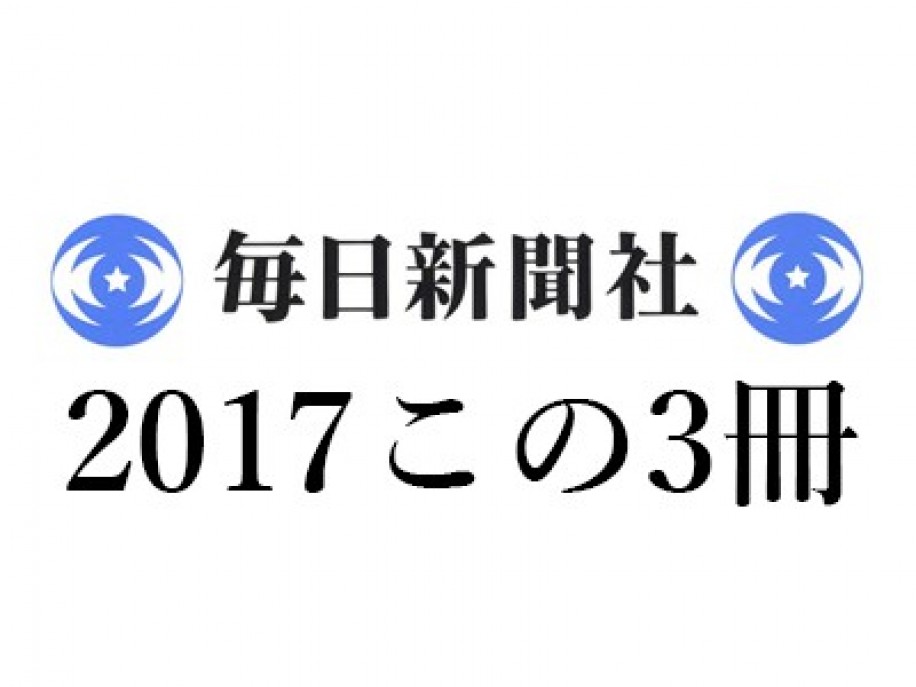書評
『新しい小説のために』(講談社)
先進的で回帰的な「語り」の復権
本大著で渾身(こんしん)の力で論じられるのは、小説における人称と視点とそこから来る「私」の問題だ。柄谷行人の『日本近代文学の起源』(一九八〇年)を一つの支点に、遡(さかのぼ)って小林秀雄、横光利一、バルト、デリダ、レヴィ=ストロース、ジュネットらの理論書、ジッドの『贋金つかい』、その一方、時代を下り、野口武彦の『三人称の発見まで』、高橋源一郎、保坂和志の評論書などを縦横に引きながら文学理論史をさらい、それを果敢に更新する。
ゼロ年代からの日本文学シーンは、大雑把(おおざっぱ)に言うと「前衛流行(はや)り」だ。奥泉光、保坂和志、磯崎憲一郎、岡田利規、青木淳悟、柴崎友香、山下澄人らが、語りの視点と人称に仕掛けのある小説を書いている。三人称多元視点でなくては見えないはずのことを一人称一視点のまま語ったり、その逆のことが行われたりし、渡部直己によって「移人称」と名づけられた。佐々木はこの問題についても本書で手厚く応答する。
江戸時代まで日本語にはなかったという三人称客観描写が「発見」されるまでの過程の解説はスリリングだ。柄谷の「風景の発見」から入り、風景とは遠近法の発明とともに生まれたが、遠近法こそが文学では三人称客観描写にあたるとする。次に「内面の発見」がとりあげられ、人物の(心の)声の、語り手を通さないじかの発露は、言文一致により可能となり、文末の「~た」という「人称詞」(野口の命名)により、三人称客観描写が実用化された。声(言)が表現(文)を得たのだ。
超越的一人称の語り手(今でいうと、たとえば小野正嗣の三人称小説『獅子渡り鼻』で議論を呼んだ見えない語り手)は、小説の中から一見消え去り、“完全な”三人称小説が誕生した--。実はわたしは、物語は三人称に始まり、一人称は後から作られたと思っていた。そのため、本書の記述に、時々戸惑った。たとえば、『三人称の発見まで』からの引用で、「古代ギリシアには、散文はなかった。あったのは、劇であるか詩であるか対話か<中略>。確実にいえるのは、この三つが一人称だったことである」。劇と対話は措(お)くとして、「物語」の始まりであり出来事を記録する叙事詩は、三人称文体ではないのか。ギルガメッシュ叙事詩、ホメロスの「イリアッド」、英語文学最古の「ベオウルフ」……。もちろん、最初(と所々)に語り手は出てくるが、これは「形式的な一人称の語り手」で、物語は実質三人称だと解釈していた。しかし本書によれば、それら近代以前の語り手の声は人形浄瑠璃の語りのように、どこか他域、異界から響いてくるものであり、その一人称性は全編に及ぶという。成程、よく十八世紀の英国小説に作者がひょいと顔を出し、ポストモダンのようで先進的と評されるのだが、むしろ「先祖返り」あるいは古(いにしえ)の語りの残響だったのか。
プラトンの時代には、作者=語り手のディエゲーシス(叙述)が尊く、ミメーシス(描写)は格下だったが、文学に散文が幅をきかせるようになると、「描写」が上になる。H・ジェイムズの言う「語るなかれ、示せ」である。しかし文学の「写実」は、写真、映画、デジタルアート等に御株を奪われてしまった。
では、描写の次にくる小説の本分とはなにか。語りの復権だろう。先述の「移人称」作品にしても、そうした「わたし」の書き方は新しいだけではなく、回帰的でもあると、佐々木は指摘している。近代的テクストの下に押しこめた古代の精霊の声が地底から響いてくるようで身震いがした。新しくて、古く、未(ま)だ見ぬ「わたし」よ、ようこそ。
ALL REVIEWSをフォローする