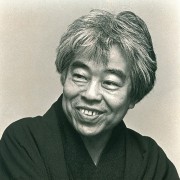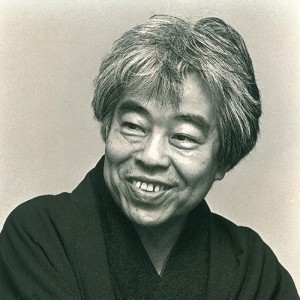書評
『スミヤキストQの冒険』(講談社)
奇妙な舌ざわりの観念小説
この長編は奇妙な舌ざわりをもった観念小説である。現代人の意識にひそむ観念の像をどのように具象化するかということは、たいへんむずかしい作業だ。現実のリアルな模写では描ききれない複雑な意識の構造を、この作者はある孤島にあるH感化院という閉ざされた舞台を設定し、そこに登場する人物たちの姿に戯画化してとらえようとこころみている。話はこの感化院にQというスミヤキ党の党員が、党の密命をうけて到着するところからはじまる。Qの使命はこの感化院に革命をおこすことなのだが、まるきり公式的なQの意識構造にとってはすべてが意表をつくような人物と行動の連続で、Qには手も足もでない。ブヨブヨした観念の肉でふくれあがった院長、哲学的な理屈をあやつる主事、カニのような容貌をもち神の観念にとりつかれた神学者、アンチ・ロマンの小説を書こうと夢みている文学者、シニカルな表情をかくそうとしないドクトルなど、登場人物たちはいずれも観念をそのまま擬人化したようなタイプだ。
この作品はほとんど彼らとスミヤキストQとの、あくことを知らない会話で構成されているが、そこには、デテールの面では現実社会の問題がかなりリアルに投影されている。この感化院に社会科学の錬師として赴任したQは、こうした院内の支配階級にたいして、院児や雑役夫たちの被支配階級が革命の意識にめざめ行動をおこすにはどうすればよいか、あれこれと思索をめぐらすが、結局Qの考えとは無関係に、院児たちの自然発生的な暴動が突発し、すべてが荒廃に帰し、Qは最後にひとり、この島から脱出する。
スミヤキ党が現代の前衛党を戯画化し、スミヤキストQの思考形式がカッコつきでいわれる革命党員のパロディーであることはあきらかだが、作者のねらいはそういった問題だけにとどまらず、むしろ支配と被支配といった社会構造そのもののパロディー化にあったのではないか。しかもそれを陰画として描くのではなく、一種の用器画的手法を用いて幾何学的な図形にまとめている。
作者は島の感化院という特殊な社会を設定し、その中をスミヤキストQという人物を動かすことによっておこるさまざまの波紋を、Qと他の人物たちとの対話で表現しているが、この対話は同時に、作者自身がスミヤキストQという作業仮設をもうけて、状況にコミットしようとすることのあらわれであり、また読者にとってもその対話に読者の側から参加できるというおもしろさを十分に味わわせてくれる。
「スミヤキストQの冒険」がしめす世界が、現実の社会をどれだけ正しく風刺しているかはともかく、読者にとって、このような読むたのしみを備えた作品であるといえよう。このたのしみはまた作者が小説を書くたのしみにもかさなるものだ。
現実の政治がもつドロドロしたものはここには感じられない。傷つき、うちひしがれ、しかも生きることの意味をもとめようとする人たちの立場からは不満がでるかもしれないが、しかしそういった政治的体験とは別のところからつかまえられた現実認識がそこにはある。
スミヤキストQが結局は、思考するだけで現実の変革に何のかかわりももてずに島から去ってゆくという設定に、作者の批判をよむことができる。学園闘争の予見となっているのもおもしろいが、観念小説のとぼしい日本の文学にとって、倉橋由美子の存在は貴重なものがある。
ALL REVIEWSをフォローする