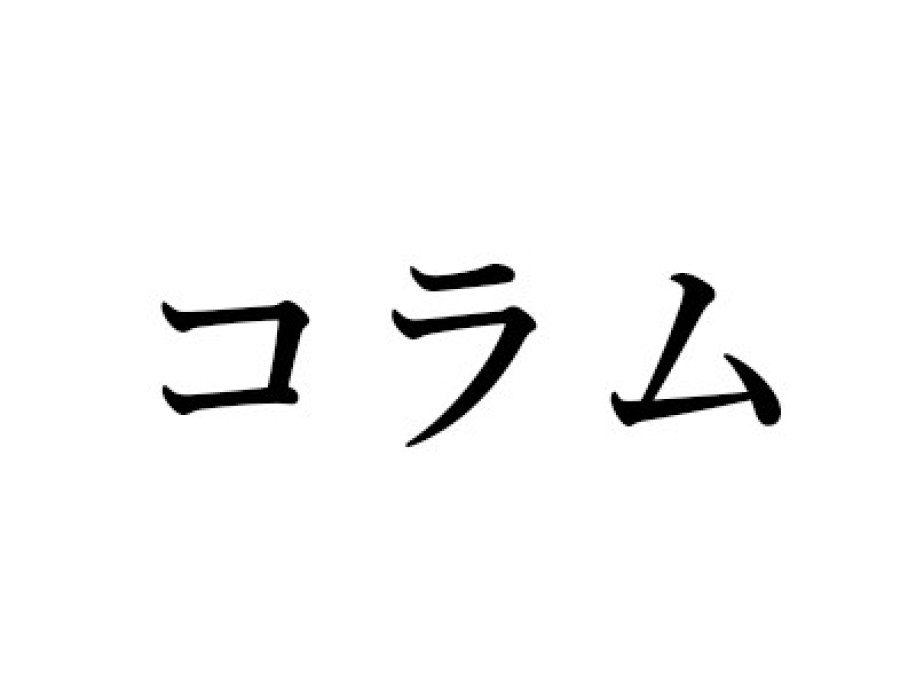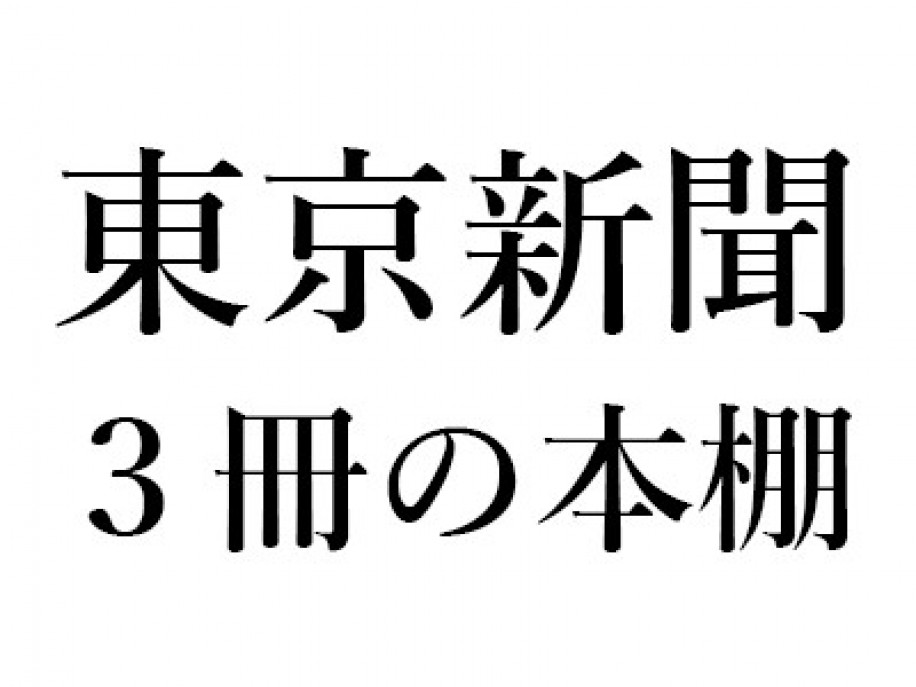書評
『超高速に挑む―新幹線開発に賭けた男たち。』(文藝春秋)
「新幹線」を実現させた男たち
高度成長への助走が開始され、やがて文字通り高速度に経済成長をとげた昭和三十年代。この時代は、まぎれもなく男くささに満ちた時代であった。道路では名神、次いで東名高速道路、飛行機ではYS11、そして鉄道では東海道新幹線。大規模な交通インフラが、次から次へと実現の緒に就いた。これらをリードしたのは、いずれも戦時体制下で必ずしも所を得られなかったいわゆる技術屋さんたちである。とりわけ高度成長のシンボルとも言うべき東海道新幹線が、実は圧倒的な反対論を克服してようやく実現にこぎつけたという事実を知る者は少ない。さらに言えば、高度成長は無為にして自然に達成されたわけではない。当時の日本人の自覚的な営みがあって、初めて実現可能となった。こうした認識を背景として、本書は当時の生き証人のヒアリングや資料を基に、東海道新幹線を実現させた男たちのドラマを描いてあきさせない。
十河信二国鉄総裁―島秀雄技師長のラインは、国鉄内における広軌別線反対論や、国鉄外における鉄道斜陽論に対して、時には政治を利用しつつ、時には技術論を援用しつつ対応していった、なかでも、鉄道にはシロウトの旧陸海軍の技術者集団に技術革新を進めさせ、個々バラバラではなく高速鉄道の総合研究プロジェクト体制をとったこと、単年度予算の限界を乗りこえ事業継続を義務づけるため、世界銀行から一億ドル近い借款をうけたこと、新幹線早期実現のために、横断的組織として総裁直属の「新幹線総局」を設けたことなどは、注目に値する。
それにしても、はてこれはどこかで聞いた話とそっくりではないか。実はその通り、国鉄分割民営化のプロセスにきわめてよく似ているのだ。国鉄内部の強固な守旧的体質と、それがみごとに覆っていく有り様を、我々は二度までも目の当たりにしたことになる、それはやはり、国鉄という組織の宿命だったのだろうか。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする