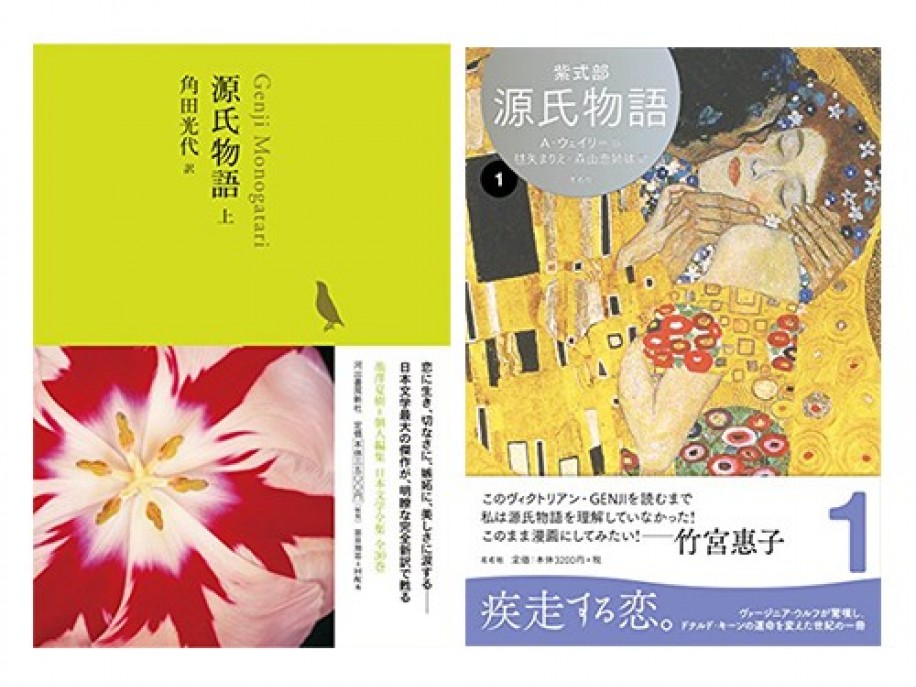書評
『源氏供養』(中央公論社)
橋本治著『窯変源氏物語』は、光源氏が「私」という一人称で語る源氏物語である。つくづくそれは「男」の源氏物語だった。
たとえば有名な雨夜の品定めの場面で、一人つまらなそうにしている光源氏のモノローグが随所に入る。なるほど、彼はこういう気分でここにいたのか、なるほど、と、私は何度も膝を打たされた。
また、談義の参加者の一人である藤式部丞の身分の低さが、しつこいほど書かれている。
この点の真意は、本書『源氏供養』を読んで、あらためてなるほど、と思った。
「雨夜の品定めは、決して『四人の貴公子による女性談義』なんかではない」結論だけをここに取り出すと「えっ?」と思われる人も多いだろうが、本書はそれをきちんと説得してくれる。
他にも「えっ?」という話が山盛りだ。
「源氏物語とは、体制批判の物語である」
「源氏物語は、不遇な中流貴族の娘の復讐譚あるいは救済物語でもあるという一面を持つ」
「桐壼帝が桐壼の更衣と死別したのは、十八歳のときではないか」
「光源氏の藤壼の女御への恋心は、母への思慕などではない」
「光源氏と藤壼の女御の恋は、それほどの大タブーだったとは思われない」
『窯変源氏物語』が生まれる過程で、著者が発見し、確信したさまざまなことが、迫力を持って綴られている。それは、『源氏物語』の一語一語と、とことんつきあった著者ならではの迫力だろう。
また、男ならではの視点も、興味深い。
『源氏物語』の中心にいる上流貴族の男たちは、十代の初期で元服すると同時に、年上の女性をあてがわれる。
「現代あるいは近代青年と光源氏が最も遠いのは、恐らくここですね。光源氏には、ひりつくように他人を求める身体欲求がない」と著者は指摘する。
私などはこれまで「よくまあ、これだけ体が続くもんだ」と思って『源氏物語』を読んでいたふしがあるので、この視点はとても新鮮だった。そして「確かに」と思う。もう一度雨夜の品定めの例を出すと、藤壼の女御のことをずっと考えている光源氏の思慕が「性的飢餓感ではない」というのは、なかなか洒落た結論ではないだろうか。
【この書評が収録されている書籍】
たとえば有名な雨夜の品定めの場面で、一人つまらなそうにしている光源氏のモノローグが随所に入る。なるほど、彼はこういう気分でここにいたのか、なるほど、と、私は何度も膝を打たされた。
また、談義の参加者の一人である藤式部丞の身分の低さが、しつこいほど書かれている。
この点の真意は、本書『源氏供養』を読んで、あらためてなるほど、と思った。
「雨夜の品定めは、決して『四人の貴公子による女性談義』なんかではない」結論だけをここに取り出すと「えっ?」と思われる人も多いだろうが、本書はそれをきちんと説得してくれる。
他にも「えっ?」という話が山盛りだ。
「源氏物語とは、体制批判の物語である」
「源氏物語は、不遇な中流貴族の娘の復讐譚あるいは救済物語でもあるという一面を持つ」
「桐壼帝が桐壼の更衣と死別したのは、十八歳のときではないか」
「光源氏の藤壼の女御への恋心は、母への思慕などではない」
「光源氏と藤壼の女御の恋は、それほどの大タブーだったとは思われない」
『窯変源氏物語』が生まれる過程で、著者が発見し、確信したさまざまなことが、迫力を持って綴られている。それは、『源氏物語』の一語一語と、とことんつきあった著者ならではの迫力だろう。
また、男ならではの視点も、興味深い。
『源氏物語』の中心にいる上流貴族の男たちは、十代の初期で元服すると同時に、年上の女性をあてがわれる。
「現代あるいは近代青年と光源氏が最も遠いのは、恐らくここですね。光源氏には、ひりつくように他人を求める身体欲求がない」と著者は指摘する。
私などはこれまで「よくまあ、これだけ体が続くもんだ」と思って『源氏物語』を読んでいたふしがあるので、この視点はとても新鮮だった。そして「確かに」と思う。もう一度雨夜の品定めの例を出すと、藤壼の女御のことをずっと考えている光源氏の思慕が「性的飢餓感ではない」というのは、なかなか洒落た結論ではないだろうか。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 1991年4月28日〜1994年4月3日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする