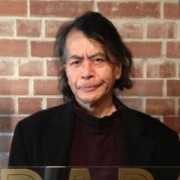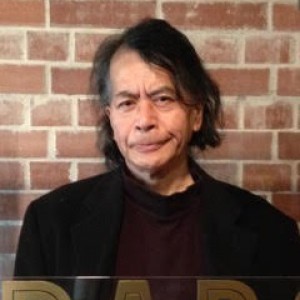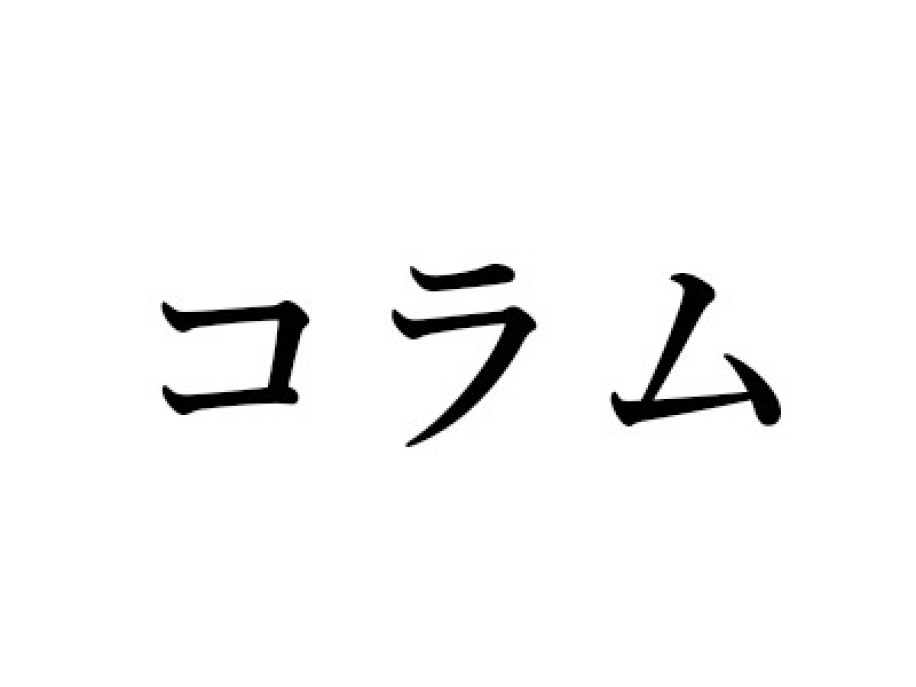書評
『退屈 息もつかせぬその歴史』(青土社)
英米文学を長くやっていて気付いたことがある。多分一番激しいアクションに満ちているはずの巨鯨への復讐(ふくしゅう)物語、メルヴィル作『白鯨』(1851年)が陸上生活の退屈な日々からの逃避行にすぎないことをあばく冒頭の1ページが今なお不思議だ。その年は熱力学第二法則の発表の年でもあることが知られている。閉じた空間の中にどんどんふえる分子が激しく運動するかにみえて、いずれ全てが安定し、動きを失う平衡状態に化していくという理系的世界観に文系の想像力までが感染していったのは、ダーウィンの進化論生物学が社会的に拡大解釈されて猛威をふるったのとパラレルである。『白鯨』冒頭は依然謎である。
児童文学に初めてといってよい激しいアクションをもたらしたキャロルの『不思議の国のアリス』(1865年)も同工で、ものごころついたばかりの少女が「何もすることがないことに退屈していった」という冒頭の1行にして、考えてみると衝撃的だし、好奇心一杯のはずの少女がなぜ、とは実は余り論じられてきていない。少し時代がたってシャーロック・ホームズ・シリーズ(1887年から)はどうかといえば、名探偵の大活劇と、麻薬に逃げるしかない彼の退屈した日常がぴったり均衡している不思議な現象が19世紀末のいわゆる「世紀末」現象を解く最大の謎とされているわけではないか。退屈こそ文学の原動力だ。
明治末年から昭和初期にかけて、欧化の蔭(かげ)で澱(よど)んだ我が国のモダニズムの倦怠(けんたい)ぶりも萩原朔太郎作「猫町」1作にして明白だ。
文学史そのものを退屈からの逃避として書き直すことができる気配だが、良書は少ないし、あっても想像通り重いものばかり。退屈が19世紀末や、実存主義全盛の20世紀半ばの専売特許ではないことをいうのに著者の西洋古典文化への造詣の深さが活(い)きているし、退屈を脳内伝達物質の不足と割り切る今日ふうの切り口にも社会統計の数値だらけのドライさにも鼻白まないで読み進められるのも、退屈を日常ありふれた「有用な」経験のひとつとして受け入れる著者の柔軟な感性があるからだ。
児童文学に初めてといってよい激しいアクションをもたらしたキャロルの『不思議の国のアリス』(1865年)も同工で、ものごころついたばかりの少女が「何もすることがないことに退屈していった」という冒頭の1行にして、考えてみると衝撃的だし、好奇心一杯のはずの少女がなぜ、とは実は余り論じられてきていない。少し時代がたってシャーロック・ホームズ・シリーズ(1887年から)はどうかといえば、名探偵の大活劇と、麻薬に逃げるしかない彼の退屈した日常がぴったり均衡している不思議な現象が19世紀末のいわゆる「世紀末」現象を解く最大の謎とされているわけではないか。退屈こそ文学の原動力だ。
明治末年から昭和初期にかけて、欧化の蔭(かげ)で澱(よど)んだ我が国のモダニズムの倦怠(けんたい)ぶりも萩原朔太郎作「猫町」1作にして明白だ。
文学史そのものを退屈からの逃避として書き直すことができる気配だが、良書は少ないし、あっても想像通り重いものばかり。退屈が19世紀末や、実存主義全盛の20世紀半ばの専売特許ではないことをいうのに著者の西洋古典文化への造詣の深さが活(い)きているし、退屈を脳内伝達物質の不足と割り切る今日ふうの切り口にも社会統計の数値だらけのドライさにも鼻白まないで読み進められるのも、退屈を日常ありふれた「有用な」経験のひとつとして受け入れる著者の柔軟な感性があるからだ。
ALL REVIEWSをフォローする