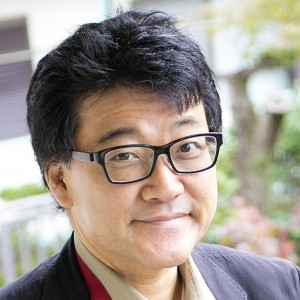書評
『西瓜糖の日々』(河出書房新社)
リチャード・ブローティガン(Richard Brautigan 1935-1984)
アメリカの作家。詩を書いていたが、「自分には文章が書けることを発見」して小説の執筆をはじめる。『ビッグ・サーの南軍将軍』(1964)、『アメリカの鱒釣り』(1967)、『西瓜糖の日々』(1968)などが、若者のあいだで強い支持を得る。物質文明を否定する作品内容だが、ビートニクスに含められることを本人は嫌っていた。そのほかの著作に『鳥の神殿』(1975)、『ソンブレロ落下す』(1976)などの小説、数冊の詩集がある。introduction
夢中でブローティガンを読んだ。『西瓜糖の日々』を読みおえるや、本屋をはしごして手に入るかぎりの本を買い、かたはしから読んだ。早く読まないと、その世界がすり抜けていってしまいそうだった。ブローティガンがさしだした謎は、どうやっても解けはしないが、そのありかだけは確かめたいと気がせいた。その当時はおなじくらいヴォネガットが好きだったが(シニカルなユーモア感覚という点で、このふたりは通じるものがある)、こちらはあわてる必要はなかった。ヴォネガット自身が答をわかったうえで作品を書いているからだ。ブローティガンはそうじゃない。考えても答が出ないことを考えつづけ、かといって問題を突きつめようというのではなく、そのまわりをただまわっている。最後の作品『不運な女』にいたるまで、それは変わっていない。▼ ▼ ▼
「西瓜糖」という文字のつらなりは印象的だ。スイカトウという響きもいい。ずっとむかし、この言葉に引かれて、見知らぬ作家の本を買ったことがある。それがリチャード・ブローティガンとの出会いだった。
『西瓜糖の日々』のなかに描かれた村は、ほとんどのものが西瓜糖でできている。家は西瓜糖をプレスした板材でつくられ、夜には西瓜糖と鱒でつくった油を燃料にランタンを灯す。服も煉瓦も窓も西瓜糖だ。赤、白、青……原料となる西瓜にはいくつもの種類があって、その特性にあわせてものをつくる。たとえば黒い西瓜は切っても音がしないので、音を立てないものをつくるのに都合がいい。
西瓜糖でできた世界などというと、メルヘン調ファンタジイと思われるかもしれない。しかし、まったく違う。おそらく、そういう嬉しげな憧れの正反対に位置する小説だ。「すりきれた青春」というのは、ボリス・ヴィアンの本についていた惹句だけど、これをそのまま流用してもいい。すりきれてすりきれて、あげくに透明になった世界。それが西瓜糖の村だ。
この村の中心にある集会所というか共同宿舎の名は“アイデス”という。綴りはiDEATH。字面のままに読めば“私(I)”と“死(DEATH)”である。主人公たちはここで平和な日々をおくっているのだが、ある日、過去の文明が埋まっている〈忘れさられた世界〉から来た荒くれ者たちが乱入してきて、「アイデスがどういうものか、教えてやる」と叫ぶなり、いきなりナイフで自分の指や耳をそぎ落として自殺してしまう。
いったい、西瓜糖の村というのは、どういうところなのだろう。「訳者あとがき」では、次のように述べられている。
西瓜糖。西瓜糖は甘いだろうが、けっしてそれは濃厚な甘さではないだろう。西瓜の果肉のことを考えてみても、そこには過度な感じというのは不在だ。西瓜糖の村というのも、おそらくそういう場所なのだ。過度な感じ【・・・・】というのがなくて、屈折の少ない世界。透明で静かなのだ。(傍点原文のまま)
過度なかんじがないというのは、世界そのもののありかたであると同時に、そこに住む一人ひとりの「自分」が希薄だってことなのだろう。ぼくは勝手にそう思いこんでしまう。自分を強く持つことは、すなわち死にいたる道なのだ。だからといって、自分を薄くすることが幸福を保証するわけでもない。
自分が希薄であること。じっさい、語り手である主人公は「わたしは決まった名前を持たない人間のひとりだ」と表明しているし、荒くれ者たちの自殺を目の当たりにしながら、アイデスの住人はほとんど動揺していない。平然とモップで血をふきとっている。だからといって、彼らには感情がないというわけではない。ただ他人や世界に対しての関わりかたがひどく淡いのだ。
語り手は、子どものころ、両親を虎たちに殺されている。家族は川沿いの小屋に住んでいた。父は西瓜を育て、母はパンを焼いていた。ある朝、虎たちがやってきて、父が武器を手にする間も与えず、彼を殺した。そして、母も殺した。語り手は朝食の最中で、まだスプーンを手にしたままだった。虎たちは「怖がるんじゃない」と言う。子どもには手をださないから。虎たちは父や母を食べながら、あとでお話をしてあげようとか、悪いとは思うが生き延びるにはしかたないとか、おれたちだっておまえらとおなじ言葉をしゃべるし考えることだっておなじだとか、語りかけてくる。おさない語り手は、算数を手伝ってほしいと頼む。虎たちは親切に答えてくれるが、やがて算数の問題に飽きあきして、もうどこかに行ってくれと言う。
これが語り手が天涯孤独になったいきさつだ。そして彼は、アイデスへと移りすむ。やがて虎たちはいなくなってしまう。数頭の年老いたものが山に残っていたが、人々に狩られてすべて殺される。こうして〈虎の時代〉は終焉をつげた。
語り手はガールフレンドのポーリーンと、虎について話しあう。「きっと、ぼくらはむかしは虎だったんだ。ぼくらは変わったが、やつらは変わらなかった」というのが、語り手の説だ。しかし、彼はそれ以上、その考えを突きつめようとはしない。
西瓜糖の村や、消えうせてしまった虎、さらに遙かむかしに崩壊した〈忘れさられた世界〉……そこに隠喩や象徴を読みとろうとしたり、作品世界を「アメリカの病んだ現代社会をアイロニカルに表現している」的に解釈するのは、誤解とは言わないが、痩せた読みかただろう。人物たちの感情の起伏を、陽ざしの色や雨の音を描写するのとおなじような調子でたんたんと綴っていくブローティガンの筆致。そういう語りかたでしか、近づけない場所があるということだけでいい。
すりきれた透明感は、ブローティガンのすべての作品の基調になっている。たとえば、『鳥の神殿』という作品では、変わり者の夫婦ジョンとパットが、乗りすてられているクルマのなかに五十個のボーリング・トロフィーを見つける。彼らは自分たちのお気に入りである張り子の怪鳥ウィラードに、そのトロフィーをお供えする。狭い部屋の床一面がトロフィーでいっぱいだ。じつはそのトロフィーはローガン三兄弟の持ち物で、兄弟はトロフィーを盗みだした犯人に復讐しようと、アメリカ中を放浪しているうちに凶悪な性格へと変わっていく。いっぽう、ウィラードが鎮座ましましているアパートの上の部屋では、もう一組の若い夫婦が「O嬢の物語ごっこ」をつづけている。彼女が一夜のあやまちで拾ってきた性病がもとで、まともな交渉がもてなくなったふたりは、こんなかたちでしか愛情を伝えられない。
なんともやりきれない話だが、ブローティガンの文章からは悲惨さは伝わってこない。ウィラードが住むアパートも、またひとつのアイデスなのだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする