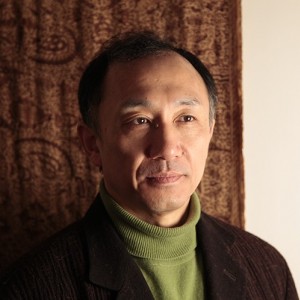書評
『家計からみる日本経済』(岩波書店)
一変する経済観、実感こもる政策提言
エコノミストの話は理屈をいじるばかりで実感に乏しいと言われる。その理由のひとつに、家計を起点として景気対策や生産活動、一国の豊かさなどを論じてこなかったことがある。消費は所得から貯蓄を差し引いたものであり、所得は生産がもたらすのだから、貯蓄や生産に焦点を当てて分析するならば消費についても論じたことになる。そういった説明がなされてきた。ところがいざ家計に焦点を当てると、金融システムや企業組織の劣化ばかりが伝えられた日本経済の光景は一変し、政策提言にも実感がこもる。これはそんな本だ。
紹介される事実が、意表をつく。日本の最低賃金は国際比較でも下位にあり、それ以下しか支払われぬ人も10%存在する。そればかりかその最低賃金は、生活保護支給額をも下回っている(働かぬ方が貰<もら>っている!)。年金・失業・医療・介護などの社会保障は、税に比して再分配に与える効果が十数倍もあるのに世界最低水準で、福祉は企業と家庭が担ってきた(日本は「小さな政府」である)。一部大企業では、中年雇用者が過酷な長時間労働を強いられている。90年代からのデフレで企業は売り上げ不振に陥ったと言われるが、企業が関係する卸売物価は80年代半ばから下がり続けている、等々。
ここから、斬新な提言が出てくる。雇用不安や社会保障への不信から、家計は景気に与える影響がもっとも大きい消費を抑えている。それゆえ70年代と同様、労働時間を失業者と分かち合い雇用を増やして人心を安定させ(ワークシェア)、煩雑な社会保障制度は公的に一本化して信頼を回復させよう。ビジネスの街・東京に機能を集中させるだけでなく、行政・文化・住みやすさなどで地方分権すべきだ、と。賛成だ。
社会保障の主な財源を税にしようなど、議論を呼びそうな提言もあるが、そもそも成長率ばかり追い求めぬ経済を作ろうというビジョンが骨太だ。
なぜ視点を移しただけで、主張が小泉内閣とこうも異なるのか(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2004年)。じっくり考えてみよう。
朝日新聞 2004年2月8日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする