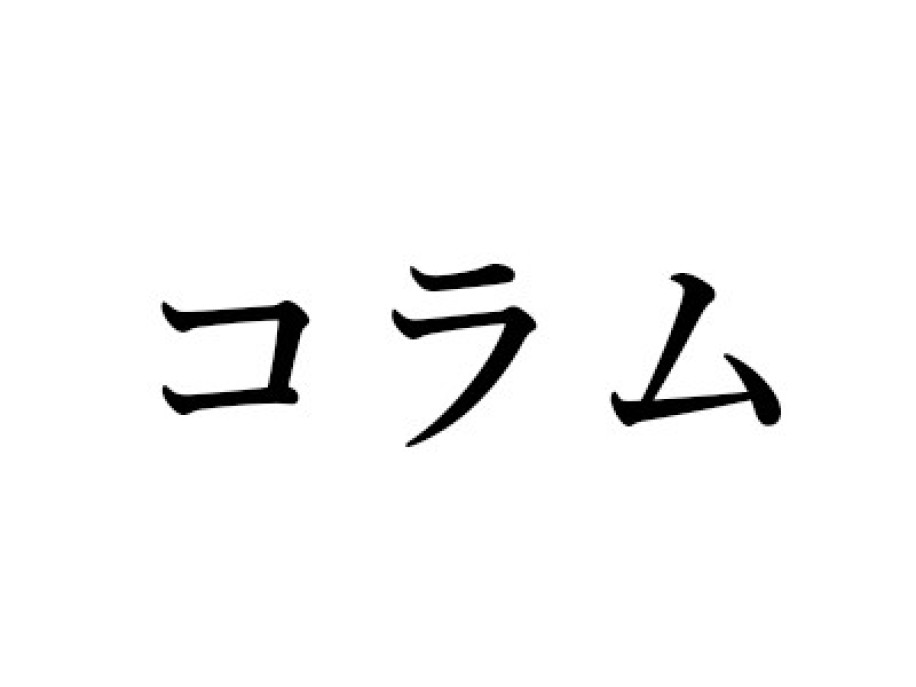書評
『私は一本の木』(みすず書房)
言葉と日常に幸福の鉱脈見る
真の知性は心によって育まれた言葉にこそ宿る。そのとき言葉は鍵となり、固く閉ざされていた心の扉を開け放つ。本書を手にする者は随所で、そうした手応えを感じることだろう。作者はいわゆる文学者ではない。岡山県にあるハンセン病療養施設長島愛生園で暮らしている彼女は今年、八十八歳になる主婦である。愛生園に来たのは十歳のときだった。本格的に文章を書き始めたのは八十歳を超えた頃だという。
だが、この本で私たちが出会うのは、掛け値なしで第一級の文学であり、情愛に満ちた想(おも)いで、人生を深く讃美する者の声である。
両親と暮らした日々の思い出に始まり、いくつかの耐えがたい試練を経て、今も寄り添い合うように暮らす夫との生活まで、五十余編のエッセイの主題はすべて、日常の出来事にとられている。作者は、日々の生活にこそ、豊饒(ほうじょう)な幸福の鉱脈があることをけっして見逃さない。
本書にはいくつか見過ごしてはならない言葉がある。「涙」もその一つだ。人は、悲嘆にくれたときにだけ涙を流すのではない。飛び上がるほどうれしいとき、感動が胸に押し寄せるとき、また、人生からの問いに直面し歯を食いしばるように生きているときにも人は、涙を流す。だが、「心の奥底で、ほんとうの私の涙を流すことをいつしか固く禁じていた」と作者が書くように、涙は、必ずしも目に見えるとは限らない。「ほんとうの涙」は、静かに心を流れているだけのこともある。
ハンセン病は完治する病気であり、また今日の日本においては発症や感染の事例は極めてまれである。しかし、特効薬もない時代では状況が違った。人々は苦痛と差別を強いられた。
作者もそうした苦境を生きた。長く、長所を見出(みいだ)せず、自分を好きになることができない。生きる力が尽(つき)そうになったこともある。しかし、今の彼女の実感は全く異なる。「あとがき」にはこう記されている。
やっとたどり着いたのです。生まれてきてよかった、らい患者でよかった。だからこそ、私はほんとうの人間の姿を見つけることができました。
絶望の底から救ったのは言葉だった。読むことによって彼女は、彼方(かなた)の世界とつながり、書くことによって、悲痛の経験の向こうに消えることのない光明を見出してきた。また、書くとは、胸の中を流れる涙で、地面に思いを刻むような営みでもあった。だからこそ、この本は、生きる希望と喜びに裏打ちされた、これまでにない幸福論にもなっているのである。
ALL REVIEWSをフォローする