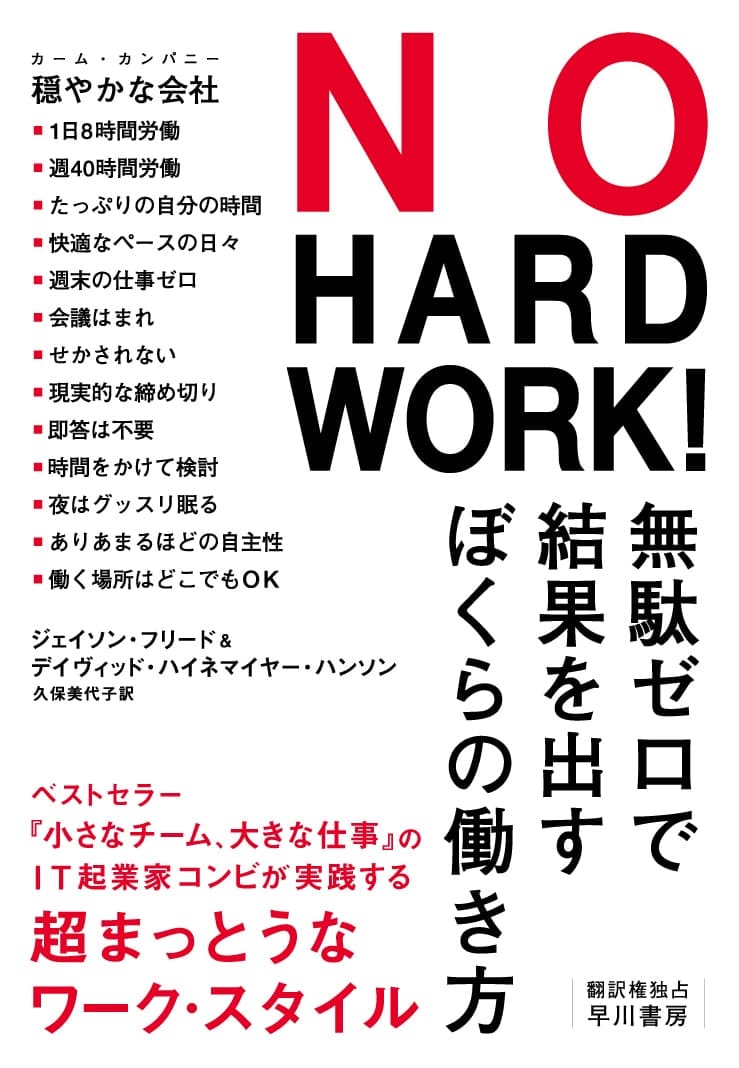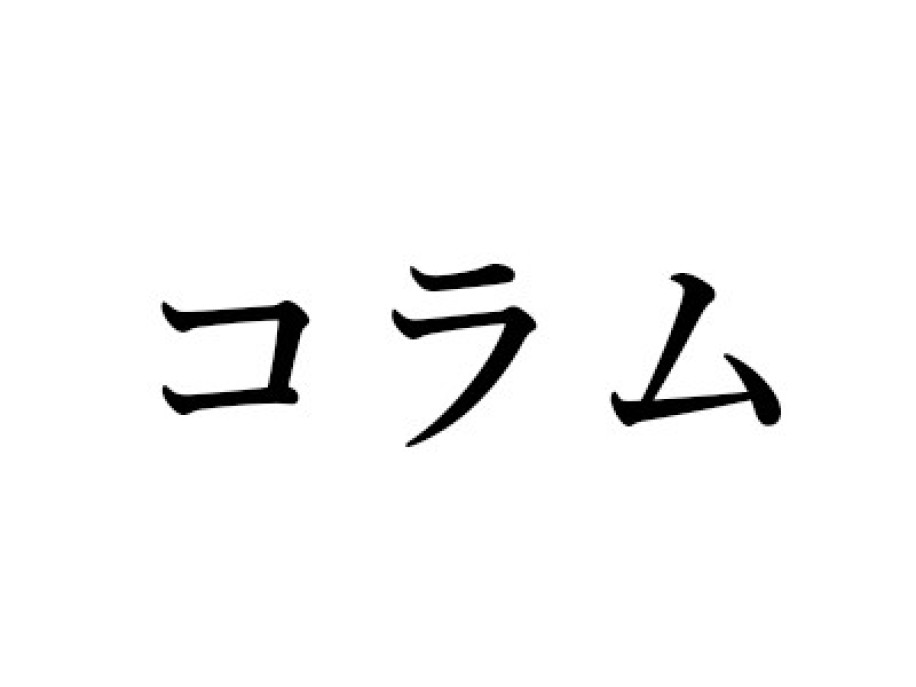書評
『ブック・ウォーズ――デジタル革命と本の未来』(みすず書房)
発見される個性、情報のブラックホール
電子書籍を読むための端末が相次いで登場した20年ほど昔、「紙の本はなくなるのか」「紙と電子は共存できるか」といった議論が盛んだった。しかし、いまも書店には紙の本が並び、ぼくらは紙の本を読む。何も変わっていないように見える。だが、目をこらすと、変わったところもたくさんある。たとえば日本の出版市場の3分の1は電子書籍で、そのほとんどは漫画だ。漫画の7割は電子書籍で読まれている。紙の本をネット書店で買う人も多い。
本書はデジタル革命(コンピューターとインターネットの普及)によって英米の出版界に何が起きたのかを調査した報告である。2013年から19年にかけて、英米の出版関係者に行った180件以上のインタビューがベースとなっている。著者は社会学者でケンブリッジ大学名誉教授。『第三の道』や『社会学』などで知られるアンソニー・ギデンズの弟子でもある。
デジタル革命で本の何が変わって、何が変わらないのか。結論から言うと、電子書籍の登場でもたらされたのは「本の新しい形態(フォーム)の発明ではなく、むしろ、本の新しい形式(フォーマット)の創造」だった。それはペーパーバックの登場と似たようなものだと著者は言う。
最初から読み始め、最後に向かって直線的に読み進めていくという本の形態は紙も電子書籍も同じだ。というか、現在の電子書籍は紙の本を再現しようとしているものがほとんど。動画をつけたり音楽をつけたりという試みはあったが、あまり広がらなかった。
本の形態は変わらなかったけれども、本の周辺ではいろんなことが起きた。序論にアンディ・ウィアーのエピソードが出てくる。アンディはコンピュータープログラマーとして働くかたわら小説を書いていたが、出版社もエージェントも彼の作品に関心を示さない。そこでアンディは自分のウェブサイトを立ち上げて作品を無料で公開した。こうして書き上げたのが長篇小説『火星の人』。
一部の読者が希望したのでアンディは電子書籍バージョンをつくった。さらに読者の希望で、アマゾンでも売るようにした。値段は99セント。たちまちアマゾンのベストセラーリストの上位になった。やがて出版エージェントからメールが来て大手出版社から本が出ることになり、映画会社が映画制作を発表した。リドリー・スコット監督、マット・デイモン主演の映画がつくられ(邦題は「オデッセイ」)、『火星の人』は海外でも大好評。日本では早川書房から出ている。個人がブログで書いた物語が世界的なベストセラーになり大ヒット映画になった。
デジタル革命があったからこそ『火星の人』は発見された。こういうことはかなり稀(まれ)で特殊な例ではないか、と思う人もいるだろう。しかし、同じようなことは現在の日本でも起きている。たとえば2024年の年間ベストセラー1位は雨穴の『変な家2』(飛鳥新社)だったが、この小説はネットから生まれた。最近のベストセラーリストにある獅子『メンタル強め美女白川さん』、新井すみこ『気になってる人が男じゃなかった』(共にKADOKAWA)もネットから生まれた。
デジタル革命は出版社に対して書き手の見つけ方や本のつくり方、宣伝方法、販売方法などを見直すように迫った。そして従来の出版業界以外のところで、本をつくったり読者に届けたりするしくみが生まれた。
従来の出版社=書店=読者という関係の外側でさまざまなことが起きた。たとえば自費出版の激増。アンディ・ウィアーのように、出版社を介さずに電子書籍を作って売ることが誰にも可能になった。クラウドファンディングで本を出す人もいる。映画や音楽と同じように定額読み放題のサービスも登場した。オーディオブックはテープやCDの時代から米国で盛んだったが、デジタルによってより広まった。そして、小説投稿サイトの盛況ぶり。日本でも「小説家になろう」や「カクヨム」をはじめ投稿サイトがたくさんある。
デジタル革命は出版社に読者との関係の大切さを認識させ、読者との関係を大きく発展させられるツールも提供した、と著者は述べる。紙の本は残った。CDの販売が激減してネット配信に取って代わられた音楽の世界とはずいぶん違う。
しかし、出版社とグーグルやアマゾンなど技術系巨大企業とでは出版の目的が違うという著者の指摘についてよく考える必要がある。出版社の目的は本を作って売ることだが、技術系巨大企業のそれは利用者のデータを集めること。ヤニス・バルファキスは新著『テクノ封建制』(集英社)において、デジタル機器を使うたびに意識せず技術系企業へデータを上納するぼくたちを「クラウド農奴」と呼んでいる。あるいは、ユヴァル・ノア・ハラリは『NEXUS』(河出書房新社)で「データ植民地主義」という言葉を使う。紙の本であれ電子書籍であれ、クリックしたりタッチするたびにデータが送られる。技術系巨大企業がトランプ&マスクにひれ伏す姿を見て、ぼくは不安を感じている。
ALL REVIEWSをフォローする