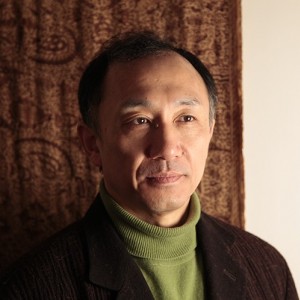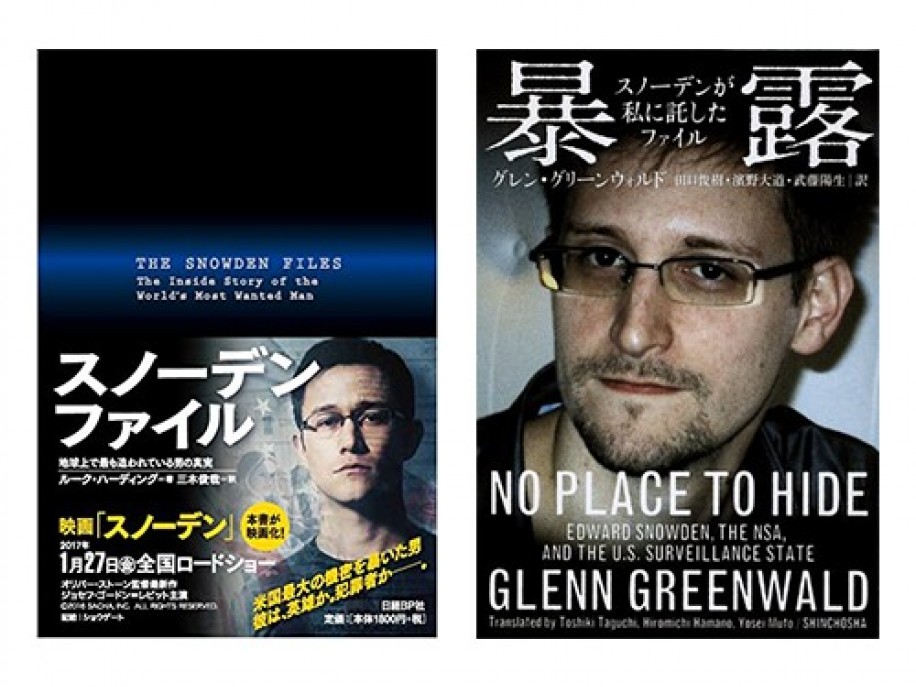書評
『ザ・トヨタウェイ』(日経BP社)
期待の方式を真に導入する原則とは
今年3月期決算で「純利益1兆円」を突破。販売台数でも米フォード・モーターを抜き、米ゼネラル・モーターズ(GM)に次いで世界第2位に躍り出ようとしているトヨタ自動車。株式時価総額に至っては約15兆円、ビッグスリーにメルセデスを加えた額をも上回る。名実ともに世界最強の自動車メーカーと言えよう。バブル経済を背景に八○年代後半に過大評価された「日本的経営」が忘れられても、「トヨタ生産方式」がいま内外で熱く語られるのは当然であろう。その秘密を探り学ぼうとする他社は後を絶たず、国内でも郵政公社が民営化の布石として導入したばかりだ。
ところが外国では、研究書でこそ「リーン生産方式」と呼ばれ評価が定まっているものの、適切な量の中間製品を作るために札を付けて回す「カンバン」や異常が発生したときに音や光で周囲に知らせる「アンドン」、5S(整理、整頓、清潔、清掃、しつけ)などのツールを取り入れた企業にも、顕著な成果は上がりにくいといわれる。著者はトヨタ生産方式の分析を専門とするのみならず、それが日本以外の国に普及する過程に直接にかかわってきた。それゆえ本書の読みどころは、トヨタ式経営が外国人の目にいかに映り、外国企業が模倣に失敗した理由をどう理解しているのかにあるといえよう。
印象深いのは、フォード主義のような大量生産方式が唱える「効率性」と、トヨタ生産方式にいう「ムダ取り」が異なるという比較論だ。前者は在庫にかかる場所代や欠陥品発生率を無視しており、消費者が購入してくれた時点で発生する「価値」から見直せば多くの過程がムダなのだという指摘は、いまなお多くの読者の目から鱗(うろこ)を落とすだろう。品揃(ぞろ)えをメーカー側の都合ではなく顧客の要望に合わせるという流通業における「買い手主導」の発想とも重なり、最近目立って増えたコンビニ発のプライベート・ブランド生産を先取りしているとも思える。
もう一点は、外国企業が導入に失敗する理由についての著者の判断である。「ムダ取り」のツールを躍起になって導入してもそれはトヨタ式経営の半面にすぎず、使いこなすにはその裏面を修得せねばならないという。それが「長期的な経営判断」「人間尊重とチームワーク」そして「継続的な改善と学習」で、合わせてトヨタウェイ14原則が詳述されている。
トヨタとは、危機感をもつ従業員たちが、何十年も先を見越し試行錯誤と改善を持続する稀有(けう)な組織体なのだ。ところが同僚であれ他者に「反省」を披露する文化は日本固有のものだから、外国ではとりわけ「カイゼン」の徹底が困難と著者は見る。だが我々は、反省しない日本企業も無数に存在することを知っている。トヨタ式は豊田家の特異な伝統なのか、日本文化の遺産なのか? 興味尽きない一冊である。
朝日新聞 2004年9月12日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする