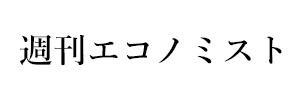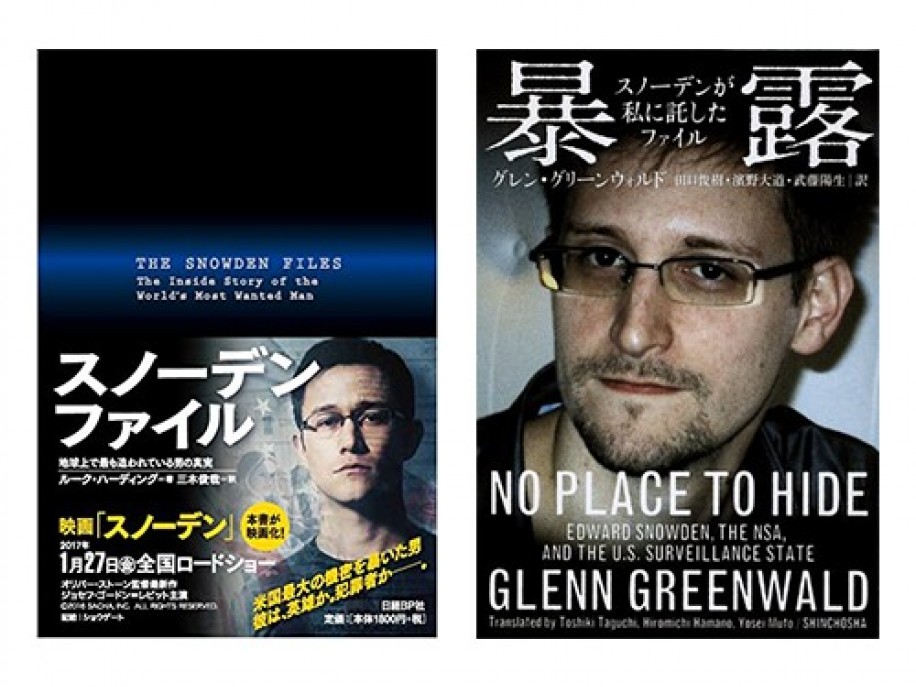書評
『ヤマト正伝 小倉昌男が遺したもの』(日経BP社)
「宅配便」の生みの親が遺した経営の神髄
社会インフラのイノベーション「宅配便」を生み出した希代の経営者、小倉昌男。本書は小倉の退任以降、ヤマトグループの経営を担った5人の社長の経営の軌跡と、彼らから見た小倉像を描く。小倉昌男は論理の人だった。彼が遺(のこ)したもの、それは経営の骨格となる論理であった。本書で繰り返し出てくる「サービスが先、利益は後」という論理はその典型である。戦略的意思決定の要諦はトレードオフにある。サービスと利益はそれ自体では二律背反の関係にある。両方を追求すれば「二兎(にと)を追うもの一兎をも得ず」。小倉は常に優先順位をはっきりさせる。
小倉の経営の神髄は、トレードオフを単純な選択の問題としないことにある。サービスを取って利益を捨てるわけではない。目的はあくまでも両方を達成することにある。ここで論理の出番となる。論理とは「XがYをもたらす」という因果関係についての信念である。因果関係である以上、論理は必ず時間を背負っている。要するに順番の問題である。ダントツのサービスを提供すれば利益は後からついてくる。荷物の受け手の満足を高めれば、やがて発送者はヤマトを選択する。
戦略の優劣は個別の打ち手そのもので決まるわけではない。戦略は箇条書きのアクションリストではない。打ち手が明確な論理でつながり、戦略が時間的な奥行きをもった「ストーリー」になる。ストーリーの中で表面的な二律背反が解け、好循環が生まれ、両方が実現される。ここに戦略の内実がある。
一人の経営者の求心力やカリスマと違って、論理には属人性がない。面白いことに、後任の5人は誰も「小倉昌男になろう」とは思っていない。彼らは「小倉さんだったらどうするだろう」と論理をたどることによって変化に対応し、難局を打開してきた。経営者が何代も代わっても、小倉イズムが脈々と継承されている理由は、それが論理の体系だからだ。
本書の白眉(はくび)は、東日本大震災を受けての当時の社長、木川眞(まこと)氏による「宅配便1個につき10円の寄付」──年間純利益の4割に相当する──という決断のエピソードだ。「サービスが先、利益は後」の真骨頂、「ヤマト魂」の本領発揮である。社会インフラを支える企業としての強烈な意志と矜持(きょうじ)を表明した。「人に人格があるように、企業も『社格』というものを高めなければならない」と小倉は言っていたという。死後二十数年、小倉の遺した論理の骨格は確かに一流の社格として結実した。
ALL REVIEWSをフォローする