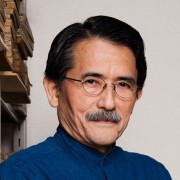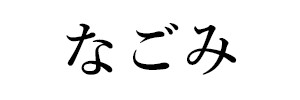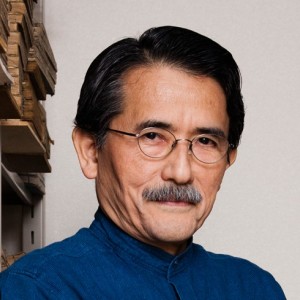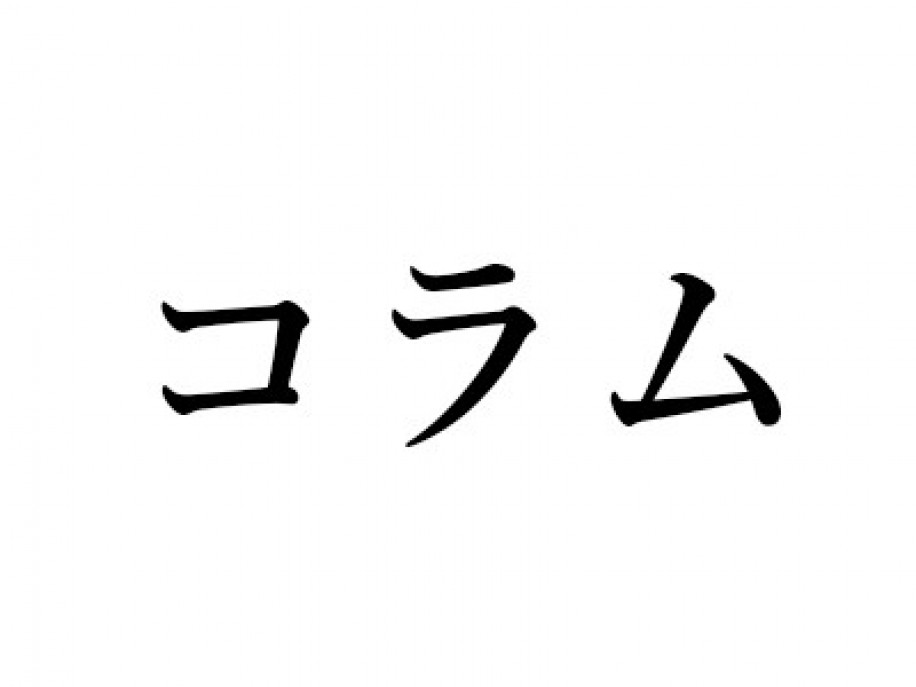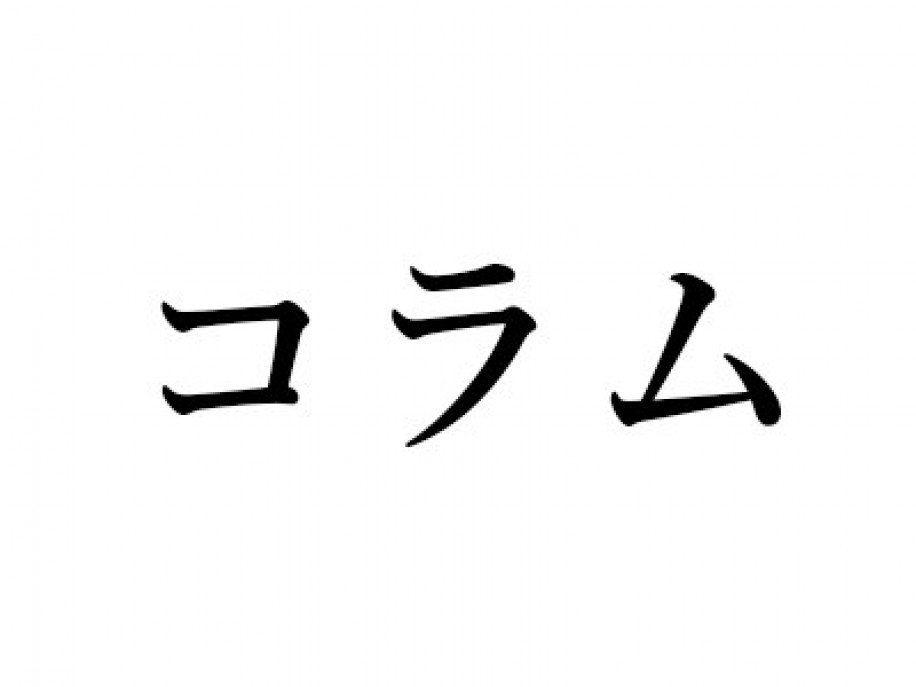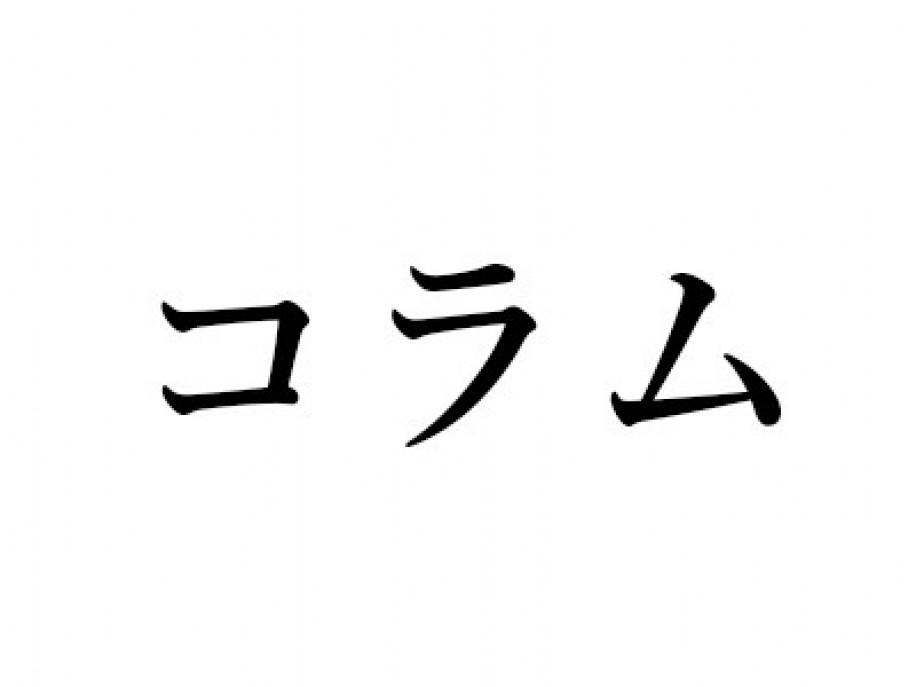書評
『闊歩する漱石』(講談社)
なるほどと頷きながら……
この二〇〇一年からちょうど百年の昔、一九〇一という年は、日本の近代にとって、とりわけて大切な意味を持っている(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2001年)。イギリスの十九世紀の大半を覆い尽くして二十世紀初頭一九〇一年まで続いたヴィクトリア女王の治世が、この年の正月に女王の崩御によってついに終わった。そうして、その前年の十月の末、夏目漱石が、ロンドンに到着し、二年あまりの留学生活を開始したのであった(彼は、到着後まもなく、ヴィクトリア女王の葬儀を、ハイドパークあたりで見物している)。
漱石がイギリスに於て、後の『文学論』に結晶するはずの猛勉強を重ねていたことは、これも有名な事実であるが、けれども、じっさいにその『文学論』と彼の作品を縦横に組みあわせて論じた書物は今まであまり書かれなかった。おそらく、国文学者の手には余るところがあったのであろう。
しかるに本書の著者丸谷才一さんは、もともと英文学の学者である。英文学を深く研究し、そしてそこから小説家に転じたという意味では、漱石を論ずるにこれほど適切な人もいなかろう。事実、この『闊歩する漱石』という丸谷版漱石論は、英文学と漱石文学と日本古典文学を縦横に斬り結んで堂々たる大論陣を張っているのであるが、といって、いわゆる学匠沙汰というのでは全然ない。もちろん、元来が英文学者だから、その論証は緻密なるアカデミズムの手順を踏みつつも、難しいことを平易に、かつ面白く「語りかける」名手丸谷さんの著作であるからには、少しも難しいことはなく、ははあ、なるほど、なるほど、と読んでいるうちに漱石がなぜにあのように面白いのかということが、すっかり腑に落ちる。
ところが、この本の特色は、漱石文学と言っても、そこらの漱石学者とはちがって、『坊ちゃん』『我輩は猫である』『三四郎』の初期三作品だけしか論じていない(実は私は、漱石はこの三つだけが面白いと思っているのであるが)。たとえば、あの痛快無比の(その故にまた漱石研究者たちからはあまり重要視されていない)『坊ちゃん』が、なぜあのように面白いかということが、『文学論』の物差しを当てることによって、残る隈無く論証されているのは、ただもう驚くばかりというほかはない。すなわち、山嵐と坊ちゃんが、野だいこをやっつける場面を論じて、漱石の文学論にいわゆる「不対法」、もっと一般的に言えば「擬英雄詩」の筆法を引き、ああそうかなるほどと思わせてくれるかと思えば、またそのつぎには、罵倒のセリフの面白さを論じるのに、歌舞伎から聖書まで驚くほど多彩な文献を引きあいに出して、それが「累積」というレトリックの見事な一例であることを教えてくれる。
こうして、丸谷さんの腑分けに従って、漱石の「喜劇(コミック)小説(ノヴェル)」を味わっていくと、漱石という人がいかに世紀を抽(ぬき)んでた大頭脳であったかが、いまさらながら痛感される。そうして、その漱石に文学の目を開かせたのが、まさにちょうど一世紀前のイギリスの天地だったのだ。つまり、一世紀前のイギリスが、日本の近代文学の基礎を作ってくれたのだと言うても決して外れないのである。そのことを改めて思い出させてくれたという意味でも、この本が今のこの時代に書かれたことの意味は小さくないのである。
ALL REVIEWSをフォローする