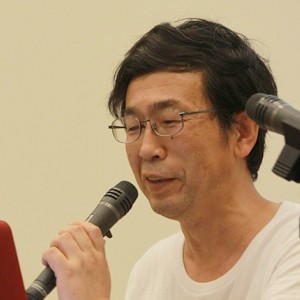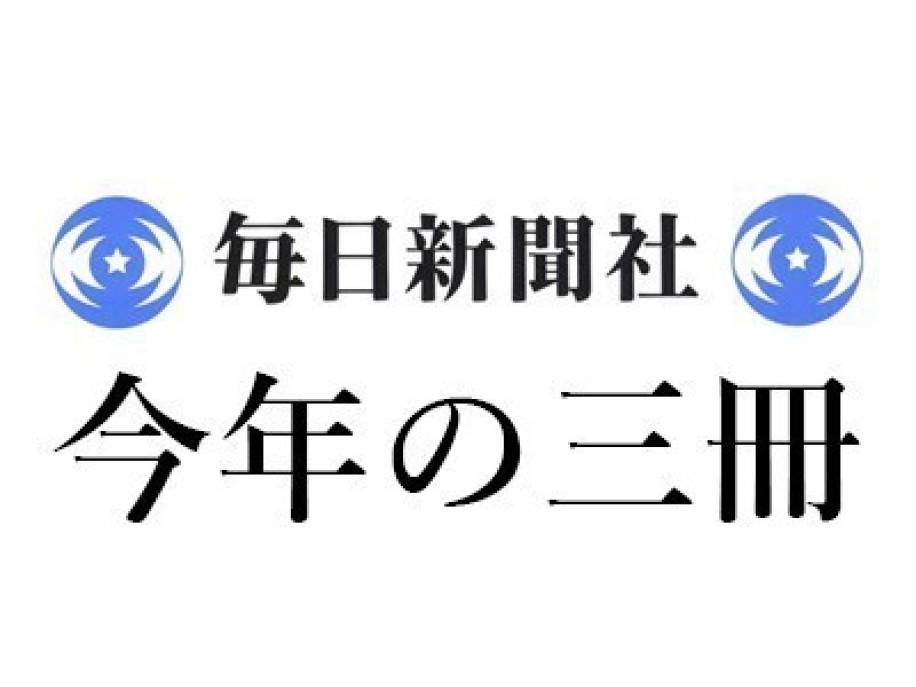書評
『魔法にかかった男』(東宣出版)
読者を不気味な世界へ連れ去る短篇
二十歳の頃だったか、あるホラー小説のアンソロジーで、イタリアの作家ディーノ・ブッツァーティの短篇「七階」を読んだ。それが評者にとって、ブッツァーティとの初めての出会いであり、そのときからブッツァーティのファンになった。正確に言えば、ブッツァーティを有名にした長篇小説『タタール人の砂漠』よりも、カフカ的としばしば評される、彼の短篇のファンになったのである。ブッツァーティの短篇と言えばまず思い出される、代表作の一つと呼んでもさしつかえない「七階」は、七階建ての病院に入院した男の物語である。そこは奇妙な病院で、下の階ほど重症の患者が割り当てられている。最初はごく軽い病状だからというので七階の部屋をあてがわれた主人公は、新しく入院した患者にベッドが足りないからとか、下の階の方が効果的な治療を受けられるからといった、もっともらしい口実で次第に下の階に移され、ついには瀕死(ひんし)の患者だけがいるはずの一階にたどりつく……。
この「七階」の例を見てもわかるように、ブッツァーティの典型的な短篇は、不可避な結末に向かって、まっすぐゆるやかに進行していく。そこには読者を戸惑わせるような、物語上の紆余(うよ)曲折はない。しかし、ごくありふれた日常から出発しているはずの物語は、知らないうちに、読者を見慣れない世界へ、あるいは不気味な世界へと連れ去ってしまう。その奇妙な感触はどこから派生しているのか、言葉に言い表すのはむつかしいが、フロイトが言う「不気味なもの」を想起してもそれほど間違いではないだろう。
本書『魔法にかかった男』は、そういったブッツァーティの持ち味が充分に楽しめる短篇集である。これまでにも、『七人の使者』『階段の悪夢』『待っていたのは』『石の幻影』『神を見た犬』といったブッツァーティの短篇選集が本邦でも数多く編まれてきたが、もう掘り尽くされたという感はまったくなく、『魔法にかかった男』にも相変わらず一定の水準を保った、いかにもブッツァーティらしい作品ばかりが集められているのには驚くほかない。その点では、カフカよりもむしろ、上質な短篇をコンスタントに書き続けた同じイタリアの作家アルベルト・モラヴィアに近い。
『魔法にかかった男』の中で、「七階」のように不可避な結末へと向かって静かに進行していく構造を持つのは、中学時代の同級生だと名乗る男が語り手の家に居候して、あげくのはてにすべてを乗っ取ってしまう「家の中の蛆虫(うじむし)」だろうか。表題作「魔法にかかった男」は、ふとした気まぐれで子供たちの戦争ごっこに加わった主人公が、そのおとぎの国の中で弓矢に射(う)たれて死ぬことで、惨めな現実世界に勝利する。「死」によってわたしたちの「生」の世界を裏返してみせるのも、『七人の使者』に収められた「大護送隊襲撃」などに見られるように、ブッツァーティが短篇で好んで取り上げたテーマだった。他にも、幻想文学愛好者の琴線に触れるのが「変わってしまった弟」で、素行の悪い弟が寄宿学校に入ってからはすっかり別人になったことに、語り手は困惑する。そのどうということはなさそうな話が、ブッツァーティの手にかかると、なにやら凶々(まがまが)しい物語に変貌してしまうのである。
ブッツァーティの短篇は、どの場所でもなく、どの時間でもないような、ある種の普遍性を獲得している。だから今の日本の読者にもおもしろく読める――とりわけ、いつのまにか七階から二階くらいへ下りてきたような感慨を味わっている、評者のような人間には。(長野徹訳)
ALL REVIEWSをフォローする