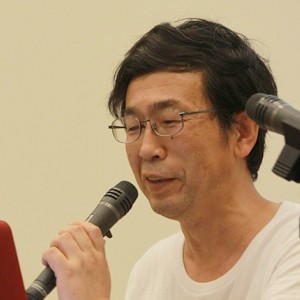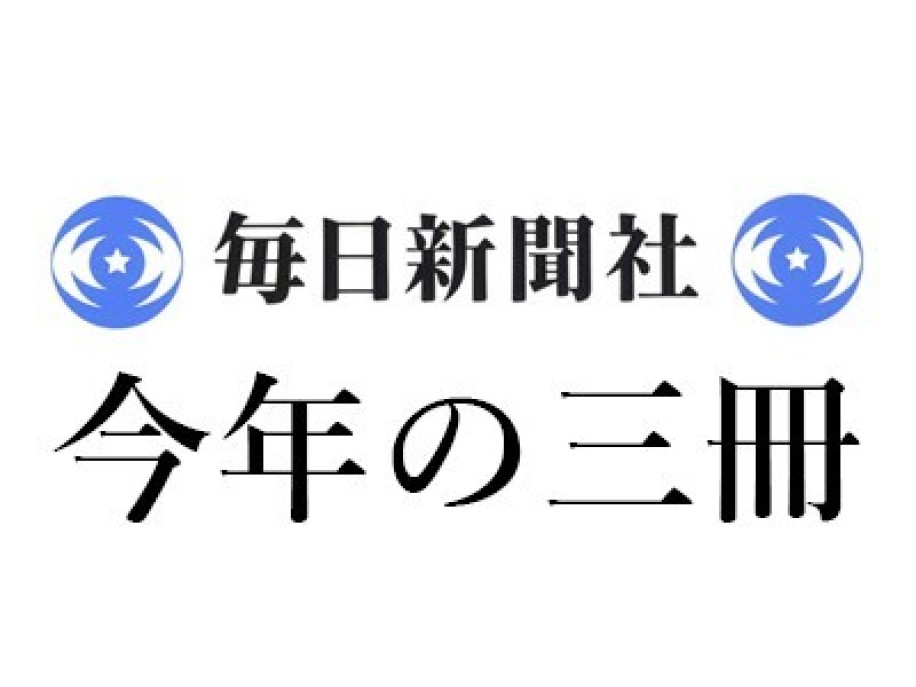書評
『グレアム・グリーン ある映画的人生』(慶應義塾大学出版会)
小説史、映画史のはざま 自由に泳ぐ
小説と映画という、異なるジャンル間の関係は、よく論じられるテーマである。しかしそこでありがちなのは、原作の小説とその映画化という問題設定だった。その場合、つねに前提となるのは原作の優位性である。映画化において、原作からこぼれてしまったものは何か、原作の小説的な部分がいかに映画的に処理されたか、などといった問題を論じているかぎり、それは小説にとっても映画にとっても有益な議論にはなりえない。グレアム・グリーンという、本邦でもおなじみの作家をとってみても、事情は同じである。グリーンと言えば、人はまず『第三の男』や『落ちた偶像』といった、キャロル・リードが撮った名作を思い浮かべる。そればかりでなく、グリーンの小説が原作になった映画は数多い。必然的に、グリーンと映画という問題は、グリーンの小説のアダプテーションという問題にすり替わる。本書『グレアム・グリーン ある映画的人生』は、そのような陥穽(かんせい)を避けつつ、グリーンが一九三〇年代後半に英国の『スペクテイター』誌で映画批評家を務め、その期間に四百本以上の映画を観(み)たという、シネフィルとしての体験が、小説家としての形成過程でいかに血肉になったかを論じた、刺激的な好著であり、グリーンの小説を読むようにスリリングだ。
著者のセンスの良さは、グリーンの小説作品と、グリーンが観た(あるいは、観たであろうと思われる)映画作品を抱き合わせにする、その意表を突いた選択に発揮される。『ここは戦場だ』とルネ・クレールの『自由を我等に』、『拳銃売ります』とヒッチコックの『三十九夜』というカプリングだけでも、読者を誘惑するのに充分だ。『第三の男』に西部劇の『ヴァージニアン』という取り合わせは、一見奇矯に思えるかもしれないが、男同士の絆というプロット構成から、グリーンが偏愛を抱いていた西部劇映画へと議論が接続されるとき、ロロ・マーティンズが西部劇小説家という設定だったことの重要性に、わたしたちは気づかずにはいられない。
ただ、そうした選択の妙だけが本書の美点なのでは決してない。文学作品における自由間接話法こそが映画的技法に対応するものだという指摘も含めて、著者はミクロなテキスト分析を用いながらも、マクロな二十世紀前半の小説史と映画史のはざまを自由に泳いでみせる。そこで問題となる異種混淆(こんこう)性は、「小説」と「エンターテインメント」を表面的に区別しながらも、ハイブロウとミドルブロウ、宗教的な世界と世俗的な世界をつねに見据えていたグリーンの、白と黒の境界が曖昧になる、いわゆる「グリーンランド」を正確にとらえている。
評者にとって本書のクライマックスだと思われるのは、『ブライトン・ロック』の横にジュリアン・デュヴィヴィエの『望郷』を置いた第四章だ。著者はまず、この小説をカトリック小説として読む伝統的な方法を示しながら、それを映画史的な文脈で読み直し、「フランスの詩的なリアリズム」へと視野を広げる。そして、ジャン・ギャバン演じるぺぺ・ル・モコが体現する、「神秘的などこか別の場所への逃走を夢見る閉じ込められた英雄たち」というイメージこそ、グリーンが『望郷』に読み取ったものであり、さらには『ブライトン・ロック』における主人公ピンキーの造形に寄与したものだと論じる。グリーンの本質を「詩的なリアリズム」だと見定めた、あざやかな論である。
エピローグに『情事の終わり』の小さなエピソードが置かれているのも、小説的かつ映画的な幕切れで、心憎いではないか。
ALL REVIEWSをフォローする


![第三の男 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51dTNXmv3AL.jpg)
![落ちた偶像 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51FHWXS5kvL.jpg)
![自由を我等に [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41Om2o7r2cL.jpg)

![ヴァージニアン [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41UuA-06XXL.jpg)
![望郷 [DVD] FRT-171](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51GXSDZ0%2BQL.jpg)