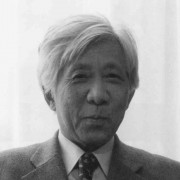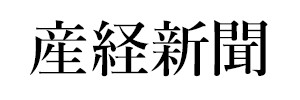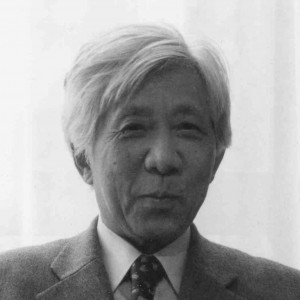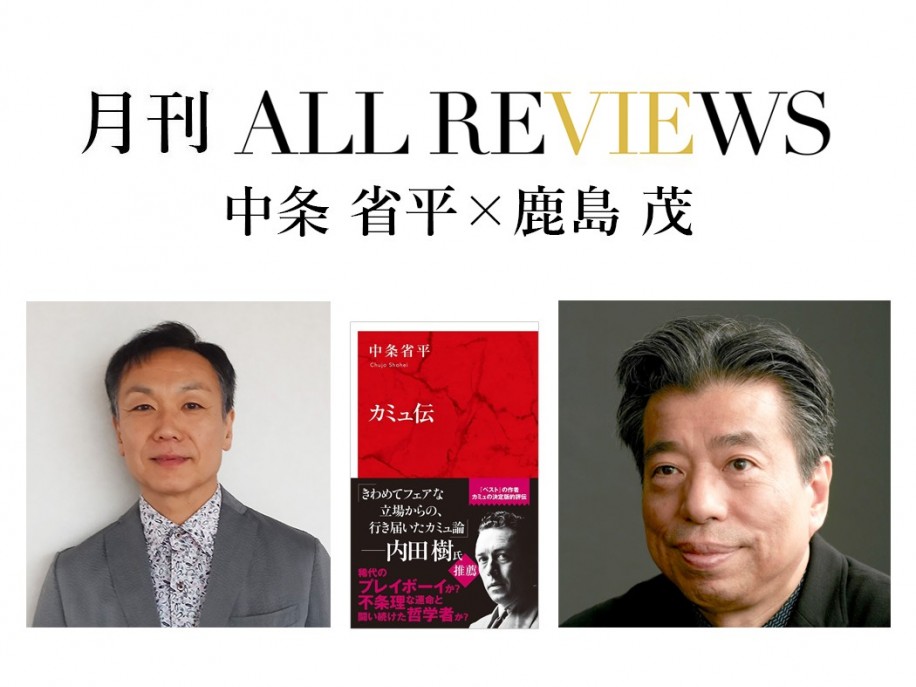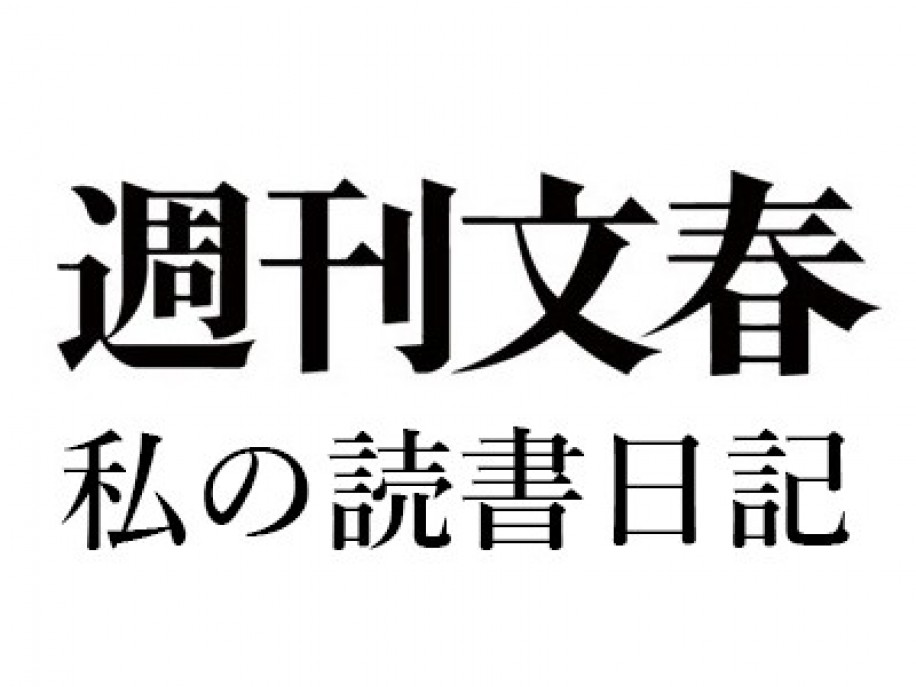書評
『すべては消えゆく』(白水社)
エロスと夢うつつのパリ奇譚
シュルレアリスムの小説というのは、もともと、言葉の矛盾である。小説は、何はともあれ、理性、知性の監視のもとに構築される文芸作品だ。無意識と夢をこそ第一義として、自動筆記という少々神がかりめいた制作方法を編み出したシュルレアリスムは、本来、小説制作には向いていない。アンドレ・ブルトン自身、名だたる小説嫌いだった。マンディアルグはブルトンの高弟だ。それでいて小説家になった。すると、どうなるか。できあがった作品に、人間の"劇"がない。人と人との葛藤がない。たとえ人間と人間の絡みあいが書かれていても、刑吏と囚人、執刀者と患者、コレクターと収集品みたいな関係しか成立しない。マンディアルグの小説は、だからすべて奇譚だ。この『すべては消えゆく』にしても同じことである。ロマンだと思って読みはじめたら弾き返される。
訳者の言葉を借りれば、「夢ともうつつともつかぬヒロインに導かれるままに、現実生活のなかの超現実性に参入する」話であり、「売春と演劇、つまり、エロスと幻影を二重のテーマとし、娼館と劇場という同心円的な宇宙を舞台にして、そこで、娼婦でもあり女優でもある双子のようによく似た宿命の女(ファム・ファタル)が、性と血の儀式を繰り広げる物語」である。
小説家として一家を成しただけあってマンディアルグは、この、エッセーがらみの長編散文詩とでも呼ぶべき作品に、地下鉄を使っての、リアルなパリの街歩きという枠をはめた。この枠を外したら小説にならないと知っているからだ。
男の特殊な性的強迫観念。これが作品の原動力である。そして、加虐者がいつのまにか被虐者になる。そこがこの小説の見せ場だ。マンディアルグは三島由紀夫の賛美者として有名だが、三島よりずっと"偏奇"の体質があらわな作家だった。遺作と銘打たれると、二十世紀もいよいよ終末、という感慨にとらわれる(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1996年)。
ALL REVIEWSをフォローする